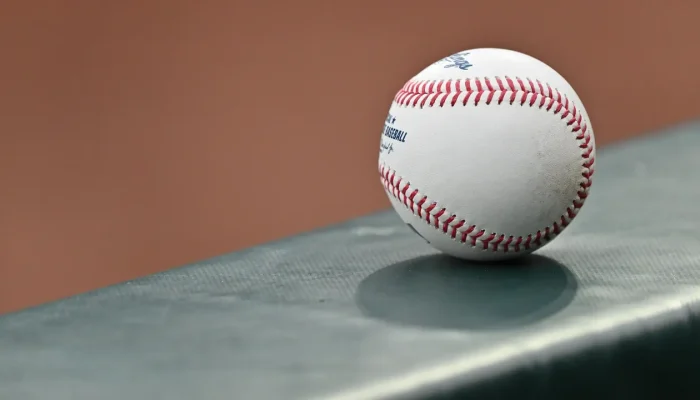なぜ球数制限だけが導入されたのか? 日本の野球育成年代に求められる2つの課題
いまなお旧態依然とした体制のままだというイメージも根強い日本野球界の育成環境にも少しずつ変化が起こっている。そんな中、育成年代にリーグ戦を定着させ、さらなる変化を起こそうと精力的に活動している人物が阪長友仁氏だ。2015年に阪長氏が創設したリーグ戦「Liga Agresiva(リーガ・アグレシーバ)」は、現在、全国各地で160校以上が参加している。そこで本稿では阪長氏の著書『育成思考 ―野球がもっと好きになる環境づくりと指導マインド―』の抜粋を通して、数多くのメジャーリーガーを輩出するドミニカ共和国の地で阪長氏自らが体感した育成環境と指導法を参考に、日本の野球育成年代に求められている環境づくりについて考える。今回は、日本野球界の現状と、さらなる発展が必要な2つの課題について。
(文=阪長友仁、写真提供=東洋館出版社)
日本の野球界にも変化。ルールができたこと自体は良かったが…
10年ほど前から、日本球界にもさまざまな変化が起こり始めています。最も顕著な例が「球数制限」でしょう。
小学生年代の学童野球では1日70球、中学硬式のボーイズリーグ(公益財団法人日本少年野球連盟)では1日80球、2日で120球という規定ができました(それまでボーイズリーグでは、1日7イニング、2日で10イニングというイニング制限のみ)。
以前は、骨が固まり切っていない=肉体的に成長過程にある少年少女の故障予防の観点から投球数を制限するルールがなかったことを考えると、大きな前進だと思います。
一方、高校野球では1週間で500球以内という規定が2020年春の甲子園大会から導入されました(同大会は新型コロナウイルスの感染拡大で中止)。エースが連投を命じられ、故障に至る例も少なくなかった過去を踏まえると、登板過多を防ぐルールができたこと自体は良かったと言えるでしょう。
ただし先発完投したとしても、1試合の球数は多くて150球程度です。あくまで単純計算ですが、1週間に完投を3回しても問題ないという数字です。この規定には、果たして実効性がどれくらいあるのか。メディアやSNSで侃侃諤諤(かんかんがくがく)の議論が起こりました。
私自身、核心をついていないと感じています。この内容では、甲子園大会などで連戦となった際、故障予防という目的を果たせないからです。
なぜ球数制限だけが導入されたのか?
なぜ、中途半端なルールになってしまったのか。
その要因は、「球数」しか考慮に入れられなかったからだと想像します。もちろん投手の故障予防は重要ですが、高校野球は育成年代であり、かつ教育の一環として行われていることを踏まえると、是非を検討されるべきものがほかにもあります。
その一つが金属バットです。日本で2023年まで使用されている金属バットは、国際大会では「規定違反」とされます。なぜなら反発力が強すぎて“飛びすぎる”からです。金属バットの反発力が高すぎると、打球スピードが速くなるため、特に投手やサード、ファーストには危険が高まります。加えて、バットを内から出すという〝正しいスイング〟が身につきにくい。そうした理由もあってドミニカでは中学生年代から木製バットが使用され、アメリカの高校年代の公式戦では「BBCOR」の認定を受けた低反発の金属バットが採用されています。
日本でも2024年から、金属バットに厚みを持たせることで飛距離を抑えたバットしか使えないという規定が設けられますが、BBCORのように反発計数に関する規定はありません。
金属バットは耐久性に優れるという利点がある一方、日本で2023年まで使用されているものは、世界基準で見ると明らかに飛びすぎます。つまり打者有利になるため、投手は直球勝負ではなく変化球でかわすピッチングになりやすい。
高校球児が育成年代であることを考えると、ストレートを磨いた方が将来の飛躍につながりやすいと思います。少なくともドミニカのサマーリーグではそう考えられ、スライダーや変化球の割合に制限がかけられています。
環境要因の課題。負けたら終わりのトーナメントでは…
二つ目はもっと大きな環境要因で、トーナメント戦という試合形式です。負けたら終わりだから、エースを引っ張らざるを得ない。論理としてはわかりますが、一発勝負のノックアウト方式は選手の育成や成長には最適ではありません。だからこそドミニカではリーグ戦が採用されています。
負けても“次”があるリーグ戦なら、そもそも選手個々に無理を強いる必要はありません。監督はリーグ戦をトータルで星勘定して、どうすれば勝ち抜けるかを考えて選手起用をしていけばいい。エースが故障して投げられなくなればチームにとっても痛いので、違和感があるのにマウンドに立たせるわけにはいきません。逆に言えば、控え投手やベンチメンバーにもチャンスが回ってくるということです。バッターはもし打てなくても、次の打席で取り返すチャンスがある。だから、思い切って振っていける。
ベンチで指揮する監督にも同じことが言えます。
負けたら終わりのトーナメントでは送りバントを指示するような場面でも、リーグ戦なら積極的に打たせていける。だからこそ私は、高校野球でもリーグ戦を導入するべきだと考えています。さらに言えば、実力拮抗したチーム同士のリーグ戦にして、多くの試合ができるようにすれば、切磋琢磨しながら成長していけます。2022年夏の高校野球千葉大会では「82対0」という試合がありましたが、どちらのチームにとっても得たものは少なかったはずです。
約10年前から野球人口減少に歯止めがかからず、高校野球でも「連合チーム」が増えてきました。一方、強豪私学では部員100人を超えるケースもあります。しかし、大会に出場できるのはどの高校でも1チームのみです。もし1校から複数チームがエントリーできるようになれば、せっかく野球をしたくてチームに入ったのにスタンドで応援しているだけ……という選手をなくすこともできます。
高校野球の先生たちと立ち上げた「リーガ・アグレシーバ」
選手たちが野球に最大限熱中し、自分自身やチームの成長につなげるためには、現行ルールのもっと大胆な変更を考えてもいいのではないでしょうか。
私がそう考える要因の一つは、近年、高校球児たちの考え方が大きく変わっているように感じるからです。
甲子園は魅力的な舞台である一方、自分の未来はもっと大事。そうして過密日程の中で連投をせず、チームメイトに大事な先発マウンドを託すという選択をする投手が出てきました。その一人が、天理高校のエースとして2021年春の甲子園に出場し、同年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団した達孝太投手です。
また、プロ側が評価する選手のタイプにも変化が生まれているように思います。例えば、2022年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに指名されたイヒネ・イツア選手。愛知県の誉高校時代には甲子園の出場歴がないものの、将来性を評価されて最高評価でプロ入りしました。
高校時代に無名だった一方、大学で成長して同年、東北楽天ゴールデンイーグルスに1位指名されたのが荘司康誠投手です。一般受験で新潟明訓高校に入学し、高校3年時は春も夏も初戦敗退。指定校推薦で立教大学に進学し、右肩の故障が癒えてきた大学3年から頭角を表すと、翌年、2球団競合でプロ入りしました。
選手の才能がいつ花開くかは、プロのスカウトにもはっきりと見えているわけではありません。だからこそ可能性の芽を大切に育みながら、できるだけ大きく飛躍できるような環境を整えていくことが大事だと思います。
そのために不可欠なのが、アマチュア球界にリーグ戦を導入することです。私はグアテマラから帰国した2014年、拠点を構えた大阪でそう訴え始め、同意してくれた高校野球の先生たちと翌年「リーガ・アグレシーバ」を立ち上げました。大阪の6校で始めたリーグ戦で、現在は全国で155校まで参加校が増えています(2023年6月26日時点)。地元で熱心に取り組んでいる公立高校から、甲子園の常連まで幅広く参加してくれています。
今の時代だからこそ、野球をする価値がある
リーガ・アグレシーバを広める上で大切にしているのが、単純にリーグ戦を行うだけにはとどまらないことです。「アグレシーバ」はスペイン語で「積極的に」という意味で、投球制限、木製バットや低反発バットの採用、スポーツマンシップ講習、指導者が学び続ける機会の確保など、選手たちが成長できる環境を整えています。まだまだ途上ですが、リーガ・アグレシーバに参加校が増えているのは、高校野球における指導者の価値観がそれだけ多様化している証左なのではないでしょうか。
今、社会の環境や世の中の価値観は、劇的なスピードで変化しています。同時に進んでいるのが少子高齢化ですが、深刻な野球人口減少は8倍の割合で進行しているというデータもあります。
では、野球の価値自体は変化しているのか。2023年WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で侍ジャパンが優勝して大きな感動をもたらしてくれたように、昭和の時代からまったく変わっていないと思います。それなのに競技人口が減っているということは、何らかの理由があるからでしょう。
常に変化し続け、混沌とした時代だからこそ、逆に野球をプレーする意義が高まっているのではと私自身は考えています。試合を通じ、選手たちは成功と失敗を数多く体験できるからです。真剣勝負の中で勝ち、負けを繰り返し、「次はどうすればうまくできるだろうか」と考えていく。体を動かし、喜怒哀楽を感じながら、スポーツマンとして成長していく。野球には、人々を幸せにできる価値があると心の底から信じています。だからこそ、関わる人たちがより成長できるような環境を整えていきたい。
(本記事は東洋館出版社刊の書籍『育成思考 ―野球がもっと好きになる環境づくりと指導マインド―』から一部転載)
【連載第1回はこちら】ドミニカ共和国の意外な野球の育成環境。多くのメジャーリーガーを輩出する背景と理由
【連載第2回はこちら】「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学
【連載第3回はこちら】なぜ指導者は大声で怒鳴りつけてしまうのか? 野球の育成年代に求められる「観察力」と「忍耐力」
<了>
ダルビッシュ有が考える“投げ過ぎ問題”「古いことが変わるのは、僕たちの世代が指導者になってから」
佐々木麟太郎の決断が日本球界にもたらす新たな風。高卒即アメリカ行きのメリットとデメリット
大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?
[PROFILE]
阪長友仁(さかなが・ともひと)
1981年生まれ、大阪府交野市出身。一般社団法人Japan Baseball Innovation 代表理事。新潟明訓高校3年生時に夏の甲子園大会に出場。立教大学野球部で主将を務めた後、大手旅行会社に2年間勤務。野球の面白さを世界の人々に伝えたいとの思いから退職し、海外へ。スリランカとタイで代表チームのコーチを務め、ガーナでは代表監督として北京五輪アフリカ予選を戦った。その後、青年海外協力隊としてコロンビアで野球指導。JICA企画調査員としてグアテマラに駐在した際に、同じ中米カリブ地域に位置する野球強豪国のドミニカ共和国の育成システムと指導に出会う。大阪の硬式少年野球チーム「堺ビッグボーイズ」の指導に携わりつつ、同チーム出身の筒香嘉智選手(当時横浜ベイスターズ)のドミニカ共和国ウィンターリーグ出場をサポート。さらには、2015年に大阪府内の6つの高校と高校野球のリーグ戦「リーガ・アグレシーバ」の取り組みを始め、現在では全国で160校以上に広がっている。2023年には一般社団法人Japan Baseball Innovationを設立し、野球界に新たな価値を創造する活動をさらに進めていく。
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training -
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion -
日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」
2025.06.16Opinion -
野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」
2025.06.06Opinion -
冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは
2025.06.06Opinion -
なでしこジャパン2戦2敗の「前進」。南米王者との連敗で見えた“変革の現在地”
2025.06.05Opinion -
ラグビー・リーグワン2連覇はいかにして成し遂げられたのか? 東芝ブレイブルーパス東京、戴冠の裏にある成長の物語
2025.06.05Opinion -
SVリーグ初年度は成功だった? 「対戦数不均衡」などに疑問の声があがるも、満員の会場に感じる大きな変化
2025.06.02Opinion -
「打倒中国」が開花した世界卓球。なぜ戸上隼輔は世界戦で力を発揮できるようになったのか?
2025.06.02Opinion -
最強中国ペアから大金星! 混合ダブルスでメダル確定の吉村真晴・大藤沙月ペア。ベテランが示した卓球の魅力と奥深さ
2025.05.23Opinion