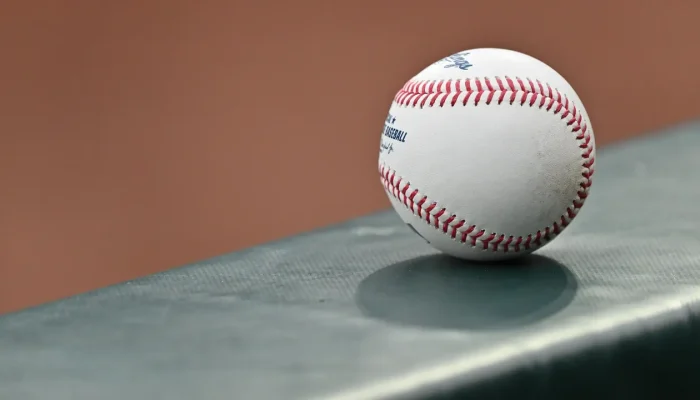新生なでしこ「ニルス・ジャパン」が飾った最高の船出。世界王者に挑んだ“強者のサッカー”と4つの勝因
初の外国人監督として招聘されたニルス・ニールセン監督の下で、初の国際大会「SheBelieves Cup」に臨んだなでしこジャパンが、3連勝で初優勝。ボール保持率で他の3カ国を上回り、パリ五輪を制した現・世界王者アメリカに13年ぶりの勝利を飾るなど、最高のスタートを切った。新監督の色とともに、短期間でチームが躍動した4つの勝因に迫る。
(文=松原渓[REAL SPORTS編集部]、写真=USA TODAY Sports/ロイター/アフロ)
難航した新監督選任から船出までの6カ月
世界一への希望を、再び抱かせる船出だった。
初の外国人指揮官であるニルス・ニールセン監督を招聘したなでしこジャパンが、世界女王を下す最高のスタートを切った。アメリカで行われた4カ国対抗戦「SheBelieves Cup(シービリーブスカップ)」で3連勝し、初優勝を飾ったのだ。3試合で10得点2失点。こんなスタートを、誰が予想できただろうか。
ニールセン監督が就任したのは昨年12月。
「海外リーグやUEFAチャンピオンズリーグでプレーするトップレベルの選手を指導できる」
「A代表を率いた経験、実績がある」
「日本女子サッカーや選手を知っている」
「戦術の引き出しが多い」
高いハードルを満たす候補者を巡る選考プロセスは難航したが、予定より3カ月近くずれ込んだ末に、デンマーク出身のニールセン監督が抜擢された。
左耳にピアスを光らせ、趣味はロックミュージック。目尻に刻まれた優しいシワと青く透き通った目に懐の深さを感じさせ、ユーモアも交えた言葉のチョイスには、日本が阻まれてきた「ベスト8の壁」という停滞感を打ち破ってくれそうな期待感があった。
目指すのは、「ボールを保持し、主導権を握る」スタイルだ。
主軸を固めて対応力を磨き、強豪国に対してカウンターに勝機を見出した池田太前監督体制の良い部分は引き継ぎつつも、サッカーの方向性は大きく舵を切った。戦術が多様化する欧州女子サッカー界で10年以上指揮を執り、直近ではマンチェスター・シティでテクニカルダイレクターを務めたニールセン監督の経歴は、その理想を理論面から支える。
同氏が求める選手像は、技術やフィジカル、経験値など特徴はさまざまだが、一貫しているのは、「メンタリティの強さ」だ。
「勇敢で、すべてを出し切る選手、リーダーシップを発揮できて、勝ちへの欲望を表現できる選手を求めています」
初陣となる今大会はまずコンディション面を重視し、指揮官はシーズン中の欧州で活躍する選手を中心に招集。23名中20名が海外組で、マンチェスター・シティ、チェルシー、リバプール、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘン……と、所属欄にはビッグクラブがずらりと並んだ。
「ミスは起こると思うし、(短期間で)スタイルに馴染めない部分もあると思うが、ミスをした後にどういうプレーをするかが重要。いかに競争力を見せて戦えているかがメインのポイントになる」
準備期間はほとんどなく「ぶっつけ本番」で今大会を迎えた日本は、移動を含む中2日の過密日程で、強豪オーストラリア、コロンビア、アメリカとの3連戦に挑んだ。
3試合すべてで上回ったボール保持率。「努力が実った」
初戦は、直近のオリンピックとワールドカップでベスト4に輝いているオーストラリアと対戦。シュート数18対1と力の差を見せつけた。
流動的に攻めながら、左の藤野あおばと北川ひかるのクロスに反応した田中美南が2得点。バルセロナの「ティキ・タカ」を彷彿させるパスワークから、浜野まいかが3点目を決め、最後はセットプレーから南萌華がゴールラッシュを締めくくった。
先発5人を入れ替えたコロンビア戦も、4対1で快勝。開始18秒、19歳の谷川萌々子が挨拶代わりの30m弾を叩き込むと、8分にはコーナーキックから田中が2点目。レアル・マドリードのヤングスター、リンダ・カイセドの反撃で1点を献上したものの、後半は1対1に強い19歳の新鋭・古賀塔子をカイセドにマッチアップさせて脅威を無効化。5つの交代枠を使い、浜野と田中のゴールで2点を追加して試合を決定づけた。
最初の2試合で、ニールセン監督はフィールドプレーヤー全員を起用。ボール保持率は2試合とも約6割と、誰が出ても質が大きく落ちないことを示した。
そして、タイトルがかかったアメリカ戦でも底力を見せつける。開始2分で長谷川唯のスルーパスから籾木結花が先制。守備の甘さを突かれて前半のうちに追いつかれたが、後半、古賀がセットプレーから押し込み2-1と勝ち越した。
アメリカは、チェルシーで一時代を築いたエマ・ヘイズ監督が昨夏に監督に就任し、戦術強化と世代交代を進めている。同監督が率いたパリ五輪の準々決勝でアメリカと対戦した際、日本はカウンター戦術でボール保持率は29パーセント(0-1で敗戦)だったが、今大会では51パーセントに上昇し、印象としても互角以上の戦いを見せた。対アメリカ戦の勝利は実に13年ぶり。それだけ価値のある勝利だった。
「チームとしてまとまって、勇敢に戦ってくれた。怖がらずにパスを回してくれたところは努力が実ったと思います。アメリカのように非常に強く、勝者のメンタリティーにあふれたチームを倒すことを目指しているし、今日は日本が上回ったと思う」
ニールセン監督は試合後、そう言って目を細めた。
チームを躍動させたルール「見るところが明確に」
短期間でこれだけチームが躍動できたのはなぜか? 勝因を4つ挙げたい。
1つ目は、ボール保持と選手間の意思疎通をスムーズにするために設定された、いくつかの「ルール」だ。
オーストラリア戦とコロンビア戦を終えた後の取材で、藤野はこう明かしている。
「ビルドアップで中央やインサイドの選手にボールをつけて、(相手が)中央に密集したところでサイドを使っていく、というように、『どういう攻撃をしたいか』『まずどの選手を見るか』という目標ができました。やらなければいけないことや、見るところが明確になったことが、初戦からスムーズにできた理由だと思います」
守備面にも変化は見られた。基本フォーメーションは4-3−3だが、守備時にはインサイドハーフの選手が前に出て4-4-2のように変形し、前線からの即時奪回を徹底。オーストラリア戦で守備の起点となった長野風花は、新しいトライに目を輝かせた。
「初めて2トップの(守備の)追い方をやったので、それがすごく新鮮でした。攻撃では中盤の3人がうまく関わりながらも形にとらわれすぎず、お互いを見てプレーして、ボールを前に運んでいくようにしています」
長野が言うように、ニールセン監督は「優先順位」を明確にしつつも、ピッチ上の表現は選手に委ねていた。選手たちは“ルール”と“自由”のバランスの中で臨機応変にプレーできたのではないだろうか。
2つ目は、前体制から主軸を大きく変えずに今大会に臨んだことだ。
ピッチ上の対応力は、個々の戦術理解度とともに、選手間のコンビネーションにも比例する。久しぶりの復帰となった籾木や三浦成美、宝田沙織も、年代別代表やクラブでプレーしてきたチームメートが多い。長谷川と籾木のコンビネーションで奪ったアメリカ戦のゴールは、年代別のなでしこジャパンでは幾度となく見てきた光景で、デジャヴのような感覚を覚えた。
ミスを恐れないメンタリティーと交代策も勝因
3つ目は、ニールセン監督が大会前にポイントに挙げていたメンタリティーだ。
どんな相手にも主導権を握る“強者のサッカー”を遂行するために不可欠な要素なのだろう。ミスを恐れず、チャレンジして自分のプレーを出し切ることが強調された。
「試合前のミーティングで(監督が)BE BRAVE(勇敢になれ)、ミスを恐れるな、チャレンジしよう、と言ってくれるので、その意識を高めて試合に臨んでいます」(北川)
「チャレンジしないで失敗しないことが一番ダメだと言われています。だからこそ、自分自身もチームとしてもチャレンジできていると思います」(古賀)
その挑戦者魂がチームに浸透し、藤野、浜野、谷川、古賀といった若手選手たちがのびのびとプレーできたことは、今大会の大きな収穫だ。谷川は、「一人一人が監督と話す時間を設けてもらい、コミュニケーションを積極的にとってくれました」と、新監督の印象を口にした。
4つ目は、的確な起用と交代策だ。
過密日程の中でケガ人が出ないよう、全員の出場時間をうまくコントロールしながら、複数ポジションで起用。リードを守りたい場面でも采配に躊躇がなく、チャレンジを促す姿勢が選手にも伝播しているように感じた。
しいて気になったポイントを挙げるとするなら、いくつかのピンチを招いた攻撃時のミスだ。高い位置で奪った時はいい距離感で攻撃につなげられるが、自陣で失った際の人数や距離感のバランスには改善の余地を感じる。とはいえ、チームはスタートしたばかり。ハイプレスを仕掛けてくる相手をビルドアップでどういなすのか、これからニールセン監督の手腕に期待したい。また、同氏は国際大会における日本の課題として「スプリント能力と持久力」を課題に挙げており、それも今後の強化ポイントになりそうだ。
新キャプテンの人選にも注目
今年度は残り6回の活動が予定されており、次は4月6日に大阪で行われるコロンビア戦となる。3月には国内のWEリーグが開幕し、7月には東アジアE-1選手権も行われるため、国内組にもチャンスが広がる。
また、コロンビア戦までには決定しているであろう新キャプテンの人選にも注目したい。今大会は「いろいろ見てみたい」という指揮官の意向で試合ごとにゲームキャプテンが変わり、オーストラリア戦は長谷川、コロンビア戦は南、アメリカ戦は熊谷紗希がキャプテンマークを巻いた。表彰式で優勝カップを掲げたのは、チーム最年長で、なでしこジャパンを長くリーダーとして率いてきた熊谷だった。
「初めて新監督の下で戦って、タイトルを取れたことはすごく大きいことですが、この優勝をいい自信にして、世界で戦えるなでしこになれるよう、個々が自チームでさらに強くなれるように頑張りたいと思います」(熊谷)
挑戦者のメンタリティーで理想のサッカーを貫き、最高の結果を勝ち取ったニルス・ジャパンは、再び世界のトップに返り咲くための力強い一歩を踏み出した。
<了>
女子サッカー過去最高額を牽引するWSL。長谷川、宮澤、山下、清家…市場価値高める日本人選手の現在地
[インタビュー]藤野あおばが続ける“準備”と“分析”。「一番うまい人に聞くのが一番早い」マンチェスター・シティから夢への逆算
[インタビュー]チェルシー・浜野まいかが日本人初のWSL王者に。女子サッカー最高峰の名将が授けた“勝者のメンタリティ”とは?
[インタビュー]なでしこJの18歳コンビ・谷川萌々子と古賀塔子がドイツとオランダの名門クラブへ。前例少ない10代での海外挑戦の背景とは?
[インタビュー]なでしこジャパンの小柄なアタッカーがマンチェスター・シティで司令塔になるまで。長谷川唯が培った“考える力”
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business -
「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案
2025.06.25Business -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion -
日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」
2025.06.16Opinion -
野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」
2025.06.06Opinion -
冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは
2025.06.06Opinion -
なでしこジャパン2戦2敗の「前進」。南米王者との連敗で見えた“変革の現在地”
2025.06.05Opinion -
ラグビー・リーグワン2連覇はいかにして成し遂げられたのか? 東芝ブレイブルーパス東京、戴冠の裏にある成長の物語
2025.06.05Opinion -
SVリーグ初年度は成功だった? 「対戦数不均衡」などに疑問の声があがるも、満員の会場に感じる大きな変化
2025.06.02Opinion -
「打倒中国」が開花した世界卓球。なぜ戸上隼輔は世界戦で力を発揮できるようになったのか?
2025.06.02Opinion -
最強中国ペアから大金星! 混合ダブルスでメダル確定の吉村真晴・大藤沙月ペア。ベテランが示した卓球の魅力と奥深さ
2025.05.23Opinion