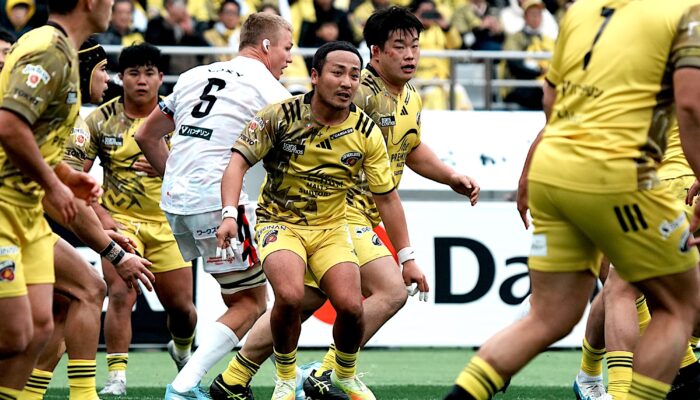なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
欧州サッカーの舞台でU-23年代の若き才能がしのぎを削るUEFA U-21欧州選手権。現地取材で見えてきたのは、戦術トレンドを追うだけでは勝てないという現実だった。戦術的柔軟性とビルドアップの巧みさ、1対1での強さ、そして選手個々の意識とタスク遂行力。なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか。A級ライセンス(UEFA-Aレベル)を有するサッカー指導者であり、サッカーライターでもある中野吉之伴氏の視点で、大会を通して見えた世界最前線のフットボールの「スタンダード」と「進化」を読み解く。
(文=中野吉之伴、写真=ロイター/アフロ)
CL王者・パリSGがもたらした「戦術上のフレキシブルさ」
UEFA U-21欧州選手権を現地取材してきた。なおU-21欧州選手権は予選開始時の年齢条件でつけられた名称であり、本大会開催時でU-23年代ということになる。つまり2025年大会の場合、2002年1月1日以降に生まれた選手が出場できる。そのため、実際はU-23代表ということになる。
今大会では16カ国が予選を勝ち残り参戦したわけだが、特にグループリーグを突破したドイツU-23、イングランドU-23、スペインU-23、フランスU-23、オランダU-23、ポルトガルU-23、イタリアU-23、デンマークU-23の8カ国は、どこも高いクオリティのサッカーを披露していた。
そこで本稿では実際にスタジアムで取材をした試合を中心に、今大会の各国サッカーを分析し、傾向と対策を考察してみたいと思う。
トップレベルのサッカーにおいて、戦術上のフレキシブルさはもはや当たり前。先日ミュンヘンで開催された育成指導者カンファレンスに参加してきたが、ドイツサッカー連盟(DFB)育成ディレクターのハネス・ヴォルフが自身の講義でこんな話をしていた。
「戦術論が好きな指導者やアナリストは、システムやポジショニングで現象すべてを分析しようとするが、果たしてそれがどこまで有効なのだろう。2024-25シーズンでCL(UEFAチャンピオンズリーグ)を制したのはパリSGだった。彼らの試合ごとにおけるポジショニングやタスクワークをシステムで解き明かすことができるだろうか?」
そう言ってヴォルフはモニターにCL決勝の映像を写した。相手の状況や時間帯に応じて、システムを変更させて優位性を保つことはこれまでにも見られたし、「可変式システム」という表現で分析されたりしていた。ただパリSGのそれは、わずか数十秒ごとに変わる。ベースとなるポジションやシステムは存在しているが、実際には流動的に変化し続けており、固定的な配置はないに等しい。それでいて、全体のバランスが崩れないし、プレー原則はブレない。他の強豪クラブにもそうした傾向はあるが、パリSGほど頻繁に、そしてスムーズに対応できているクラブはない。
そうした世界のトレンドがある中で、U-21欧州選手権ではそこまでの多様さはないものの、それでもチームとしての戦術的柔軟性と個々のタスクワークアップは上位進出チームに見られた。
チームとしての狙いが明確。「クロースロール」を見せたり…
欧州におけるサッカー研究と落とし込みのスピードはとても速い。パリSGが見せた自分たちのキックオフ時のボールを敵陣深くに蹴り込んで、相手スローインからプレスに持ち込む戦略を、今大会ではスロベニアがすぐに見せていた。相手スローイン時は一番自分たちが意図的にプレスに入れる状況でもある。プレスからのボール奪取を出発点にゲームデザインするのは興味深い。
ビルドアップの巧みさと種類の豊富さではスペインとドイツが素晴らしかった。GKがボールを収めて、相手FWを自分に引き寄せてからパスを展開し、相手のファーストプレスを回避する術がうまい。またあえて、低めの位置にポジショニングを取り、相手のハイプレスを誘発し、中盤にできたスペースに縦パスを送り、FWのポストプレーから素早い攻撃へ移行するなど、チームとしての狙いが整理されている。
相手の布陣やプレスの位置に応じて、ボランチの一枚がサイドへ下がってパスを引き出す「クロースロール」を見せたり、センターバックがボールを運んだ後にそのまま流れに乗って前線までオーバーラップを仕掛けたりと、状況に応じて変化をもたらすプレーを見せる選手が多くいた。そして周りの選手もスペースカバーに動いたり、サポートへ動き直したりと、連動した動きが浸透している。
FWにパスを当てる局面でスペースを作るコース取りがうまかったのがイタリア。中盤の選手が相手ボランチをうまく誘い込むところへのフリーランで中盤にスペースを作り出し、そこへタイミングよくFWが顔を出して巧みに攻撃の起点となった。
イタリアは、相手の狙いに応じて対策が常に準備されているのも特徴的だった。相手のビルドアップに対して、FWがGKへは絶対に食いつかずに、我慢強くポジショニングをとり続けるようになる。そして中盤のスペースを空けすぎず、相手のロングを推測し、ボランチが準備。そうすることでボール回収率が上がる。
優勝したイングランドは何が優れていたのか?
攻撃戦術に関してはバリエーション的にも、浸透のさせ方にもまだまだ大きなポテンシャルがあるとされている。トップレベルのサッカーでは、相手がプレスにくる位置と人数に応じてビルドアップからのバリエーションを多数準備している。いずれにしても上位進出したどの国でも共通していたが、自分たちの時間帯をどのように作り出し、そこからどのようにゴールへ結び付けるのかへの共通認識がきれに整理されていた。
「ビルドアップを大事にする=縦への勢いを出せない」というわけではない。さまざまなトレンドがある中で、取り組むべきことが増えたり、深まったりしていくが、それぞれの要素をなかったこととして切り捨てるのはまた違う。ビルドアップだけになるのはよくないが、ビルドアップを捨てるのはまた違うのだ。
もちろんU-23年代だと、まだそのバリエーションの種類も、それぞれの精度も十分ではない。ハイインテンシティで連続プレスをかけてくる相手と対峙すると、そのプレッシャーとストレスの中で最適な決断ができずに、ミスパスを次々にしてしまう試合も少なくはなかった。互いに見ながら見られながらプレーするのが本当にうまいスペインにしても、イングランドの迫力あるプレスには屈してしまった。
特に一発勝負の決勝トーナメントからは、それまで以上に負荷がかかってくるので、そうした状況下でもゲームプランを貫くのは、非常にタフ。だからといって、そもそも選択するチャレンジもせずに、ロングボールばかりを蹴り込むことは、選手にとっても、チームにとってもプラスにはならない。実際に優勝したイングランドと準優勝のドイツには、相手への対策とゲームプランの遂行力があった。さらに、選手交代を戦術的に活用して試合の流れに変化をもたらす総合力も備えていた。
トレンドを追うだけではうまく機能しない
また忘れてはいけないのは、トレンドとスタンダードは違うということ。前述した戦術的バリエーションの豊富さと選手タスクの多様性が効果的に作用するためには、モダンサッカーのスタンダードとして、ハードワーク、フィジカルコンタクト、ハイインテンシティのレベルがしっかりあり、激しいプレッシャーを受けながらでも的確なプレーができるスキルが定着していることが挙げられる。
特に近年では数的有利を作ってからそこでプレスをかけてボールを奪取するのではなく、数的同数下でプレスをかけるチームが増えてきている。1対1の状況で奪いやすい状況を作り出し、相手の前に出て奪い切ることができる選手が重用されているのはそのためだろう。そうなると守備への要求平均値としても、1対1で振り切られる選手がピッチに立つのは厳しい。
ポルトガルは中盤ひし形の4-4-2を基本システムとして、アンカーではポルトガル2部のヴィゼーラでプレーするディオゴ・ナシメントが担っていた。ベンフィカの育成育ちの技巧派MFは小柄な体格ながら、競り合いにも強く、ポルトガル代表MFヴィッチーニャのように積極的にボールをもらい、巧みなドリブルとパスで相手陣内へうまくボールを運べていた。体が小さいから競り合いを避けるのではなく、どのようにアプローチしたら勝てるのかにフォーカスして取り組むことが大切なのだろう。
サッカーはトレンドを追うだけではうまく機能しない。
ユース年代から1対1での強さや駆け引き、ハイインテンシティでもクオリティの高いプレーをし続けられるだけのフィジカル能力、連続でハードワークし続けるメンタリティが備わってくることが望ましい。そのためにはジュニアやジュニアユース年代で、その準備がされていることも必要になる。それらが当たり前のベースとしてあったうえで、本稿で紹介したように戦術的なバリエーションを増やし、個人タスクを多様化させていくことが同時に求められるのが世界最前線のサッカーの流れといえるだろう。
【連載後編】「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
<了>
「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果
ユルゲン・クロップが警鐘鳴らす「育成環境の変化」。今の時代の子供達に足りない“理想のサッカー環境”とは
なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは
新生イングランド代表・トゥヘル新監督の船出は? 紙飛行機が舞うピッチで垣間見せたW杯優勝への航海図
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」
2026.02.26Education -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」
2026.02.20Career -
「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念
2026.02.20Career -
ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断
2026.02.20Career -
名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持
2026.02.13Career -
WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏
2026.02.13Business -
新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」
2026.02.12Business -
「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断
2026.02.12Career -
女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割
2026.02.10Career -
なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性
2026.02.10Business
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方
2026.02.09Training -
スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体
2026.01.05Training -
「木の影から見守る」距離感がちょうどいい。名良橋晃と澤村公康が語る、親のスタンスと“我慢の指導法”
2025.12.24Training -
「伸びる選手」と「伸び悩む選手」の違いとは? 名良橋晃×澤村公康、専門家が語る『代表まで行く選手』の共通点
2025.12.24Training -
サッカー選手が19〜21歳で身につけるべき能力とは? “人材の宝庫”英国で活躍する日本人アナリストの考察
2025.12.10Training -
なぜプレミアリーグは優秀な若手選手が育つ? エバートン分析官が語る、個別育成プラン「IDP」の本質
2025.12.10Training -
107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学
2025.11.17Training -
「やりたいサッカー」だけでは勝てない。ペップ、ビエルサ、コルベラン…欧州4カ国で学んだ白石尚久の指導哲学
2025.10.17Training -
何事も「やらせすぎ」は才能を潰す。ドイツ地域クラブが実践する“子供が主役”のサッカー育成
2025.10.16Training -
“伝える”から“引き出す”へ。女子バスケ界の牽引者・宮澤夕貴が実践する「コーチング型リーダーシップ」
2025.09.05Training -
若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり
2025.08.22Training -
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training