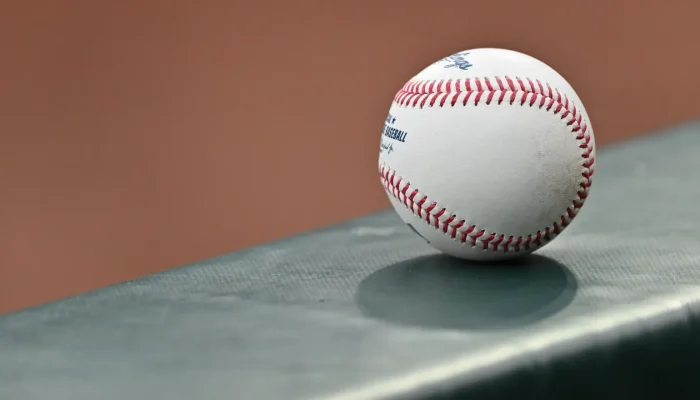「フットサルとモータースポーツに、イノベーションを」スポーツ庁とスクラムスタジオが取り組むスポーツの拡張
この度スポーツ庁とスクラムスタジオが手を組み、スポーツイノベーションを推進するプログラム「SPORTS INNOVATION STUDIO(スポーツイノベーションスタジオ)」が産声を上げた。本記事では、コラボレーションパートナー(実証連携団体)に決定している日本フットサルトップリーグを運営するFリーグと、四輪モータースポーツ統轄団体の一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が「SPORTS INNOVATION STUDIO」のオープンイノベーションプログラムに参加した経緯やねらい、両団体がかかえている課題と今後の展望について話を聞いた。
(インタビュー・構成=五勝出拳一)
費用やメンタリングサポートも…室伏広治長官率いるスポーツ庁から支援を受けられるチャンス
2023年7月19日、ミッドタウン日比谷のBASE Qにて「SPORTS INNOVATION STUDIO」プログラム説明会が開催された。「SPORTS INNOVATION STUDIO」はオープンイノベーションとコンテストの2つで構成され、スポーツ庁が取り組む「スポーツオープンイノベーションプラットフォーム(SOIP)」を加速させるための取組みとして位置づけられている。冒頭、スポーツ庁・室伏広治長官より主催者あいさつがあり、スポーツ庁からの最大限の支援を約束するとともに、本プログラムへの積極的な参加を呼びかけた。
「SPORTS INNOVATION STUDIO」オープンイノベーションのコラボレーションパートナーにはFリーグとJAFの参画が決定しており、採択された企業・団体は両社との事業共創機会が与えられる。加えて、経験豊富なメンター陣によるメンタリング機会やスクラムスタジオが有する多様かつ世界規模のネットワークへのアクセス、共創期間中の実証実験や新規開発に関するサポート費用も提供が約束されており、リソースやネットワークが限られるスタートアップにとっては、またとない機会となっている。プログラム説明会の中では、コラボレーションパートナーであるFリーグとJAFの担当者より、オープンイノベーションにかける期待や事業共創のテーマが伝えられたので、その内容をお届けしたい。

「見る」を強化し、Fリーグの価値向上サイクルを回したい
小野寺:私はFリーグで副理事長兼専務理事を担当しております。今、Fリーグは北は北海道から南は九州まで全国21チームで構成されており、Jリーグと同じようにディビジョン1とディビジョン2に分かれています。今年から愛媛県にミラクルスマイル新居浜というチームができて、9地域がやっと出そろうかたちになりました。昨年開催された「AFCフットサルアジアカップ」では、フットサル日本代表が見事8年ぶり4度目の優勝を果たしまして、着実に競技レベルは上がってきています。国内リーグのFリーグも、アジアトップクラスであることは間違いありません。
またFリーグは誕生から17年目のシーズンを迎えておりますが、スポーツ3つの視点「する」「見る」「支える」全ての面で改善できる部分が多く残されていると考えております。
今回のSPORTS INNOVATION STUDIOとのコラボレーションについては「見る」ところに主眼を置いて取り組んでいきたいと思っていますが、「する」についても課題は多いです。Jリーグとは違ってFリーグはフットサル以外に仕事をしている選手も多く、完全プロチームの名古屋オーシャンズの選手以外は、その大半が働きながら二足のわらじでプレーしています。世界のトップに日本が立つためにも、国内リーグでプレーする選手は一人でも多くプロ契約が増えていってほしい。そのためにも「見る」「支える」の部分で、リーグは持続的に価値提供をしていかなければいけません。
現状、Fリーグはリーグ運営で手一杯になってしまっている部分も多く、より多くの価値を提供してファンの皆さまに喜んでいただくために事務局の体制を拡充していく必要がある。加えて、Fリーグの価値向上サイクルを回し、より良い体験を提供していくためには魅力的なフットサルの視聴体験をどう作り出すのかが大きなポイントになってきます。

Fリーグの「見る」には配信映像と現地観戦の2つが存在しているのですが、現状はコンテンツが少ない。選手の皆さんもスタッフの皆さんも一生懸命戦ってくれてはいて、観客の皆さんも応援をしてくださるのですが、Bリーグさんをはじめとしたアリーナスポーツの盛り上がりと比べると、その部分でちょっと物足りなさを感じています。
既存のコンテンツを改善していかなければいけないのかもしれませんし、新たな魅力を作り出していかなければいけませんし、また観戦者向けもただ見に来るだけなのか、何か参加して一緒に楽しめることがないのか、こういったことも作っていかなければいけないかなというふうに思っております。既存のコンテンツの改善、新しい魅力や体験の創出、アリーナで体験できる参加型コンテンツなど、よりフットサルを多くの人に楽しんでいただける工夫が求められています。
今回のオープンイノベーションのプログラムの中では、テクノロジーやアイデアを持っている企業・団体の皆さまとコラボレーションし、フットサルコンテンツの価値向上にチャレンジしたいと考えております。本プログラムをきっかけに、持続的なビジネスモデルを構築して収益化と価値提供のサイクルを回したい。
今回のFリーグの事業共創テーマは「ファンエンゲージメントを通じた収益源の拡大」です。ぜひ皆さまと一緒に、このFリーグを盛り上げていけたらと思っています。

モータースポーツの興奮を、より近くに――
一般社団法人日本自動車連盟JAFの前岡さんは、次のように語った。
前岡:JAFは自動車を安全で快適に利用するためのサービスを提供する自動車ユーザー団体として、自動車業界の尽力により、1963年4月1日に業務を開始しました。会員数は全国2000万名以上で、皆さまのおかげで今年創立60周年を迎えることができました。
JAFといえば思い浮かぶのは、ロードサービスではないでしょうか。全国で年間219万件以上、約14.4秒に1件の救援要請を受け、車両救援にあたっています。対象施設は約4万7000カ所あり、会員証を提示するだけで手軽にご利用いただけます。また、JAFは交通安全活動などにも取り組んでおり、その活動は多岐に渡ります。

そしてJAFは、国内で唯一の四輪モータースポーツ統括団体として、モータースポーツの統括や振興に力を入れています。JAFは国内で唯一の四輪モータースポーツ統括団体として、国際自動車連盟に登録されています。四輪モータースポーツにはさまざまなカテゴリーがあり、世界選手権のF1やスーパーフォーミュラ、スーパーGT、スーパー耐久などが該当します。そして入門カテゴリーとしてはカートも人気があります。
加えて、今注目を集めているのがeスポーツです。先日開催されたオリンピックeスポーツシリーズでは、モータースポーツが種目に採用され盛り上がりを見せています。この他にも、ドリフトやサーキットトライアルヒルクライムなど、さまざまなカテゴリーの競技会が日本で開催されています。
続いて、JAFが直面している課題についてお伝えさせていただきます。F1が日本で開催され、日本人選手が参戦していても他のスポーツほどメディア露出は多くなく、一部ファンの間でしか盛り上がらない現状があります。
モータースポーツの魅力は、実際にサーキットなど競技会場へ来ていただいて一度見てもらえれば、時速300キロにも及ぶ迫力満点の走りと、車の動きとともに風を切るエンジン音にあると考えています。ですが、現状はなかなかレース会場に足を運んでもらえない状況です。
そのような現状から、私たちが今回のコラボレーションで取り組みたいモータースポーツの振興における課題は「裾野を広げたい」「競技の魅力を伝えたい」「サーキットを身近にしたい」、そして「来場者の脱炭素」の4つです。
「来場者の脱炭素」は他のスポーツ団体と比べてもJAFならではの課題だと思うのですが、脱炭素は地球全体の問題でもあり、モータースポーツでも精力的に取り組んでいるところです。国際自動車連盟の調査によると、F1のレースにおけるCO2排出量のうち、レーシングカーのCO2排出量はわずか0.7%で、約7割が来場者の移動と機材輸送に関連するのです。
これら4つの課題の解決に向けて、サーキットなどの競技会場にいなくても、モータースポーツの魅力を感じられるようにすることや、競技会場に来た際の楽しみを増やすこと、来場者が自ら進んでカーボンオフセットできる取り組みを実施することを検討していきたいと考えています。
オープンイノベーションを通じて企業・団体の皆さまとのコラボレーションで取り組みたいアウトプットとしては、モータースポーツの新たな楽しみ方とサーキットの特性を生かした体験の創出や、より身近にモータースポーツを感じて楽しめる体験の場作り。サーキット来場時の新たな購買体験と観戦体験の提供。イベント・レース来場時に、お客さまや関係者に対して環境に配慮した行動を促すことができるサービス、テクノロジーの提供などをイメージしています。
「モータースポーツの興奮をより近く」というテーマで、モータースポーツをともに盛り上げていきましょう!

<了>
■「SPORTS INNOVATION STUDIO オープンイノベーション」
スポーツ領域に限らない、最先端のテクノロジーやサービス・プロダクトと、スポーツ協会/団体が持つ課題やアセットを掛け合わせることで新たなビジネスを創出し、スポーツ産業の拡張を目指すプログラム。(2023年度の共創パートナーは一般社団法人日本フットサルトップリーグ(Fリーグ)と一般社団法人日本自動車連盟(JAF))
応募期間:2023年7月3日(月)~8月31日(木)23:59
▼詳細はこちら
https://sports-innovation-studio.com/
筆者PROFILE
五勝出拳一(ごかつで・けんいち)
広義のスポーツ領域でクリエイティブとプロモーション事業を展開する株式会社SEIKADAIの代表。複数のスポーツチームや競技団体および、スポーツ近接領域の企業の情報発信・ブランディングを支援している。『アスリートと社会を紡ぐ』をミッションとしたNPO法人izm 代表理事も務める。2019年末に『アスリートのためのソーシャルメディア活用術』を出版。
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business -
「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案
2025.06.25Business -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business -
「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案
2025.06.25Business -
移籍金の一部が大学に?「古橋亨梧の移籍金でも足りない」大学サッカー“連帯貢献金”の現実
2025.06.05Business -
Fビレッジで実現するスポーツ・地域・スタートアップの「共創エコシステム」。HFX始動、北海道ボールパークの挑戦
2025.05.07Business -
“プロスポーツクラブ空白県”から始まるファンの熱量を生かす経営。ヴィアティン三重の挑戦
2025.04.25Business -
なぜ東芝ブレイブルーパス東京は、試合を地方で開催するのか? ラグビー王者が興行権を販売する新たな試み
2025.03.12Business -
SVリーグ女子は「プロ」として成功できるのか? 集客・地域活動のプロが見据える多大なる可能性
2025.03.10Business -
川崎フロンターレの“成功”支えた天野春果と恋塚唯。「企業依存脱却」模索するスポーツ界で背負う新たな役割
2025.03.07Business -
Bリーグは「育成組織」と「ドラフト」を両立できるのか? 年俸1800万の新人誕生。新制度の見通しと矛盾
2025.02.28Business