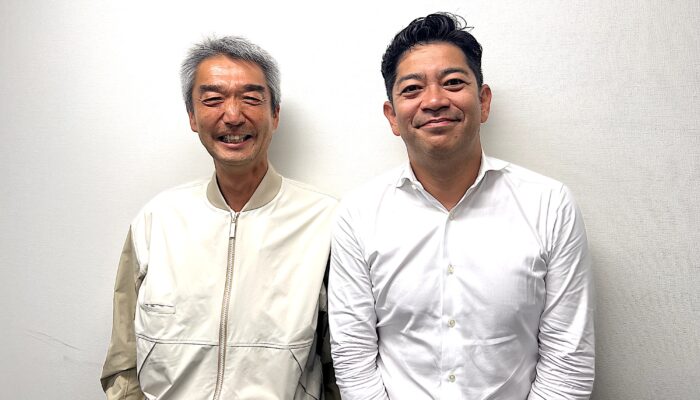なぜ卓球王国・中国は「最後の1点」で強いのか? 「緩急」と「次の引き出し」が日本女子に歓喜の瞬間を呼び込む
アジア大会 中国・杭州。卓球の女子団体戦の決勝戦は、大方の予測通りに日本対中国の争いとなった。第1試合では、日本のエース・早田ひなが登場。世界ランク1位の孫穎莎と激突したが、1-3で敗戦。そのまま、第2、第3試合も制した最強の卓球大国・中国が3―0で優勝を飾った。しかし、これまでとは違い、そこにあったのは「あの中国に本当に勝てるかもしれない」と期待を抱かせる空気感だった――。
(文=本島修司、写真=西村尚己/アフロスポーツ)
中国と対等に戦える選手は早田だけではない
9月26日に行われたアジア大会・卓球女子団体の決勝。
第1試合でエースの早田が接戦の末に孫穎莎に負けはしたが、その後の2試合目と3試合目には、卓球王国・中国を相手に0―3という結果とは別に、手応えを感じる内容が詰まっていた。
2番手の平野美宇と、3番手の張本美和。この二人の堂々とした戦いぶりは、中国と対等に戦えるのは早田だけではないということを印象付けた。
一方で、大会を通じてどの試合にも言えたことは「中国の最後の1点」の強さだ。加えて、どんな場面でも常に発揮される「勝負所での強さ」。 では、その「あと1点の差」は、どこから生まれるのか?
第2試合、完成の域に達しつつある平野の激戦
決勝・第2試合は、平野美宇 対 陳夢。序盤から大方の予想通り、激しい打ち合いが展開された。平野が巻き込みサーブから両ハンドのラリーに持ち込めば、陳夢はその流れをパワーとサイドを切るようなコース取りで押し切ってくる。
しかし、この日の平野は明らかに調子がいい。お互いが1ゲームずつを取り合いって1-1となった、3セット目。9-5とリードを奪うと、ここで両ハンドの連打はさらに勢いを増した。11-6でこのゲームを取り切る。
4ゲーム目。“試合内容が動いた”のは、ここだ。陳夢が、サーブに変化をつけてきた。1-1からは強烈な下回転サーブで、平野のレシーブミスを誘う。その後もバック対バックの打ち合いで1-3と陳夢がリードを広げていく。やはり、バックミートを真正面から打ち合うと、中国のパワーの前に捻じ伏せられるようなシーンが増えていく。
しかし、2-3から、3-3へ追いついた場面では、平野が観衆の度肝を抜いた。フォアとバックの壮絶な切り返しラリー。まさにパワーとピッチの速さ比べで、中国のオハコといえる展開だ。そこを、切り返しの連打で耐え切り、陳夢のバッククロスを打ち抜いた。陳夢は、反応しきれずに、左手を出すほどに強烈だった。
4-6。今度はここで、緩急をつけて、ユルめにミドルを突いた。陳夢の体勢が崩れた。ユルいボールだ。それも、体の前にボールがあるのに、あの中国のトップ選手が反応できなかった。これもまた、驚くような光景だが、最近の平野はこのボールをよく使う。平野の緩急をつけたボールは「いつ来るかわからない」「意表を突いたもの」に仕上がってきている。 7-8からは、速いラリー。陳夢が先に崩れた。いつユルいボールが来るか。そこに意識がいっているように見える。8-8。ここからもう一回、バックミートの打ち合いが始まる展開が続き、コースをフォアに替えるタイミングもうまく使った陳夢が、このゲームを制した。
それでも平野を上回った中国・陳夢の圧巻の精度
ゲームカウントは、2-2。ファイナルゲームへともつれ込んだ。
2-1と平野リードから開始。ラリーの打ち合いでも負けない平野姿には、頼もしさすら感じる。バックミートをストレートに放ち、それがライン上のギリギリを通過していく。エッジインでポイント。運も平野に味方した。
3-2からは、陳夢が大きくフォアドライブをフォアクロスに打ち込む、平野を大きく動かしてポイント。忘れた頃にこういうコースが来る。このあたりの戦術が豊富だ。
4-5で、日本がタイムアウト。ここから再び“ユルて高さのある”バックループドライブで、陳夢を崩していく。
しかし、陳夢もまた、後半になるにつれてどんどん精度が上がっていく。バックフリックからのバックミートにミスが出なくなる。その上で、速いバックドライブも飛んでくる。5―7からはそのボールが決定打に。
5-8。ここからは縦横無尽に陳夢が飛び回る姿は圧巻だった。最終的には、11-5で陳夢が勝利。最後は平野が完敗の形だったが、「最後のひと押し」と、もっというなら「あと一点」という試合だった。
ただ、かつて水谷隼氏が選手時代に語っていたこういう言葉がある。
「中国の選手とは、すでに競り合うところまではいける。そこからの最後の1点を取れるかどうかが問題」 この、詰め切るための少しの、それでいて決定的な“差”。それが見つかった時、日本の女子卓球は世界の頂を手にするはずだ。
そして始まった、第3試合。「張本美和」の名が世界に響く
第3試合は、張本美和 対 王曼昱。世界での経験値が浅い15歳の張本。対するは、世界ランキング3位の王だ。
試合は5―3と張本のリードで始まった。巻き込みサーブから低いツッツキ。その後は強烈なフォアドライブを淡々と打ち込み、軽打で緩急をつけながら、決定打のフォアドライブをもう一度放つ。まさに「大人の卓球」だ。どちらが格上かわからないほどの立ち上がりを見せる。
バックミートの連打で、張本が9-5としてポイントを重ねていく。世界3位のボールに、軽々と反応できてしまっている。切り返しの打ち合いで、10-6。バックドライブで打ち抜き、1ゲーム目を圧勝で決めた。
2ゲーム目。王曼昱も、ここから本領を発揮。今度は王が1-3とリードから開始。激しい打ち合いの攻防が続く。3-7からは、回り込もうとした張本がボールに食い込まれるような体勢に。回り込みの動き。ボール自体の速度。王は全てが速い。このゲームは4-11で王が取り切った。
3ゲーム目。張本は打開策を投じる。YGサーブだ。それも、サイドを切るような、鋭さのあるYGサーブだ。次はYGをフォア前へ。同じフォームで、コースに変化をつける。できることはすべて試していく。そのすべてが、今後の張本美和の大きな財産になっていくはずだ。 5-8。ここで、巻き込みの長いサーブに戻す。これをバックへグッと食い込ませる。「ナイスサーブ」と見えるが、王は何事もなかったように返球してしまう。食らいつく、張本。突き放す、王。一進一退の攻防は、7-9から張本にサーブミスが出て、7-11で王が制した。
追い詰められると余計に強い、それが中国の強さ
ゲームカウント、1-2となっての4ゲーム目。大きなラリーとなった打ち合いを張本が制すと、観衆から大歓声が上がる。リーチを生かしたダイナミックな卓球をしても、年上の格上選手に引けを取らない。
3-2からも、同じようなラリーの展開に。ここも張本が制す。やや下がって、男子のような大きなラリーの打ち合いになると、むしろ張本美和のほうに点数が入る。9-6で、再びYGサーブからのフォア強打一発。10-6と追い詰めた。しかし、やはり問題はここからなのだ。
ここで、王はフォア前のサーブで「展開を作る」ような卓球で2本を連取。このあたり、「やることが決まっている」感じがする。
10-8。張本は、また得意のYGサーブ。しかし対応される。10-9。もう一回YGサーブ。そこから強打で打ち合いに持ち込むがカウンター気味に打たれる。テレビ中継の実況者からも「あと1点なんですけど」というフレーズが飛び出す。
しかし、ジュースになると王はさらに勝負強くなる。10-11。王は、張本のフォア前に短いサーブ。そして張本を前に動かしてからのバックミートの連打が決まる。追いつく際に使ったパターンだ。11-12。張本の選択は、やはりここでも「この試合で一番“効いた”YGサーブ」からの速攻を仕掛けた。だが、王は「それを待っていた」かのようにレシーブから押し切り、この試合を制した。
王は、下半身の切り返しのスピードも、2ゲーム目以降から増していった。そこから、多くの「次の一手」が生み出されていた。
「接戦の先のもう1点」の取り方とは?
こうして日本対中国の戦いは、3-0で中国が勝利して優勝を飾った。
3-0という結果だけ見れば、やはり何度やっても超えられない厚い壁だ。しかし、中身は違う。
かつて、対中国選手戦では0-3の試合が多かった時代を超えて、早田ひなは2-3、平野美宇も2-3、張本美和も1-3という内容だった。どのゲームも、「もう一歩決定力があれば」という試合だ。
日本の女子と、中国の女子の間にある「最後の一点の差」は何か。この決勝戦を振り返ると、日本の女子は「これをやって負ければ悔いがないといえるプレー」が多かったように見える。そして、その試合で「ここまで接戦に持ち込めた要因のサーブ」を出していた。
もちろん正しい選択でり、当然の戦術だろう。しかし、中国の選手は常に「それ」を上回ってくる。時に、得意パターンを読み切り、待っているかのようにも見える。
平野が、特に対中国の試合で見つけつつある、中国選手の予想すら上回る「緩急を使ったユルいボール」のような、驚くような手が、もう一つ、二つあれば……。決定打となる引き出し。この試合でまだ見せていないビッグプレー。実力の差は、この点だけだと感じる。
数年前までは、「中国から1ゲームでも取れば卓球人生の歴史になる」といった雰囲気があった。それが今では、1ゲームを取るのは当たり前というところまできている。
大会後のインタビューで、早田は「何か一つカギが見つかればいいな」と言った。その言葉は、この壮絶で素晴らしい決勝戦のすべてを物語っているようだ。
実力が少しずつ互角に近くなってきた、今。決定打となる引き出しを増やし、勝ち切ること。残る課題はここだろう。
そして、負けた中にも何か手応えを感じられたような笑顔が見られた試合後の光景からは、その歓喜の瞬間が、もう、すぐ近くまできているような気がしてならない。
<了>
早田ひなが織りなす、究極の女子卓球。生み出された「リーチの長さと角度」という完璧な形
新生・平野美宇の破壊力が中国卓球を飲み込む? 盟友に競り勝った国内大会優勝が示した“伏線”
遂に「張本・張本」ペアも登場! なぜ卓球は兄弟や姉妹が“揃って強い”のか?
女子卓球界のエース・伊藤美誠を封じた高校生のバックドライブ。日本中が待つ、エースの完全復活
なぜ北海道から卓球女子日本代表が生まれたのか? “異色の経歴”佐藤瞳を生んだ指導者・佐藤裕の挑戦
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business -
「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案
2025.06.25Business -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion -
スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験
2025.06.19Education -
なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意
2025.06.17Education -
「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地
2025.06.16Career
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion -
日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」
2025.06.16Opinion -
野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」
2025.06.06Opinion -
冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは
2025.06.06Opinion -
なでしこジャパン2戦2敗の「前進」。南米王者との連敗で見えた“変革の現在地”
2025.06.05Opinion -
ラグビー・リーグワン2連覇はいかにして成し遂げられたのか? 東芝ブレイブルーパス東京、戴冠の裏にある成長の物語
2025.06.05Opinion -
SVリーグ初年度は成功だった? 「対戦数不均衡」などに疑問の声があがるも、満員の会場に感じる大きな変化
2025.06.02Opinion -
「打倒中国」が開花した世界卓球。なぜ戸上隼輔は世界戦で力を発揮できるようになったのか?
2025.06.02Opinion -
最強中国ペアから大金星! 混合ダブルスでメダル確定の吉村真晴・大藤沙月ペア。ベテランが示した卓球の魅力と奥深さ
2025.05.23Opinion -
当時のPL学園野球部はケンカの強いヤツがキャプテン!? 宮本慎也、廣瀬俊朗が語るチームリーダー論
2025.05.23Opinion