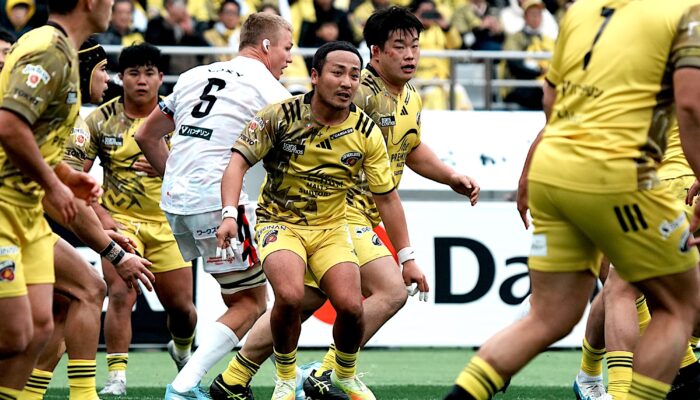「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
ユース世代を経てプロの舞台へ──。誰もがその先にA代表やビッグクラブでの活躍を夢見るが、現実は厳しい。6月にスロバキアで行われたUEFA U-21欧州選手権では、将来を嘱望される多くのU-23年代の若手が集結した。だが、その中で真に“伸びる選手”と“伸び悩む選手”の差はどこにあるのか。成長に必要な「環境」と「条件」。ドイツを中心とした欧州の育成現場を例に、「仕上げの育成」期に潜む課題とヒントを探る。
(文=中野吉之伴、写真=ロイター/アフロ)
U-21欧州選手権での活躍が、A代表につながるのか?
スロバキアで6月に開催されたUEFA U-21欧州選手権ではイングランドU-23が決勝でドイツU-23を下し、2年に1度行われる本大会で2連覇を飾った。
なおU-21欧州選手権は予選開始時の年齢条件でつけられた名称であり、本大会開催時でU-23年代ということになる。
2009年、同大会で優勝したドイツではマヌエル・ノイアー、ジェローム・ボアテング、マッツ・フンメルス、ベネディクト・ヘーヴェデス、メスト・エジル、サミ・ケディラといった、のちにA代表で主力となる選手が躍動。彼らを中心にしたチーム作りがうまくいき、それが2014年FIFAワールドカップの奪還につながった。
では現代においてU-21欧州選手権で活躍することが、A代表の補強にどこまでつながるのだろう?
ドイツでの話をすると、前述したように2009年優勝組の多くがA代表の主軸へと成長した。ここ最近でいうとニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、フロリアン・ヴィルツらは、それぞれU-23で経験を積み、所属クラブで活躍し、A代表で主力へと成長している。
ただそれ以上に伸び悩んでいる選手が非常に多いのも事実だ。
2017年優勝組だと、ルカ・ヴァルトシュミットが、大会最多得点記録となる7点を挙げて得点王に。輝かしい未来が待っていると誰もが期待を寄せていた。当時所属クラブのフライブルクで活躍し、ヴォルフスブルクへとステップアップ移籍を果たしたが、そこからは停滞が続き、昨季は2部リーグのケルンでのプレーを余儀なくされていた。
ドイツだけではなく、他国でも伸び悩みは大きな問題となっている。2021年大会MVPはポルトガルのファビオ・ビエイラ。ポルトで主力選手に成長し、2022年夏にアーセナルへと3500万ユーロで移籍。ただそこから2シーズン在籍でスタメンに定着することはできず、2024年夏にポルトへ復帰となっている。
U-23代表の価値とは? そこで躍動する選手の評価は?
今大会で躍動した選手がみな、確かな資質を感じさせていたのは間違いない。
市場価値1000万ユーロ以上の選手が85人もおり、すでに欧州で確固たる価値を示している選手も少なくない。それでも、ある選手はそこからさらにステップアップを果たし、ある選手は壁を乗り越えられずに失速し続けてしまう。その差はどこで生まれ、そしてどこに本質的な問題があるのだろうか?
ドイツU-23代表監督アントニオ・ディサルボに以前インタビューをしたことがある。今大会では惜しくも準優勝となったドイツU-23は、2017年と2021年大会でそれぞれ優勝、2019年大会でも準優勝を手にしたものの、当時各国1部や2部でレギュラーとして定期的にプレー機会を得ている19〜22歳の選手が非常に少ない、という点を危機感とともに指摘していたのを思い出す。
「僕がU-23代表でコーチを始めたとき、ブンデスリーガを視察して回ると、本当にたくさんの素晴らしい選手がプレーしていたんだ。短い出場時間ではなく、チーム内でしっかりとポジションを獲得していた。CL(UEFAチャンピオンズリーグ)でプレーする選手だって多かった。
ただここ最近は、ブンデスリーガでプレーするU-23選手がかなり少ないし、ブンデスリーガ2部でもまだポジション争い真っ只中という立ち位置の選手のほうが多い。ドイツの若手選手が、クラブから信頼を受けてプレー機会をもらえるようになるというのも大事だし、選手も普段から自分に矢印を向けて努力を重ね、チャンスに自分のクオリティを発揮して、ポジションを確保できるようにできなければならない」
国際市場の活発化が進む中、自クラブや自国選手を我慢強く育成するよりも、安価でより資質を感じさせる国外の選手を補強し、プレー機会を与え、市場価値を高めてからまた市場に介入するというほうが、費用対効果という面では効率がいいという考えが、一時期強くなりすぎた傾向は間違いなくある。
実際、U-23代表世代でもA代表レベルの選手は20歳前後で頭角を現している。前述したドイツのヴィルツやジャマル・ムシアラ、カイ・ハバーツもそうだし、スペインで絶対的な存在となりつつあるラミン・ヤマルやニコ・ウィリアムズといった選手はみな、10代からA代表を居場所としている。そうなるとU-23代表は、その次に属するカテゴリーという見方がどうしても強くなる。今大会のドイツU-23代表にしても、FIFAクラブワールドカップと同時期開催だったために、バイエルン、ドルトムント勢はアメリカでの大会に参加。他国のU-23代表も同様の問題を抱えていた。
今大会のドイツU-23代表を見られた特徴
欧州においても、10代でA代表へ定着できるほどの資質を持った選手が常に待ち望まれているのは間違いないし、実際にそうした選手もたくさんいる。ただ、それができないがために、19〜22歳の段階で見切りをつけられるようになるのはよろしくない。前述のディサルボはこのように語る。
「誰もがみんな同じような成長曲線を進んでいけるわけではない。成長スピードには個人差があるし、飛躍を果たすにはきっかけだって必要だ。遅咲きの選手だってたくさんいる。そして遅咲きの選手にしても、自分に合った環境で着実に試合出場機会を積み重ねていくから、ある日花咲く日を迎えることができるわけだ」
19〜22歳年代の出場機会確保と適切な環境の整理に関しては、ドイツ国内でも常々ディスカッションが行われている。ただ、代表の利害とクラブの利害がバランスよく噛み合わなければ、明確な解決策は見出されない。
今大会のドイツU-23代表を見ると、すでにA代表デビューを飾っているニック・ヴォルテマーデ(シュツットガルト)だけではなく、ブラヤン・グルダ(ブライトン)とロッコ・ライツ(ボルシアMG)の2人もA代表の練習に参加し、ユリアン・ナーゲルスマン監督からも高く評価されている。加えて今大会メンバーではフランクフルト、フライブルク、マインツ組が多いのが特徴的だった。
フランクフルト:ナサニエル・ブラウン、ナムディ・コリンズ、エリアス・バウム、アンスガー・クナウフ
フライブルク:ノア・アトゥボル、マックス・ローゼンフェルダー、メルリン・レール
マインツ:パウル・ネーベル、ネルソン・ヴァイパー
彼らはCL、EL(UEFAヨーロッパリーグ)出場権争いをしているクラブで確かな戦力として活躍しているし、ブライトンのグルダも前所属はマインツだ。
ユース後の「仕上げの育成」時期の最大の問題点
代表に多く選手を派遣するクラブに関して、ナーゲルスマンが興味深いコメントをしていた。A代表でシュツットガルトの選手が多い点についての質問が出たときに、こんな風に話している。
「なぜシュツットガルトの選手が多いのか。それはシュツットガルトで多くのドイツ人選手がプレーしているからだ。例えば11人のドイツ人がピッチに立っていたら、そこから代表に入ってくる選手のパーセンテージだっておのずと高くなる。セバスティアン・ヘーネス監督は、彼らの資質を正しく見極めて、成長に導き、素晴らしい仕事をしてくれている」
フランクフルト、フライブルクやマインツも同様だ。それぞれはクラブとして、明確なビジョンとコンセプトが整理されている。自前の育成選手を大事にし、セカンドチームを有効活用して出場機会を確保し、トップチームでも積極的に起用することで、選手の成長を促している。他国の資質ある選手を安価で獲得するのとは別に、クラブへのアイデンティティを大切にし、所属選手のパーソナリティやメンタリティが合うかを重視する傾向が強まっている。
ここは本当に大事なポイントだ。FIFA U-17ワールドカップで優勝したドイツU-17代表のクリスティアン・ビュック監督がとても貴重なコメントを残している。
「U-19までの育成時代を終えた次のステップとして、選手はそれぞれクラブでプロデビューを飾り、ポジションをつかんでいくことが求められる。同時に所属クラブには、彼らにどんな道があるのかを示し、出場機会を与えなければならない。それも可能な限りトップレベルの環境を、だ。
これこそがドイツサッカー界における最大の問題の一つ。将来有望なタレントは十分なだけいる。だが、ユース後の『仕上げの育成』時期に適切なレベルで、適切な出場機会がない。
大切なのは選手を信頼すること。出場機会を与えることを怖がってはいけないのだ」
選手キャリアの成功ルートは一つではないし、決まりきった道をたどることが最善とも限らない。選手それぞれに合ったさまざまな登頂ルートがある。各国でU-19からU-23、トップチームへどのように選手が成長してきているかを探ることには、とても大きな学びがある。
そして日本は日本で、どのように選手が成長できるか、若手選手の成長にどんな取り組みがクラブとして必要かを考えることが大切なのだろう。
【連載前編】なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
<了>
「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果
ユルゲン・クロップが警鐘鳴らす「育成環境の変化」。今の時代の子供達に足りない“理想のサッカー環境”とは
なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは
海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」
2026.02.26Education -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」
2026.02.20Career -
「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念
2026.02.20Career -
ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断
2026.02.20Career -
名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持
2026.02.13Career -
WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏
2026.02.13Business -
新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」
2026.02.12Business -
「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断
2026.02.12Career -
女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割
2026.02.10Career -
なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性
2026.02.10Business
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方
2026.02.09Training -
スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体
2026.01.05Training -
「木の影から見守る」距離感がちょうどいい。名良橋晃と澤村公康が語る、親のスタンスと“我慢の指導法”
2025.12.24Training -
「伸びる選手」と「伸び悩む選手」の違いとは? 名良橋晃×澤村公康、専門家が語る『代表まで行く選手』の共通点
2025.12.24Training -
サッカー選手が19〜21歳で身につけるべき能力とは? “人材の宝庫”英国で活躍する日本人アナリストの考察
2025.12.10Training -
なぜプレミアリーグは優秀な若手選手が育つ? エバートン分析官が語る、個別育成プラン「IDP」の本質
2025.12.10Training -
107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学
2025.11.17Training -
「やりたいサッカー」だけでは勝てない。ペップ、ビエルサ、コルベラン…欧州4カ国で学んだ白石尚久の指導哲学
2025.10.17Training -
何事も「やらせすぎ」は才能を潰す。ドイツ地域クラブが実践する“子供が主役”のサッカー育成
2025.10.16Training -
“伝える”から“引き出す”へ。女子バスケ界の牽引者・宮澤夕貴が実践する「コーチング型リーダーシップ」
2025.09.05Training -
若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり
2025.08.22Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training