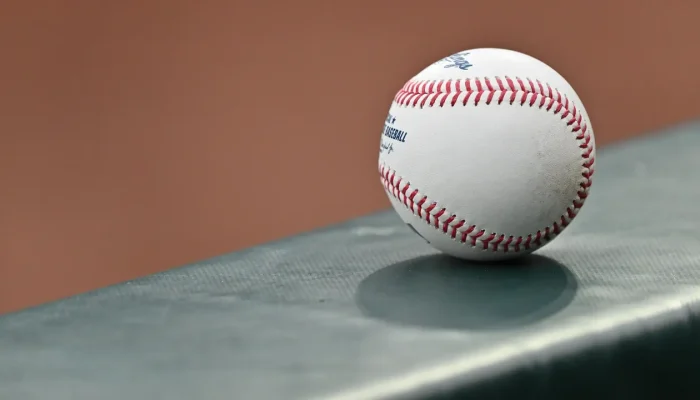スポーツは「見る」“だけ”でも健康になる? 東京五輪前に知りたい脳と身体への影響
スポーツ庁が実施した「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(平成30年度)によると、成人の週1回以上のスポーツ実施率は55.1%となっており、「スポーツ基本計画」ではこれを早期に65%程度にまで引き上げることを目標に掲げている。
その背景に、高齢社会に伴い膨張し続ける医療費がある。2017年度には過去最高の42.2兆円となり、30年前と比較して2倍以上にもなった。スポーツによって健康増進、健康寿命の延伸を図ることで、医療費を削減することを狙いの一つとしている。
だが、スポーツは「する」だけではなく、「見る」だけでもその健康効果を得られることをご存じだろうか? 東京オリンピック・パラリンピックを来年に控える今、あらためてスポーツを「見る」ことの効能を考えたい。
(文=谷口輝世子、写真=Getty Images)
テストステロン値の上昇と「ウィナーズ・エフェクト」は見る人にも
スポーツ中継で「手に汗握る」という言葉を聞くことがある。どちらが勝つか分からない大接戦に興奮している様子を表しているが、「手に汗握る」というのは単なる比喩表現ではない。見ているだけの観客も、試合の興奮や緊張で、汗ばんでいることがある。実際にプレーしている選手ほどではないにしても、試合中に血圧や心拍数、ホルモン値などが変化している。見ているだけの人間も、あたかも自分がやっているかのように感じて、身体も反応しているのだ。
米シラキュース大学のアラン・メーザー教授によると、テニスや柔道で勝利した選手は、試合後に男性ホルモンの一種であるテストステロン値が高まるという。(1)
男性ホルモンのテストステロンは、競争をするときに上昇し、勝者はテストステロンの上昇が維持される。このテストステロンの上昇の維持によって、勝者はさらに積極的な行動を起こすことができる。これは「ウィナーズ・エフェクト(勝者効果)」と呼ばれるものだ。
このウィナーズ・エフェクトは、スポーツを「する人」だけでなく、「見る人」にも当てはまる。1994年のFIFAワールドカップ決勝で、試合を観戦した人のホルモン値の変化を調べた研究がある。この大会の決勝はブラジル対イタリア。0−0のまま決着がつかず、PK戦で勝負が決まった試合だ。ファンにとっては、これ以上ないくらい、ハラハラ、ドキドキする展開だったといっていいだろう。米ユタ大学のポール・バーンハード教授のグループが、米国内でブラジルファンが集まったレストランと、イタリアのファンが集まったピザのレストランで、それぞれテレビで試合を観戦していたファン(両サイド合わせて計21人)の男性の唾液を採取し、テストステロン値を調べた。優勝したブラジルを応援していたファンのテストステロン値は高いままだったが、負けたイタリアを応援していたファンのテストステロン値はやや低くなっていたという。(2)
面白いことに、このような現象が見られるのは、人間だけではない。他の魚の争いを見ているだけの「観戦魚」のホルモン値も変動するそうだ。攻撃性のある淡水魚のシチリッド種を水槽の中で戦わせ、その戦いをマジックミラーのように一方からしか見えないガラス越しに同種の他の魚に見物させるという実験では、「観戦魚」の尿中のテストステロン値が上昇したと認められた。(3)
脳内のミラーニューロンも「見る」だけで反応している
頭の中でも、自分が実際にやっているかのように反応している。脳のミラーニューロンと呼ばれる神経細胞群が、他人の行動を自分の脳の中で鏡のように映し、あたかも自分がやっているかのように反応しているのだ。
ミラーニューロン研究の第一人者であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のマルコ・イアコボーニ教授は、著書『ミラーニューロンの発見』(早川書房)の冒頭で、ミラーニューロンの象徴的な働きとしてスポーツ観戦を取り上げている。
「選手がプレーしているのを見ることも、自分がプレーしていることと同じになる。選手が捕球するところを見たときに発火するニューロンのいくつかは、自分が実際に捕球するときにも発火する。だから見ているだけで、同時にプレーしているような気になれる」
他人の動きを見ているだけなのに、脳では、実際にその動きをするのに必要な部位が反応している。自分でも経験のある動きを見たときの方が、ミラーニューロンはより発火するといわれている。また、誰の動きを見ても同じように反応するのではなく、ファンである選手、応援している選手の動きを見ているときに、より強く反応するようだ。
他人の動きを見ることは、見る人の身体にも影響を及ぼす。この働きを利用することで、「他の人のパフォーマンスを見ることで、健康に役立てることができるのではないか」という研究もなされている。バーチャルエクササイズは、実際に運動したのと同じような効果を得られるかという実験だ。研究したのは、西シドニー大学のグループ。ジョギングの映像を見たときには、心拍数、血流量、呼吸数がやや増えた。実際に運動したのと同じわけではないだろうが、見ているだけでも、自分が運動しているかのように身体が反応したのだろう。(4)
特定のチームを応援するファンには身体的にも心理的にもメリットがある
最近では、英国リーズ大学のアンドレア・ウトリー教授が、サッカー観戦は健康に良い可能性があるという研究結果を得たそうだ。米CNNなどの報道によると、ブックメーカーの「ベットビクター」との共同研究で、応援しているチームの勝利を見ることは、90分間、早足で歩くのと同程度の身体的負荷がかかり、勝利を見届けた場合は24時間にわたり高揚感が続くという。
応援していたチームの勝利を見た後で高揚感が得られるのは、身体だけでなく、気持ちの面でも「あたかも自分が勝ったかのように」感じているからだろう。
「Basking in reflected glory(栄光浴)」という言葉がある。社会的に評価の高い人物や団体と自己との関係性を強調することで,自らの評価も高めようとするという意味だ。有名人やスター選手と知り合いであると自慢したくなるのも栄光浴だ。応援しているチームが勝利し高い評価を得ることで、応援しているファンも評価されている気分になるのではないか
それに、特定のチームを応援することは孤独感もまぎらわしてくれるようだ。スポーツファンの心理を研究するダニエル・ワンは、スポーツファンのグループに参加することのメリットについて調査を行っている。
米国ケンタッキー州立大学に通う155人の学生を対象に、地元スポーツチームのファンであるか、ファンのグループにどの程度の結びつきを感じているかを質問した。この質問と同時に、自己肯定感と人生への満足度を、最低から最高まで数字によって答えてもらった。
「チームを自分自身の延長だと強く感じている学生」は、個人的にも社会的にも自尊心が高く、健全で前向きな感情の度合いも強かった。全体的に孤立や怒りを感じることも少なく、孤独や落ち込みや疲労といった感情もあまり見られなかった。スポーツへの興味そのものがもたらす効果ではなく、チームや選手との心理的結びつきや、自分と同じチームを応援するファンとのつながりによるものが大きいという。仲間を得られるという意識や、ファンの一員であるという帰属感を得られるからだろう。ワンはこの効果を「チーム同一化 社会心理学的健康モデル」と呼んでいる。(5)
ただし、熱狂的な応援することは、一部の人にとっては健康リスクになるかもしれない、ともいわれている。2006年のFIFAワールドカップ開催期間中のミュンヘンで、ドイツ代表の試合があった日に循環器の急な不調で救急病棟を訪れた患者数の変化を調べた資料がある。この調査によると、ドイツ代表の試合があった日は、そうでない日に比べて、循環器の患者数が2.66倍にも上ったという。試合開始から2時間が、最も発生数が多かったようだ。この調査を行った研究者はもともと心疾患を抱えており、熱狂的に応援をする人は観戦によるストレスが身体不調の引き金になるのではないかとしている。
東京オリンピック・パラリンピックでも、アスリートによる素晴らしいパフォーマンスが繰り広げられるだろう。それは、見ているだけの我々にもウィナーズ・エフェクトや心地良い高揚感を与えて、心身の不調を吹き飛ばしてくれるはずだ。見ているだけでも疲れそうな暑さが、これらの効能を溶かしてしまわなければよいのだが。
<参照元>
(1) The Secret Lives of Sports Fans (Eric Simons, The Overlook Press)
(2)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9811365
(3)https://psycnet.apa.org/record/2001-16544-001
(4)https://www.westernsydney.edu.au/newscentre/news_centre/story_archive/2013/couch_potatoes_take_heart_-_watching_sport_can_make_you_fitter
(5)『ファンダム・レボリューション』(ゾーイ ・フラード=ブラナー、アーロン M・グレイザー著、関美和 翻訳/早川書房)
<了>
渋野日向子の“笑顔”を奪うな! 繰り返される無責任なフィーバーへの危惧
理系のお父さん・お母さんのためのかけっこ講座 “理系脳”でグングン足が速くなる3つのコツ
武井壮が語った、スポーツの未来 「全てのアスリートがプロになるべき時代」
J1で最も成功しているのはどのクラブ? 26項目から算出した格付けランキング!
ダルビッシュ有が考える、日本野球界の問題「時代遅れの人たちを一掃してからじゃないと、絶対に変わらない」
この記事をシェア
KEYWORD
#COLUMNRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯
2026.01.30Career -
ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件
2026.01.23Career -
ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地
2026.01.23Career -
世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断
2026.01.23Career -
女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道
2026.01.20Career -
丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化
2026.01.19Career -
伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”
2026.01.16Career -
史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北
2026.01.16Career -
狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生
2026.01.16Career -
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体
2026.01.05Training -
「木の影から見守る」距離感がちょうどいい。名良橋晃と澤村公康が語る、親のスタンスと“我慢の指導法”
2025.12.24Training -
「伸びる選手」と「伸び悩む選手」の違いとは? 名良橋晃×澤村公康、専門家が語る『代表まで行く選手』の共通点
2025.12.24Training -
サッカー選手が19〜21歳で身につけるべき能力とは? “人材の宝庫”英国で活躍する日本人アナリストの考察
2025.12.10Training -
なぜプレミアリーグは優秀な若手選手が育つ? エバートン分析官が語る、個別育成プラン「IDP」の本質
2025.12.10Training -
107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学
2025.11.17Training -
「やりたいサッカー」だけでは勝てない。ペップ、ビエルサ、コルベラン…欧州4カ国で学んだ白石尚久の指導哲学
2025.10.17Training -
何事も「やらせすぎ」は才能を潰す。ドイツ地域クラブが実践する“子供が主役”のサッカー育成
2025.10.16Training -
“伝える”から“引き出す”へ。女子バスケ界の牽引者・宮澤夕貴が実践する「コーチング型リーダーシップ」
2025.09.05Training -
若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり
2025.08.22Training -
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training