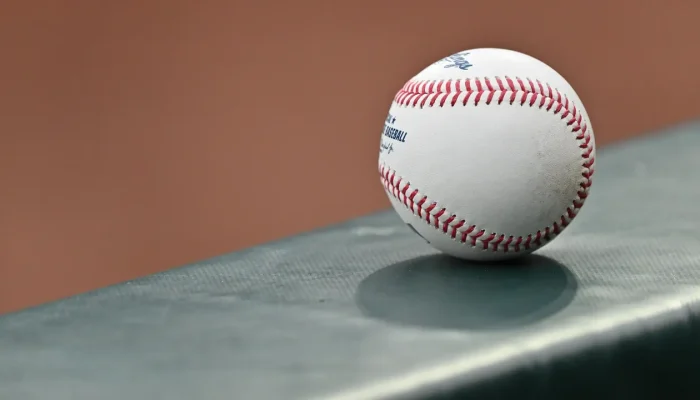子供のスポーツに月謝2万6000円は高い? 日本の育成の常識を打ち破るFC市川ガナーズの挑戦 ~高校野球の未来を創る変革者~
美しく整備された国際規格の広いピッチの上で、小学生から高校生までのサッカー少年少女が思う存分に駆け回る。専用グラウンドに加え、ナイター設備、シャワー、おしゃれなクラブハウス。FC市川ガナーズは、民間のサッカースクールとは思えぬ充実した施設を有している。
だがここはもともと、草木が生い茂る何もない土地だったという。これだけの施設をゼロから造り上げるには、莫大(ばくだい)な資金がかかるはずだ。民間のいちサッカースクールになぜこんなことが可能だったのだろうか――?
本連載「高校野球の未来を創る変革者」では、高校野球界の変革に挑む人たちを紹介してきたが、今回はあえてサッカー界で育成年代の改革に取り組む男を取り上げたい。サッカー界、ひいてはスポーツ界の常識を打ち破ろうと尽力する幸野健一氏が実践する、あるべき育成年代のチームの姿とその経営哲学は、必ずや野球界にとっても学びのあるものになるだろう。
(取材・文・撮影=氏原英明)
地域の小さな民間クラブとは思えぬ充実した施設造りを実現させた“手法”
サッカーと野球――。
2大プロスポーツを形成しながら、真逆の方向性に向かっている両競技は交わることがあまり多くない。日本国内重視、親会社が主体となってチームを支えるのが野球で、サッカーは常に世界との距離を測りながら、その立ち位置を少しでも上げようと努力してきた。地域に根を張ったクラブとして独立しているといえる。
千葉県市川市にあるFC市川ガナーズは地域の民間クラブとは思えないほどの城を構えていて、サッカー場のフルコートを造り上げ、クラブハウスも有している。もともとは草木が生い茂る何もない土地に北市川フットボールフィールドを建設し、さらにはテニスコートも完備するなど人口約50万人の市川市はスポーツのにぎわいを見せている。
海外のようなクラブづくりを現実にしてみせたのが、FC市川ガナーズの代表・幸野健一氏である。
「ヨーロッパではどんな小さなクラブでも、クラブハウスとグラウンドを持っている。それがクラブの定義です。日本では関東リーグ(実質5・6部相当)のチームでさえ、借り物のグラウンドであることが多い。では、そのチームにとっての名残やクラブの雰囲気、文化はどこにできていくのか。僕はこれまでもサッカー界のことを考えて行動・発信してきた。でも、なかなか思うように伝わってこなかった。自分の理想を追求するには、自分のクラブをつくって、グラウンドを造ってやりたいと思っていたところにそのチャンスが巡ってきた。自分の理想を追求することができるチャンスが巡ってきたんで、それにチャレンジした。当時はアーセナルサッカースクール市川からスタートして、日本がこうなったらいいなと思う理想のクラブにしようと立ち上げました」
PFIを活用すれば、四者みんなに利益があり幸せになれる
とはいえ、疑問として残るのが、なぜ、千葉県の市川市の北部、梨の名産地とされるこの地区にサッカーグラウンドとクラブハウスの建設がかなったのだろうか。その背景には、1992年イギリス・サッチャー政権の時に生み出されたPFIという手法を持ち込んだことにある。
Private Finance Initiative(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)の略称であるPFIとは、内閣府のHPによれば「公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して行う新しい手法」とある。民間の資金や経営・技術的能力を活用することによって、国や地方公共団体の施設を効率的かつ効果的に使用して、サービスを提供するというもの。
いわば、行政は資金はもちろん、経営に関して一切手をかけずに民間に経営などを任せ、市民にサービスを提供できるというものである。
幸野氏は言う。
「PFIはみんなに利益をもたらすシステムといえます。市川市はここにあった空き地を、市民に対してスポーツという形で提供することになるわけだし、固定資産税を払っていた土地を貸し出すことで、われわれのクラブから賃借料が入る。僕らはファンドで集めた資金でグラウンドを建設し、民間会社として利益を出していくと。サッカークラブがあることで子どもたちも喜ぶわけですから、四者がみんな幸せになる。どこかに負担がかかることなく、みんなに利益があるんです」
PFIでなければいけない理由は、経済的な理由が一因としてある。通常、自前で土地を購入してサッカーグラウンドを造ることになるわけだが、その場合、初期費用に莫大な資金がかかってしまう上に、サッカーグラウンドの場合はサッカー以外の稼ぎ方に使用することが難しいこともあって、ペイすることができなくなる。だがPFIを活用すれば、少なくとも自前で土地を購入する必要がなくなって初期費用を抑えられるようになり、その分の資金を他に回して質の良いサービスを提供できるようにもなる。
チーム全員を試合に出すことと、勝つこと。相反する両面を追求する
とはいえ、1億〜1億5000万円の回収は必要である。ただ、そこは幸野氏の経営手腕がものをいう。
「永続性が大事。そのためにはみんなが気持ちよくやれる仕組み、ソフトの部分が大事になってくるわけです。ボランティアのお父さんコーチを連れてきて月謝3000円の少年団では(永続的なクラブ運営は)無理なんです。ある程度お金を取れるほどのものをつくらないといけない」
その中で最初は、130年の歴史を誇るイングランドの名門アーセナルとの業務提携を結んだ。データをもとにした育成メソッドを軸に「アーセナルサッカースクール市川」として2014年にスタートした。
2019年にアーセナル本部でサッカースクール事業の全世界的な育成方針の変更が行われ、世界約20カ国のスクールを閉校することになりFC市川ガナーズと名称変更しているが、元スペイン代表のリカルド・ロペスをクラブアドバイザーに招聘(しょうへい)してソフト面の充実は年を追うごとに増している。
中でも、FC市川ガナーズの大きな柱となっているのがテクノロジーの充実と、詳細にまとめられたチームの育成メソッドだ。
幸野氏が説明する。
「初期投資の1億5000万円を回収するためには高収益なクラブにしていかなきゃいけない。そこで僕らが何をやるべきかというと価値を創り出すこと、クラブとしての価値を高めることです。それが何かというと、子どもたちがサッカーやっていて何が楽しいかといったら試合をすることが楽しい。特に小学生年代から中学前半まではできるだけ全員を試合に出す。そして、弱くてもダメで、強くする。全員を試合に出しながら強いチームをつくることは二律相反するんですけど、この2つを追い求める。そういう方向性でずっときているんです」
月謝2万6000円。決して安くないお金を出す価値のあるクラブ運営
そこでキーになってくるのがデータ集積だ。まず、選手全員の出場時間を管理して、極端に試合出場が少なくならないようにしている。そして、映像分析アナリストを雇い、選手個々の動きのレクチャーを練習前の時間を使って行うのだ。こちらは勝つためのアプローチだ。
昨今のスポーツはサッカーに限らず、科学的な手法が避けられない領域にきているが、FC市川ガナーズでは最新の映像システムを使用して、選手を効率よく育てるための取り組みにまで着手している。こうした取り組みの一つ一つが、いわば、クラブの価値というものだ。
チームに所属する選手の月謝は2万6000円と高値がついているのはそのためで、選手の保護者たちはそれほどの月謝を出す価値をクラブに見いだしている。
さらに、育成メソッドは他に類を見ないほど綿密に作られている。何より驚いたのは、ポジションごとに求められるプレーの種類がきっちりと記されているところだ。攻撃の時、サイドバックはどうすべきか、守備時にはどの位置からプレスをかけるべきかなどである。これをプレーモデルというらしい。
幸野氏が力説する。
「アーセナルとしてスタートした時は基礎的なメソッドがあって研修を受けるんですけど、そういうところから僕ら独自のものを保とうとして、メソッドを研究して何年もかけて作り上げてきた。サッカーを4つの局面に分けて、攻撃の時、守備の時、攻撃から守備、守備から攻撃に移る局面では何をすべきか全てが決まっている。ビジネスでいえば、こういうことは当たり前なんですよ。日本人は“見て覚えろ”という考えが根強いですが、世界的なレベルでは通用しない。全てプレーモデルによって作り上げられている。選手たちが連動をしていった方が相手より一瞬早く動ける。その方が論理的じゃないですか。それで勝っていくための分析と研究をいつもしています」
「スポーツを教えるだけのクラブは生き残れない」
2020年に市川SC(千葉県1部/J1から数えて実質7部相当)と業務提携したFC市川ガナーズは将来的なJリーグ昇格を目指している。サッカースクールから始まったクラブはPFIを利用して独自のグラウンドとクラブハウスを構える大きなクラブへと成長した。
彼らが今、起こしている変革の一つ一つはサッカー界のみならず、育成の模範として、これからも注目を浴びていくことだろう。そして、サッカー・コンサルタントとして国内外を飛び回る幸野氏の声に続く者たちの存在が、サッカー界、ひいてはスポーツ界を大きくし、一時期のブームではなく、文化として定着していく礎の一つになるだろう。
幸野氏は言う。これはスポーツに関わる指導者・経営者に向けた強烈なメッセージだ。
「僕は日本中を回ってセミナーをやるんですけど、サッカーを教えているだけのクラブは生き残れないと話しています。ビジネス的な観点から見たら、お客様(選手)は神様だという感覚でいないといけない。子どもに怒鳴りまくって、試合に出さないといったことをやっているビジネスが横行しているのはスポーツの世界だけ。こんなことをやっていたら、スポーツ界は終わりますよ。他にゲームや楽しいアミューズメントだってある。今こそ変わらないと、僕らの未来はないんですよ。子どもたちのスポーツの未来は、野球もサッカーも、今こそちゃんと考えましょう。なぜスポーツをやるのか? なぜ子どもたちにとってスポーツが大事なのか? それを理解できなかったら、スポーツ界が廃れてしまう」
“男の子のスポーツ=野球”の時代は30年以上も前に終焉(しゅうえん)している。それどころか、スポーツは多様化し、さらに子どもが楽しむためのツールは果てしなく多くなっている。その中で、スポーツが選ばれていくためには、今、何が必要とされているのだろうか。
視聴者や観客が喜ぶための甲子園。本屋にずらっと並ぶ名将をうたったかのような書籍が世の中に乱立するのはおかしな世界だ。主役になるのは選手たちであるべき。そのことを忘れてはいけない。
<了>
なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点
高校サッカーに訪れたビジネスの波 スポンサー入りユニフォームの是非を考える
「リフティングできないと試合に出さない」日本の愚策。元ドイツ代表指導者が明言、平等な出場機会の重要性
「勝ちにこだわる」より大事な3つのこと ドイツ指導者が明かす「育成」の目的と心得
10-0の試合に勝者なし。育成年代の難題「大差の試合」、ドイツで進む子供に適した対策とは?
PROFILE
幸野健一(こうの・けんいち)
1961年9月25日生まれ、東京都出身。17歳の時にイングランドへ渡りプレミアリーグの下部組織でプレー。以後、指導者として日本サッカーが世界に追いつくために、世界42カ国の育成機関やスタジアムを回る。2014年4月にアーセナル サッカースクール市川の代表就任。2019年4月にFC市川ガナーズへと改称し、2020年千葉県1部の市川SCと業務提携、将来のJリーグ入りを目指す。また育成を中心に、サッカーに関わる課題解決を図るサッカー・コンサルタントとしても活動。2015年、小学5年生年代の400チーム、7000人の選手が参加する全国リーグ、プレミアリーグU-11を創設し、実行委員長として日本中にリーグ戦文化が根付く活動を実践している。著書に『パッション 新世界を生き抜く子どもの育て方』(徳間書店)。
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business -
「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案
2025.06.25Business -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験
2025.06.19Education -
なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意
2025.06.17Education -
部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方
2025.03.21Education -
高卒後2年でマンチェスター・シティへ。逆境は常に「今」。藤野あおばを支える思考力と言葉の力
2024.12.27Education -
女子サッカー育成年代の“基準”上げた20歳・藤野あおばの原点。心・技・体育んだ家族のサポート
2024.12.27Education -
「誰もが被害者にも加害者にもなる」ビジャレアル・佐伯夕利子氏に聞く、ハラスメント予防策
2024.12.20Education -
ハラスメントはなぜ起きる? 欧州で「罰ゲーム」はNG? 日本のスポーツ界が抱えるリスク要因とは
2024.12.19Education -
スポーツ界のハラスメント根絶へ! 各界の頭脳がアドバイザーに集結し、「検定」実施の真意とは
2024.12.18Education -
10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢
2024.08.19Education -
レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道
2024.08.06Education -
須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶
2024.08.06Education