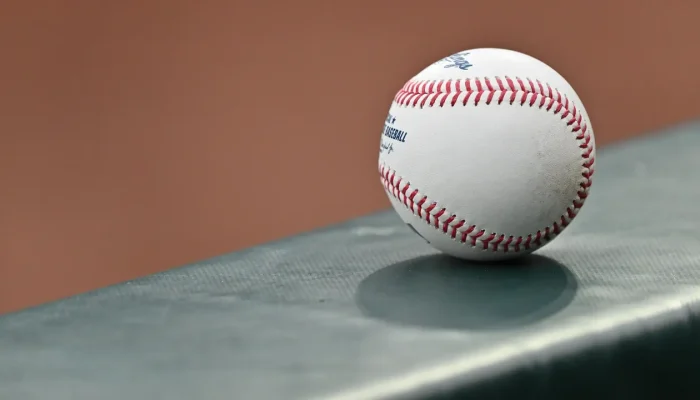“ブライトンの奇跡”から10年ぶり南ア戦。ラグビー日本代表が突きつけられた王者との「明確な差」
2015年9月19日、イングランドで開催されたワールドカップの舞台でラグビー日本代表が南アフリカを破った“ブライトンの奇跡”。あれから10年、舞台をロンドン・ウェンブリーに移して再び両国が相まみえた。結果は日本の完敗。それでも、指揮官エディー・ジョーンズは言う。「差が明らかになった。これを自覚することが重要」だと。“奇跡”から10年の時を経て、日本代表が見た「現実」と「希望」を追う。
(文=向風見也、写真=ロイター/アフロ)
“あれから10年”――ウェンブリーで再び世界王者と
南アフリカ代表はうんざりしていたのではなかろうか。
「あれから10年」
イギリス・ロンドン時間で2025年11月1日(日本時間11月2日)、ウェンブリースタジアムでの日本代表戦がこのストーリーテリングのもとで行われたことに対して、である。
いまから10年前の2015年9月、ワールドカップ・イングランド大会でのこのカードを日本代表が制した。
大会通算2度の優勝を誇っていた強豪国を、同1勝の新興国がノーサイド直前の逆転トライにより34―32で下したのだ。今度のマッチメイクの背景には、スポーツ史上最大の番狂わせと謳われる件の一戦がある。
もっともそれからの南アフリカ代表は、2019年に2度も日本代表に完勝。何よりその後、4年に1度のワールドカップで2019年、2023年と連覇している。直近の南半球でのラグビーチャンピオンシップも制覇しており、国際ラグビー界きっての巨象と見なされる。
たった1度の失意の敗戦を蒸し返されるのにそぐわぬ立場となり、果たして、この日も南アフリカが61―7で快勝した。
10年前に日本代表で指揮を執り、いま復帰2年目のエディー・ジョーンズ ヘッドコーチは淡々と述べる。
「今回、南アフリカ代表と自分たちとの差が明らかになった。これを自覚することが重要です」
挑戦者の狂気と大国の弛緩。“奇跡”を生んだ2つの要素
あの10年前の勝利の裏には、概ね二つの要素がある。
一つは挑戦者の常軌を逸した準備である。
早朝から複数回にわたる練習が当たり前だった第1次ジョーンズ体制は、イングランド大会の組み合わせが決まるや南アフリカ代表との初戦のプランを繰り返しアップデート。大会開催年には朝と夜の区別がつきにくいほどの過密日程の合宿で、蹴って大男たちを後退させる戦術「ビート・ザ・ボクス」を刷り込んだ。
さらにはその日の担当レフリーをキャンプ地に招き、一般的なレフリング分析を超越した解析に成功。当日、向こうがタックラーになった際の笛が多く吹かれたのは偶然ではない。
ピーキングも絶妙だった。ひたすら鍛えて本番間近にコンディションを整えたことで、世界屈指の大型選手たちとの接点で対抗できた。直前の壮行試合でやや差し込まれ気味だったのは、いわば壮大な「前振り」だった。
もう一つの要素として、別角度から考察すれば、向こうの混乱と弛緩も見逃せない。
あの頃の南アフリカ代表は、自分たちがしたいことと相手がされたら嫌であろうこととのバランスが取れずにいた。
特に日本代表戦では積極的にパスを回そうとしていて、本来の持ち味である推進力がやや削がれた格好。2011年から5年間サントリーサンゴリアス(現東京サントリーサンゴリアス)でプレーしたスクラムハーフのフーリー・デュプレアは後述する。
「あの試合ではフェーズ(を重ねる)ラグビーを多くしていました。日本に対して、それはよくないやり方だった」
そんな調子であるうえに、初戦をやや軽視した事実もある。
デュプレアを含む当時のスコッドは、当時のスタッフが2戦目以降でぶつかる他の上位陣に意識を傾けていたと証言する。
悲劇の1日を体験し、今年の再戦にも加わったセンターのジェシー・クリエル(現横浜キヤノンイーグルス)は、専門誌の取材にこう伝えたことがある。
「私は(当時)若手だったので、ただ傍観している感じでした。(かつて日本でプレーしていた)フーリーは『日本人をなめるな。見くびるな。強いぞ。彼らはいいチームだ』と。ただその言葉は、真剣には聞けていませんでした。決して彼らを見下したわけではありませんが、あそこまでの底力があるとは思えなかったんです。それが、見ての通りの結果です」
挑む側も、挑まれる側も、尋常ではなかった。それこそが「ブライトンの奇跡」であり、「あれから10年」の80分は決してそうとは言い切れなかった。
進化した王者に挑む、若返り最中の日本代表
現在2年後のワールドカップ・オーストラリア大会に向け、日本代表は大幅な若返りの最中だ。さらに故障者の続出、アタックコーチの突然の離脱と、置かれた状況は優しくはなかった。
日程も過酷だった。1週間前には国内でオーストラリア代表に15―19と肉薄も、それこそ当日までの約3週間は「ワラビーズ(オーストラリア代表の愛称)戦だけに集中している」とジョーンズ。その後、週明けに国内で2日間調整し、現地時間29日までのフライトから3日後にゲームという強行軍だった。
かたや南アフリカ代表は、2023年の世界一メンバーの多くが健在。当日は、マルコム・マークスらリーグワンでプレーする主軸級をずらりと並べていた。あの日のような、極東のチャレンジャーを軽視して臨むそぶりが見られないのが伝わる。
さらに昨年からは、元日本代表アシスタントコーチのトニー・ブラウンを招いている。ただでさえ大型選手のフィジカリティ、タックルが脅威だったのに、新セコンドのもと多彩な連携攻撃も刷新しているわけだ。
果たして今回、会場のウェンブリースタジアムでは接点という接点で日本代表の動きをストップさせた。ジャパンのランナーが一瞬でも孤立すれば、その場には大抵マークスらターンオーバーの達人が待ち構えていた。ジョーンズの述懐。
「ただ単に、キャリア(突進役)への寄りが遅かった。(全体的に食い込まれたため)後ろに戻りながらボールをもらっていたから、やるべきことに取り掛かるテンポが遅れてしまう」
キック処理でも緑のジャージーが優勢だった。
特に高い弾道の争奪戦で、流れを優位に持ち込めた。ハイボールキャッチとも呼ばれるこの分野は、10年前よりも前衛の防御が進歩した最近のラグビー界で重視されている。展開重視の国内リーグから人を集める日本代表は、ここがアキレス腱の一つだと指摘されて久しい。
対峙した側の最後尾、フルバックの矢崎由高は潔い。
「南アフリカの空中戦が強いのは僕が説明するまでもない。ベストは(蹴り込まれたボールを)クリーンキャッチすることですが、それを毎回できるとは思っていなかったですし、現実、そう(ずっと好捕できる状態)ではなかった」
時間が経つほどに、南アフリカ代表はカウンターアタックも冴えた。ウイングのカートリー・アレンゼが快足を飛ばし、プレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。
欧州遠征は続く。再現性ある「強豪撃破」の道を探して
競技のあらゆる面で王者が上回っており、追う側は有形無形の圧力を感じていただろう。日本代表は、序盤から陣地獲得やハンドリングでミスがかさんだ。向こうの強みがスコアに変わるのは、自然な流れだった。
かねて「2015年のチームよりもよくなるポテンシャルがある」と訴えていたジョーンズだが、どんな策をもってしてもベーシックな領域における現時点での「差」は認めざるを得なかった。
それでも、立ち止まるわけにはいかない。
10年前の一戦がいかに希少性のあるものだったかを再確認した日本代表は、そのまま欧州にとどまりアイルランド代表(日本時間11月8日)、ウェールズ代表(同11月16日)、ジョージア代表(同11月22日)と順にぶつかる。世界ランクで上回る国との連戦で底力をつけ、いつか、再現性のある強豪国の倒し方を確立させたい。
<了>
「日本は引き分けなど一切考えていない」ラグビー南アフリカ主将シヤ・コリシが語る、ラグビー史上最大の番狂わせ
ラグビー日本代表“言語の壁”を超えて。エディー・ジョーンズ体制で進む多国籍集団のボーダレス化
ラグビー界“大物二世”の胸中。日本での挑戦を選択したジャック・コーネルセンが背負う覚悟
「ザ・怠惰な大学生」からラグビー日本代表へ。竹内柊平が“退部寸前”乗り越えた“ダサい自分”との決別
ラグビー日本人選手は海を渡るべきか? “海外組”になって得られる最大のメリットとは
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯
2026.01.30Career -
ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件
2026.01.23Career -
ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地
2026.01.23Career -
世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断
2026.01.23Career -
女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道
2026.01.20Career -
丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化
2026.01.19Career -
伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”
2026.01.16Career -
史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北
2026.01.16Career -
狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生
2026.01.16Career -
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion -
「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地
2025.12.23Opinion -
「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実
2025.12.23Opinion -
なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋
2025.12.17Opinion -
中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”
2025.12.10Opinion -
『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏
2025.11.28Opinion -
デュプランティス世界新の陰に「音」の仕掛け人? 東京2025世界陸上の成功を支えたDJ
2025.11.28Opinion