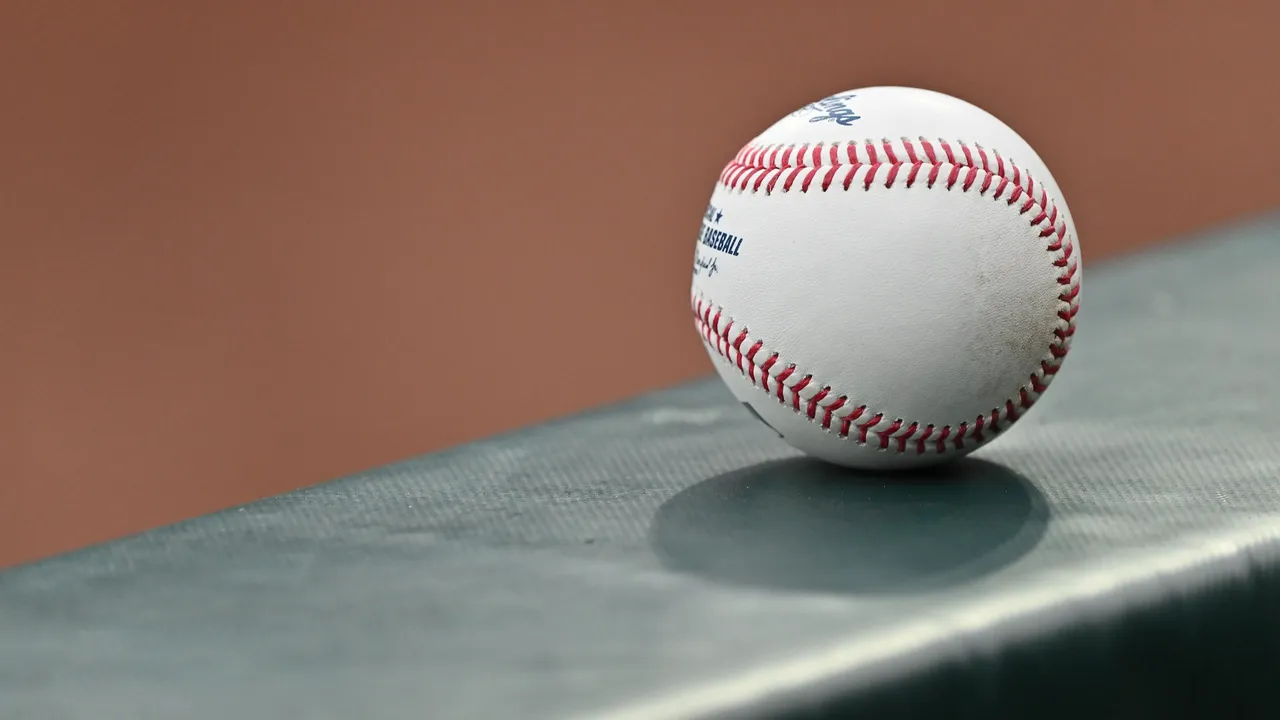
丸の“危険な走塁”に潜む巨人大敗の本質。すべてを見誤る「謝ったから終わり」の解決法
激動の2020年プロ野球を締めくくる日本シリーズは、福岡ソフトバンクホークスの4年連続日本一で幕を閉じた。2年連続の4連敗を喫した巨人とソフトバンクの実力差、ひいてはセ・リーグとパ・リーグの格差が話題になっているが、作家・スポーツライターの小林信也氏は、今季の日本シリーズには「見過ごしてはいけないプレーがあった」と語る。第1戦、巨人・丸佳浩の走塁と、その後の対応をめぐる問題の本質とは?
(文=小林信也、写真=Getty Images)
巨人の終焉を感じさせた「丸の走塁」
今年の日本シリーズは、日本プロ野球の深刻な行き詰まりを白日の下に晒(さら)す結果となった。2年連続で巨人がソフトバンクに4連敗。「セの覇者」、というより「球界の盟主」を自認してきた巨人の権勢が、ついに終焉を迎えたと多くの人が感じたのではないだろうか。
勝負に負けたから、ではない。巨人が放つ雰囲気が、すでに王者のそれではなく、盟主の誇りも感じさせない。「こういうチームが野球のお手本なら野球なんて嫌い」と思わせる低次元な振る舞いを随所で見せながら、当人たちはおごりか慢心か、まるでそれに気づいていない。まさに末期症状だ。
第1戦、丸佳浩の走塁とその対応には、巨人の「終わっている」体質が象徴的に表れていた。
2点リードを追う4回裏、無死1、2塁で打席に立った丸は千賀滉大投手に対してショートゴロ、併殺打に倒れた。一塁に駆け込んだとき、一塁手の中村晃がごく普通の体勢で伸ばした左足のかかとの上、アキレス腱(けん)あたりに丸の左足、スパイクの裏側が接触した。スバイクの歯が食い込んでいたら大ケガになりかねなかった。
その瞬間、2017年、夏の甲子園3回戦で起きた出来事を思い起こした野球ファンも多かっただろう。
仙台育英の打者走者が、大阪桐蔭の一塁手の伸ばした足を蹴った。本人の意図は置くとして、明らかに「蹴った」と見える行為。打者走者は次の瞬間、体勢を崩して転倒し、一塁手はその場にうずくまってしまった。
なぜかこの出来事はテレビなどの大手メディアで大々的に取り上げられることがなく、SNSなどを中心とするネットで拡散されたが、結果的には一部の熱心な高校野球ファンが共有するにとどまった。日大アメフト部の「危険タックル問題」がネットに端を発して、テレビの情報番組で大騒ぎになったのはその翌年のこと。甲子園の事件が前段となり、アメフトで大きく取り上げられる流れを作ったようにも感じた。
丸の行為は、仙台育英の打者走者に比べれば小さなアクションで、その動きを見ただけでは「故意だ」と断定はできないかもしれない。だが、この場面で「故意か偶然か」は関係がない。
一塁手の伸ばした足に接触するのは「ありえないプレー」
仮に故意であったなら、丸は野球の試合に出る資格がない。言うまでもなく、スポーツマンの大前提である「スポーツマンシップ」を持っていないからだ。
例えばボクシングで、「ローブローは反則だ」と知っていながら、巧妙に急所を狙ってパンチを放つようなものだ。そんな選手がリングに上がることは許されるだろうか。あるいは陸上競技の長距離レース、集団で走っている中で前や横にいる選手の足を意図的に蹴るなどすれば、深刻な転倒事故、そして選手生命にも影響する大ケガにつながりかねない。そういうやり方で勝とうとする選手と一緒にレースをすることを他の競技者たちは認めないし、許さないだろう。
野球も同じだ。一塁手は、通常の体勢で野手の送球を受ける際に、打者走者と接触することなど想定していない。もしその安全が脅かされるなら、野球という競技の安全性が成り立たなくなる。
少年時代から長く野球を愛し、選手として、ファンとして、取材者として、また少年野球や高校野球のコーチ・監督として60年近く野球に携わってきた私自身、ごく通常の体勢で足を伸ばした一塁手と打者走者の足が接触する場面など、一度たりとも見たことがない。野球を始めたばかりの小学生でもそのような間違いは犯さない。
安全に一塁を駆け抜けることができない打者走者は、打席に立つ資格がない。あのプレーはそれほど“ありえないプレー”なのだ。
ケガや重大事故への警戒を怠るべきではない
一塁手と打者走者の接触は、野手からの送球がそれた場合に起こる可能性はある。送球が本塁方向にそれ、捕球しようファーストミットを伸ばした一塁手の腕に走ってきた打者がぶつかる場合もあるし、高い悪送球に一塁手がジャンプしたり背を伸ばしてバランスを崩したら、足を踏まれたり衝突する恐れもある。だが、一塁手が通常の体勢でベースの端を踏み、前足を伸ばして捕る場合に、打者走者と接触する可能性はほぼゼロだ。
まさに今回の接触はほぼ可能性がないに等しいケースで起こった。不用意にベースの真ん中付近に置いた足を踏まれるならまだしも、中村はごく普通に足を伸ばし、ベースの端を踏み、送球もそれたわけではなかった。
野球界は長く本塁上での衝突プレーを正当でスリリングな場面として容認してきた。しかし数年前、重大な事故の頻発を経て、メジャーリーグが禁止にかじを切った。コリジョンルールを採用し、本塁上での接触や衝突を禁じたのだ。それくらい、安全に対する認識は高まっている。
私は走者の安全や権利を優先し、捕手に不利なコリジョンルールは、野球の原則と矛盾する不備があると感じているので、そのまま日本に導入したことに異議を唱えている。不備がありながらもコリジョンルールが日本でも採用された背景には、現代においてはケガを防止する意識が何よりも大切だという判断からだろう。
それなのに、無風状態の一塁で接触プレーが起きた。
原監督、巨人にしても「謝って不問に付す」はありえない
巨人の原辰徳監督は、このプレーをどう理解し、どう判断したのだろう?
翌日の試合前、丸がソフトバンクのベンチを訪ね、工藤公康監督に謝罪した。中村には試合前のシートノックで一塁の守備位置付近にいた時に少し離れた位置から頭を下げた。中村は両手で丸を作って和解が成立したように報じられた。ソフトバンクは謝罪を受け入れ、それ以上の抗議はしなかった。中村にケガがなかったことに加え、事態を荒立てれば、プロ野球そのもののダメージになる、騒ぐのも恥ずかしいといった意識もあったのかもしれない。
しかし、この問題は「謝ればいい」というものではないほど、大きな問題だ。
このような「ありえない愚行」を演じた丸が、われわれのように野球を志した者、そしてファンにとって垂涎(すいぜん)の舞台である日本シリーズに立っていることが情けない。野球への冒瀆(ぼうとく)とさえ感じてしまう。内部でどんな話があったかは知る由もないが、表向きにはこれを許し、何事もなかったかのようにスルーしてしまった原監督と巨人の認識には落胆と失望を感じた。
あの瞬間から丸を試合から外し、二度と日本シリーズの舞台に立たせない見識があってもよかったと私は思うが、いまのところ、そこまでの提言は他に見ていない。
思えば現在ソフトバンクの会長を務める王貞治氏は、一塁を守っていた現役時代、内野手からの送球を受けると、ベースに置いた足をリズミカルにすぐ離すスタイルで有名だった。
子どもたちがそのまねをするのが一つの遊びになっていたし、「送球を捕るより先に足を離しているのでは?」とちまたでは囁(ささや)かれていた。あのプレーは、無意識のうちに自分の足を守るためのプレーだったのだろうか? 毎日の試合の中で、打者走者に足を踏まれる、蹴られる不安があったからなのだろうか?
それが自己防衛のためだったとすれば、プロ野球の世界ではそうしたラフプレーが相当古くからくすぶっていたことになる。
巨人や横浜で長く一塁手として活躍した駒田徳広氏も、「送球を受けるとき、走者が一塁にすごい勢いで走ってくるのが怖かった」と述懐している。
一塁手以外の選手たちの大半が「一塁手なんて簡単だ」と思っている以上の難しさや重圧が実は一塁手にある。私も高校時代、一塁を守った経験がある。
足を踏まれないベースの踏み方、送球がそれた場合の対処法などは教わるが、それでも野手からどんな送球が来るかわからない。無事にアウトにできるかどうか、内心の重圧は見ているよりずっと大きい。それだけに、足を蹴られるかもしれない危険性などあってはならない。
このようなプレーを放置していたら、昨今叫ばれている「野球離れ」は歯止めが利くどころか加速していくだろう。今回の接触プレーとそれに対する対応は、日常的な暴言、支配的な指導体質、勝てばすべてが肯定される勝利至上主義のまん延など、野球人口の減少につながる問題を象徴している。親たちが野球のような野蛮な競技にわが子を託したくないと考えるのは当然で、野球界が抱える体質への嫌悪や敬遠が「野球離れに」の原因になっている現実を当事者である野球界がまだ自覚できていない。
今回、原監督や巨人が、そして多くのメディアもファンも丸の走塁をさほど問題視しなかった背景にも、その甘い認識が見て取れる。
巨人が勝つことが正義ではない。巨人が勝てばプロ野球が発展し、野球は人気を伸ばすという信仰はもはや幻想だ。このままでは巨人の崩壊が野球の終わりにもなりかねない。いまこそ、巨人への忖度(そんたく)を捨て、プロ野球改革を始めなければ手遅れになる。
ソフトバンクの快勝は、充実した戦力、工藤監督の采配だけの成果ではないだろう。もっと本質的に、球団経営、チームづくり、野球の発展にかける情熱や哲学の違いが反映したものだと感じる。
巨人だけでなく野球界は、相当深刻な状況にあることを改めて直視するべきだと思う。
<了>
王会長提言、なぜ「16球団構想」は進まないのか? “球界のドン”と「変わらなくて当たり前」の呪縛
三井不動産の東京ドーム買収騒動。マツダスタジアムを手掛けた専門家はどう見た?
「指導者・イチロー」に期待する、いびつな日本野球界の構造をぶち壊す根本的改革
この記事をシェア
KEYWORD
#COLUMNRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」
2025.07.18Opinion -
なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある
2025.07.18Opinion -
ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地
2025.07.16Career -
ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し
2025.07.16Opinion -
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training -
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」
2025.07.18Opinion -
なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある
2025.07.18Opinion -
ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し
2025.07.16Opinion -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion -
日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」
2025.06.16Opinion -
野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」
2025.06.06Opinion -
冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは
2025.06.06Opinion -
なでしこジャパン2戦2敗の「前進」。南米王者との連敗で見えた“変革の現在地”
2025.06.05Opinion -
ラグビー・リーグワン2連覇はいかにして成し遂げられたのか? 東芝ブレイブルーパス東京、戴冠の裏にある成長の物語
2025.06.05Opinion
























