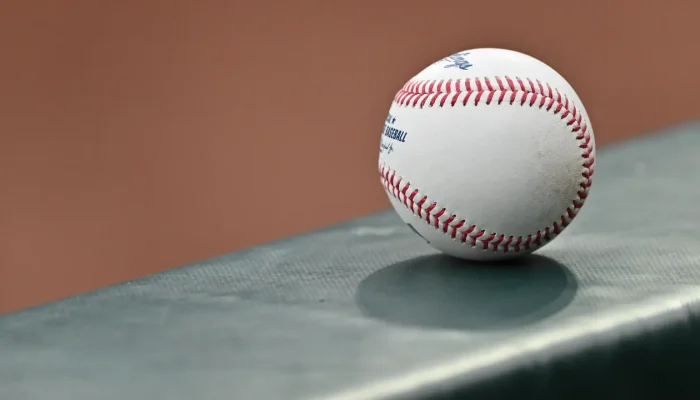「どこで試合してるか分からなかったよー」奥原希望、バドミントン界の危機を感じた友人の一言
2016年、リオデジャネイロオリンピックで日本人初となるバドミントン・女子シングルスでの銅メダルを獲得した奥原希望。2019年1月には太陽ホールディングスと所属契約、実業団が主体のバドミントン界では異例、初の完全プロ宣言を行い、新たなキャリアを築いている。
本来ならば東京オリンピックが行われていたはずの2020年を前にプロ宣言をした理由、東京以降のキャリア展望は? 奥原希望の“BEYOND2020”について聞いた。
(インタビュー・構成=大塚一樹[REAL SPORTS編集部]、撮影=軍記ひろし)
金メダルのために「レベルアップの時間」をつくりたかった
「もちろん大きな理由の一つは東京で金メダルを取るためです」
リオデジャネイロオリンピックの銅メダリスト、奥原希望は2018年12月、それまで所属していた日本ユニシスを退社、翌年の1月にはプロとしての活動を開始した。理由の一つは地元開催のオリンピックで金メダルを取るため。
「環境を整えたかったというのはあります。代表としての活動、実業団の試合と連戦が続く中で、体のケアで精いっぱい。金メダルを目指す上で、自分のレベルを上げるためのトレーニングが十分にできないことに不安がありました」
実業団主体で個別に強化されてきた日本のバドミントン界は、近年、日本代表の強化合宿、ナショナルチームとしての国際試合転戦で大きな結果を得てきた。日本代表の活動は年間250日にも及び、トップ選手のスケジュールには国内の大会、実業団のリーグ戦が加わる。
「本当に休みがないんです。海外の選手は国際大会のない期間を休養に充てたり、足りない部分を補強するトレーニングを積んだりしています。金メダルへの差を埋めるためには、練習に費やす時間を持たないとダメだというのがあって」
加えて奥原は、高校3年生のときに左ひざ半月板を損傷、復帰後には右ひざも痛め、若くして両ひざを手術している。リオ後にも右肩と右ひざのケガを抱え、不本意な欠場も経験している。
「シーズンをフルに戦うことでまずケガのリスクが伴う。ケガのことを気にしていると、自分のプレーレベルをもうワンステージ、ツーステージ上げたいという時に、やっぱり上げられることができないんです。ケガをしないようにケアしているうちに、現状維持が精いっぱいになってしまう環境を変えたかった」
プロになって、支えてくれる人との関係がより深まった
プロ選手として活動することで、すべてが個人の裁量に委ねられることになった。プロ宣言後に大きく変わったのは、能動的にスケジュールを組める、強化プランを自分発信で遂行できることだった。
――プロ選手になって、意識の面で変わったことはありますか? プロフェッショナル・バドミントンプレーヤーになったんだみたいな。
奥原:そんなドヤった感じはないですけど(笑)、個人競技とはいえ、それまでチームとして動いていて、トレーニングだけじゃなくて生活も全体に合わせたりするところはどうしてもありました。今は完全に自分だけのスケジュールで動けているので、ストレスがなくなりました。もちろんその分、責任は伴いますが。
――プロになるということは全部自分でやるということでもありますよね。組織に守られていた部分もあったと思うのですが。
奥原:そこは全然逆で、プロになったことでより深く接してくれる人、関わってくれる人が増えました。マネジメント会社もそうですし、コーチやトレーナー、「チーム希望」として、直接、目に見える形で関わってくれるので、やりがいはありますね。
――プロ選手は結果を出すだけでなく、対外的な発信、選手としての価値をアピールする部分も求められると思うのですが、その点についてはどのように捉えていますか?
奥原:「自分」をアピールしやすくなりましたね。もちろんリスクもありますけど、でも、いい意味で「本当の自分」を表現できる立場になったと思っています。
日本のバドミントンは、一気に強くなって、すごく注目されるようになったし、メディアにも取り上げていただく機会が増えましたが、野球やサッカーのようなメジャースポーツに比べると、自分自身も含めて選手の、発言力・発信力はまだまだですよね。ここの部分は選手自身が考えて、何かを変えようと思わないと変わっていかないと思っています。
海外のバドミントン選手と比べても、発信力や競技の普及、バドミントン界全体を自分の課題として考えている選手はやっぱりまだまだ少ないのかなと思っています。

コロナ禍、大坂なおみの発信で見つめ直した自分の“存在意義”
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって東京オリンピックは延期、バドミントンの国際大会も3月を最後に長い中断期間に入った。インタビューは、BWFワールドツアーの再開初戦、デンマークオープン前に行われたが、コロナ禍による自粛期間、大坂なおみのBlack Lives Matterをめぐる発言に象徴される社会問題とアスリート、スポーツの関係など、「プロ」として考えさせられることも多くあった。
――コロナ禍によって活躍の場を失ったアスリートの中には、「アイデンティティーの喪失」のような感覚に陥った人もいると聞いています。オリンピックがなくなって、活躍の場がなくなったときに「自分の価値」について見つめ直したり。
奥原:それはすごく考えました。スポーツの価値だったり、自分の立場や価値はなんなんだろう? 誰かに求められなければ世の中に貢献できないのか、今の自分は「本当に無力だな」と思ったり、本当にいろいろ考えました。
でも、やっぱりバドミントンしかないというか、今の自分の役割はまずはバドミントンの選手であること、それが一番だなと思います。
オリンピックがどうなるかわからないとか、大会がないとかいろいろ不安に思うことはありますが、今やるべきことは本当に練習。練習の先にある試合で結果を出すこと、プレーを見てもらうことしかないので、そこは切り替えてやっています。
――プロとしての発信力、発言力の話も出ましたが、大坂なおみ選手の発言、行動は、日本のアスリートにも大きな影響があったのではないかと思います。奥原選手はどんなことを感じましたか?
奥原:大坂なおみ選手も、自分で考えて行動したり、発言しているからこそ、発言力や影響力があるんだと思うんです。あの発信(黒人男性銃撃事件への抗議を表明し、ウエスタン&サザン・オープン準決勝を棄権した)に対していろんな意見はありましたが、アスリートがああいう問題を自分ごととして行動できるのは、すごく社会にとっても影響力があるんだなと改めて実感しました。
じゃあ自分が社会問題に対して自分ごととして捉えられるくらい考えているかというかというと、そこまではできていないと思いますし、他人(ひと)ごととしているんじゃないかなという感覚もあります。
試合に出ないという決断をしてでも何かを伝えたい、伝えるべきことがあると思えるのか? 大坂選手の行動を見て、社会で起きている問題を自分の課題として考えられる能力が低いなと自覚することができました。
――大坂選手が自ら語ったように、「アスリートである前に、一人の黒人女性」という圧倒的当事者だったことも大きかったですよね。大坂選手の影響力という話も出ましたが、世界のバドミントンは男女ツアーが世界的に成功しているテニスを参考に戦略を見直しているという話もあります。
奥原:世界バドミントン連盟(BWF)も、ツアーの仕組みや規模をテニスに近づけたいということでいろいろ取り組んでいるんですよね。ただ、結局は選手それぞれの意識っていうのが上がらないと、バドミントンが世界的に盛り上がっていくことはないと思います。プロテニスプレーヤーにも友達がたくさんいるので、いろいろ話してますけど、「なんで、そんなことしているの?」とか「それは必要なくない?」とか言われること多いんです。自分たちもわかってはいるけど、自分の課題として向き合って声をあげるとか、行動しようというところにはいかないんです。小さなことの積み重ねが大きな差になっている。そこをクリアしていかないと……。
――日本では、社会問題や政治的な発信、時には「自分」を伝えようとする発信でさえ、「競技がおろそかになっている」「結果が先」という声が必ず上がります。そういう声は気になりますか?
奥原:あんまり気にならないんですよね(笑)。否定的な意見を目にしても、「そういう意見があるんだ」と素直に思いますし、そういう意見もすごくありがたいし、受け入れるんですけど、その後どう自分に取り入れるかは自分で決めたい。
よく「好きな俳優さんとか、憧れの選手とかいないの?」と聞かれるんですけど、私、いないんですね。なんでいないんだろうというのを考えたんですけど、カメラの向こう側で演技をしている俳優さんの本心を知らないじゃないですか。やっぱりじかに接しないとわからない。内面も知らない人を好きとか憧れるのが、なんていうか「無責任」に感じてしまうんです。
だからこそ私も「ファンです」って言われるよりも、短い時間でも直接会ったり、人となりがわかるような発信に触れたときに「いいな」って思ってもらえたほうがうれしいんですよね。そういうこともあって、発言や行動に外から何か言われてもあまり気にならないのかもしれません。

注目を浴びながら感じるバドミントン界の「今そこにある危機」
――オリンピック以降、プロ選手としてどんなキャリアを歩んでいきたいか、ちょっと気が早いですけど、引退後のキャリアについて何か考えていることはありますか?
奥原:現状維持ではなくて常に挑戦、いろんなことにトライしていたい。アスリートはそうであるべきだと思っているんです。
バドミントン界全体でも、結果が残せているうちはメディアにも取り上げていただけると思いますが、東京オリンピックが終わって、みなさんの興味が薄れたときに、結果以外にも何かないと、たくさんあるスポーツの中で生き残っていけないと思っています。
――引退後、バドミントン協会なのか、運営側に回るという選択肢も?
奥原:やりたいですね。必要とされればやりたいです。「いらない」って言われたらやめよう(笑)。
バドミントンは、観戦体験というか見てくれる人へのアプローチがまだまだと思うんです。海外の試合はどんどんエンタメ化が進んでいて、照明や演出のショーアップがされているんですけど、国内の試合は競技のため、順位を決めるためという意味合いが強いので、まだまだ観戦してくれる人に目が向いていないんですね。
他の競技の友達が来てくれたとき、「どこで試合してるかわからなかったよー」と言われたことがあったんです。たしかに国内の大会は特に数日でとんでもない数の試合をしなければいけないこともあるので、たくさんのコートで一斉に試合をしていて、どこで誰が試合をしているのかわからないんですよね。
格闘技イベントのRIZINを見に行かせていただいたときに感じたんですけど、光と音、照明と演出が会場を盛り上げることで、観客も一体になって盛り上がれるんですよね。演出以前に環境の問題もありますが、大会で同じ会場を使っていても、フェンシングはいろいろ試しているじゃないですか。どんどん変えようとしているし、実際に変わっていますよね。
コロナの影響でオンラインイベントが増えていますが、やっぱりスポーツ観戦は生で見てもらうのが一番だと思うんです。コロナが収束後には、そこも自分ごととして捉えて、変えていく行動を起こせたらなと思っています。
時代の流れが変化していく中でも、常に攻めの姿勢でいたい。自分にしかできないことに積極的に取り組んでいきたいです。
【前編はこちら】「ダブルスは絶対できない」奥原希望が“勝てない”シングルスに拘り続けた理由とは
<了>
[アスリート収入ランキング]トップは驚愕の319億円! 日本人は2人がランクイン!
伊達公子さんが警鐘 日本のテニスコート事情が次の錦織、なおみの登場を阻害している!?
なぜ今の子供は「卓球」を選ぶのか?「地味」から一転「親子人気」勝ち得た4つの理由
小林祐希が“タトゥー”と共に生きる理由とは?「それで代表に選ばれなかったら仕方ない」
PROFILE
奥原希望(おくはら・のぞみ)
1995年3月13日生まれ、長野県出身のプロバドミントン選手。太陽ホールディングス所属。小学校1年生からバドミントンを始め、中学2年生で全日本ジュニアバドミントン選手権大会優勝、中学3年生で同ジュニア部門準優勝。埼玉県立大宮東高等学校へ進学後、1、2年生の時に全日本ジュニア選手権を連覇。1年生の時から国際試合にも出場し、世界ジュニアバドミントン選手権大会で銅メダルを獲得。同年、全日本総合選手権を16才8カ月で制し最年少バドミントン全日本女王となり、2011年12月21日付けで日本代表に初選出。日本ユニシスへ入社後、2015年に全英オープンで日本勢39年ぶりとなる優勝、日本人選手初のBWFスーパーシリーズファイナルズ女子シングルスで優勝を飾るなど快進撃を続けた。2016年リオデジャネイロオリンピックでは日本人初のシングルスでメダル獲得(銅メダル)、2017年に日本人初の世界選手権女子シングルス優勝。BWF世界ランキング最高位は1位(2019年10月29日。2020年11月4日時点で4位)。2018年に日本ユニシスを退職し、2019年1月に太陽ホールディングスとプロ契約。2019年12月に開催された第73回全日本総合選手権大会では、自身4年ぶり3度目となる優勝、国際大会(デンマーク)で優勝を飾る。自国開催となる 東京オリンピックでメダル獲得を狙う。
この記事をシェア
KEYWORD
#INTERVIEWRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
日本人のフィジカルは本当に弱いのか? 異端のトレーナー・西本が語る世界との違いと“勝機”
2026.03.02Training -
風間八宏のひざを支え、サンフレッチェを変えたトレーナーとの出会い「身体のことは西本さんに聞けばいい」
2026.03.02Career -
野球界の腰を支える革新的技術がサッカーの常識を変える。インナー型サポーターで「適度な圧迫」の新発想
2026.03.02Technology -
なぜ老舗マスクメーカーはMLB選手に愛される“ベルト”を生み出せた? 選手の声から生まれた新機軸ギアの物語
2026.03.02Business -
「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質
2026.03.02Opinion -
クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地
2026.02.27Career -
“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」
2026.02.26Education -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」
2026.02.20Career -
「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念
2026.02.20Career -
ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断
2026.02.20Career
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質
2026.03.02Opinion -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟
2026.02.06Opinion -
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion -
「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地
2025.12.23Opinion -
「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実
2025.12.23Opinion