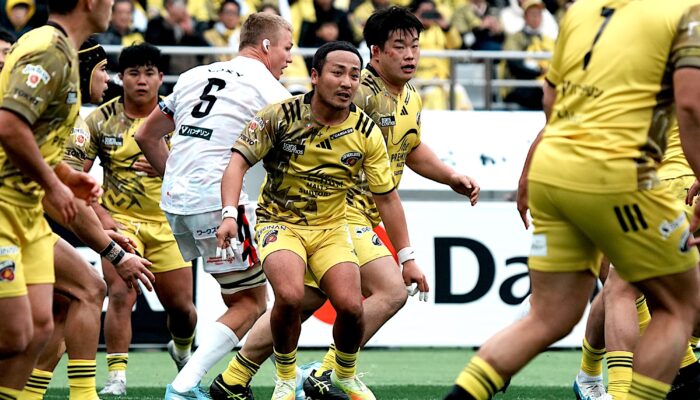子供の野球チーム選びに「正解」はあるのか? メジャーリーガーの少年時代に見る“最適の環境”とは
どのスポーツにおいても「我が子をどのチームに入れるべきか?」は、親にとってとても悩ましい問題だ。かつては選択肢が少なかった野球においても、近年は異なる連盟に所属するチームが同地区に複数あるケースも珍しくないという。では「野球がやりたい!」と言う我が子をどんなチームに入れるのが正解なのか? 長年、野球の育成年代の取材を続ける花田雪氏が考える、令和の指導者、保護者に求められる子どもたちの導き方とは?
(文=花田雪、写真=ZUMA Press/アフロ)
「子どもが野球をする場」の選択肢は増えている
「ウチの子どもをどんな野球チームに入れたらいいですか?」
編集者、スポーツライターという仕事をしていると、こんな質問をされることがある。正直に言うと、何と答えていいのかいつも迷ってしまう。
これまで、多くのプロ野球選手を取材してきた。選手に自らの少年時代のエピソードを聞いたり、後のプロ野球選手を指導した少年野球の監督・コーチに話を聞いたことも多々ある。
それでも、この質問の「正解」はいまだに見えてこない。
野球界は今、過渡期を迎えている。競技人口の減少はもちろん、「少年野球」のあり方も見直されている。中学校の「部活動」も地域への移行化が少しずつだが現実味を帯び始めている。 それと同時に、実は「子どもが野球をする場(習う場)」に選択肢が増えているのも事実だ。小学生であれば軟式野球チームだけでなく、硬式野球のリトルリーグ、ボーイズリーグといった異なる連盟のチームが同地区に複数あるケースも珍しくない。中学も同様に、部活動ではなく硬式、軟式の「クラブチーム」でプレーする選手も増えている。また、クラブ形態ではなく個人指導や、スクールといった形をとるケースもある。
「今の少年野球チームは『成果を披露する場』なんですよね」
関東地区でいうと、かつては小学生であれば地元の少年野球チームかリトル、中学生であれば部活動かシニアの、多くても「2択」程度だった選択肢が細分化されている印象は強い。例えば軟式少年野球でも、保護者が車で送迎して自宅から少し遠くのチームに所属しているという話も耳にする。
その背景には、「熱心な保護者」の存在もあるだろう。「野球がやりたければ、近くのチームに入ればいいでしょ」ではなく、選択肢があるぶん、どのチームに入団するのか熟考する。チーム選びの理由は当然人それぞれで、指導方針やチームの雰囲気はもちろん、立地や、金銭的な問題もあるはずだ。
だからこそ、私のような一介のスポーツライターにも「どんなチームに入ったらいいのか」という質問が飛んでくるのだろう。
冒頭でも書いたが、この質問の「正解」は分からない。ただし、それに近づくための「ヒント」くらいは見えてくるかもしれない。そのためにはまず、野球界の「育成」の現状を少しでも知る必要がある。
思い出されるのが、あるプロ野球OBの言葉だ。そのOBは現役引退後、プロはもちろん、学生や社会人、U-12日本代表など各カテゴリの指導を精力的に行っていたが、少年野球の現状をこう話してくれた。
「今の少年野球チームは、選手が『うまくなる場』ではなく『成果を披露する場』なんですよね」
真意はこうだ。ひと昔前と違い、現在のアマチュア野球界からはいわゆる「厳しい指導」が消えつつあり、練習時間も制限されることが多い。特に少年野球の場合は練習が土日のみ、しかもどちらかは半日だけ、というケースも増えている。練習内容もどちらかといえば選手をノビノビ、楽しくやらせるメニューで組まれているため、地味でキツイ基礎練習にはあまり時間を割かない傾向にある。 そうなったとき、どこで差が生まれるのかというと、練習のない平日に、個人でどれだけやってきたか――だという。
どこにでもいる平凡な野球少年が“日本のエース”に
土日の練習や試合は、子どもたちが個々でやってきた練習で「どれだけ上達したか」を披露する場。そんな側面が強くなっているという。
これについて良し悪しを論ずるつもりはない。厳しい練習の排除や練習時間の短縮は、子どもたちの心身の健康を考えてのもの。過度な練習や過密日程での試合出場が、育成年代の子どもたちの「故障」を誘発してきた事実もある。
では、「育成」におけるクラブチームの役割が変化していると考えた場合、果たしてどんなチームが「子どもが成長できるチーム」と言えるのか?
参考までに、現在メジャーリーグで活躍する何人かの選手の少年時代のエピソードを紹介したいと思う。
例えば、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸。昨オフ、ルーキーながら12年総額3億2500万ドルという投手史上最高契約を結んだ“日本のエース”は、中学までを出身地である岡山県で過ごした。中学入学と同時に入団したのが地元の硬式野球チーム・東岡山ボーイズだ。
入団時の山本少年は小柄で、どこにでもいる平凡な野球少年だった。1~2年生までは試合に出ることもほとんどなく、最高学年となった3年生でようやくレギュラーを獲得。エースではなくセカンドと投手を兼任し、背番号も4だった。
当時の指導者に話を聞くと、特に我が強いわけでも、ヤンチャなわけでもなく、目を離すとうまくサボる「どこにでもいる中学生」だったそうだ。そんな山本少年が一気に伸びたのが中3の夏が終わり、チームを引退した後。宮崎県の都城高校への進学が決まり、本人にも自覚が芽生えたのか、新チームに交じって練習に参加しながら来る日も来る日も投球練習に明け暮れたという。
指導者は、「本人がやりたいのであれば」と山本少年のヤル気を尊重し、特に口を出すこともなかったという。すると、高校入学までの半年余りで球速が10キロ以上アップ。指導者も驚く急成長を見せた。
「怪物」だった2人。鈴木誠也と吉田正尚
シカゴ・カブスに所属する鈴木誠也の場合はこうだ。東京の荒川シニアに所属していた鈴木少年は、リトル時代から地域にその名を轟かす「怪物」だった。当時のポジションはピッチャーで、小学校時代には1学年下のキャッチャーがあまりの速さにボールを捕ることができず、「高めに浮いたら全部パスボールで試合にならなかった」という。
中学に上がっても持ち前の才能をいかんなく発揮した鈴木少年だったが、同時に「ヤンチャ」な一面もあり、指導者は最後の夏までエースナンバーを付けさせなかったという。「お山の大将にしてはいけないと思った」と、当時の指導者は語ってくれた。
決して練習熱心なタイプではなかったというが、時折指導者の自宅にあるネットを使ってティーバッティングを自主的に行っていたそうだ。その時は、たとえ放課後、遅い時間でも快く場所を提供し、本人がやめるまで練習させていたという。
ボストン・レッドソックスの吉田正尚も、鈴木誠也と同じように幼少期から才能を発揮。中学時代に所属した鯖江ボーイズの指導者は当時を振り返って「入団前の体験会の時点でモノが違った」と語る。スイングがとにかくきれいで、3年間バッティングに関してはほとんど指導しなかったという。
本人がやりたい瞬間、やりたいことをやらせながら、指導者は…
もちろん、山本由伸、鈴木誠也、吉田正尚の3人は恵まれた才能と類まれなる努力で現在の実力を身に付けた「特別な存在」でもある。ただ、この3人の育成年代の指導者に共通しているのは「放任」ではないだろうか。
「放置」ではなく「放任」。
決して勝手にやらせるわけではない。本人がやりたい瞬間、やりたいことをやらせながら、指導者は一歩下がった視点でそれを見守る。例えば鈴木誠也のようなヤンチャなタイプは、自主練の最中に指導者から横やりを入れられたらやる気をなくして練習をやめてしまうかもしれない。
山本由伸は中学野球を引退した後に覚醒したが、指導者は「そりゃ、もうちょい早めにヤル気出してよ……とは思いますよ(笑)」と冗談めかしながらも、チーム在籍中に何かを強制することは決してなかった。
クラブチームの立ち位置が「個々の練習の成果を披露する場」へと変貌しつつあるのであれば、大切なのは子どもたちがどれだけ自主性を持って、日々の練習に打ち込めるかだ。
例えば、平日に子どもたちが自主的にこなしてきた練習を、土日のチーム練習で全否定したらどうなるか。もしかしたら、「自分のやってきたことは無駄だったのか」と感じて、練習そのものをやめてしまうかもしれない。
令和の指導者、保護者に求められるものとは?
福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐は以前、自身がプロ野球選手になれた理由をこう語ってくれた。
「たぶん、子どものころに野球にハマれたからだと思います」
子を持つ親ならばわかるだろうが、我が子に「親のやりたいことをやらせる」のは非常に難しい。そこに少しでも「強制」が生まれてしまうと、子どもはそれを敏感に察知するものだ。
その意味でも、選手の自主性を重んじながら、ヤル気を出させる方向へと導き、しっかりと見守ることが、令和の指導者には求められるのかもしれない。かなり難しいことではあるが、これは指導者だけでなく保護者にも言えることだ。
「ウチの子どもをどんな野球チームに入れたらいいですか?」
この質問の正解は分からない。ここに書いたメジャーリーガーのエピソードも、子どもたち全員にとっての最適解ではないかもしれない。
本当に大切なのは、子ども自身が夢中になれてハマれる環境かどうか。もちろん、保護者の目線で見て「このチームに入団させたい」と思うケースもあるだろう。ただ、そんなときもまずは一度、実際に子どもと一緒に練習を見学したり、体験入部するなどして、子どもの意見を尊重しながら見極めるほうがより良い選択ができるのではないだろうか?
少しでも多くの子どもが野球を楽しみ、野球にハマってくれれば……。この原稿が、その一助になればこれほどうれしいことはない。
<了>
[インタビュー]ダルビッシュ有が明かす教育論「息子がメジャーリーガーになるための教育をしている」
山本由伸の知られざる少年時代。背番号4の小柄な「どこにでもいる、普通の野球少年」が、球界のエースになるまで
吉田正尚の打撃は「小6の時点でほぼ完成」。中学時代の恩師が語る、市政まで動かした打撃センスとそのルーツ
なぜ指導者は大声で怒鳴りつけてしまうのか? 野球の育成年代に求められる「観察力」と「忍耐力」
大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持
2026.02.13Career -
WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏
2026.02.13Business -
新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」
2026.02.12Business -
「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断
2026.02.12Career -
女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割
2026.02.10Career -
なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性
2026.02.10Business -
技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方
2026.02.09Training -
ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ
2026.02.09Career -
「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟
2026.02.06Opinion -
中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代
2026.02.06Career -
守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏
2026.02.06Career -
広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係
2026.02.06Business
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟
2026.02.06Opinion -
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion -
「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地
2025.12.23Opinion -
「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実
2025.12.23Opinion -
なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋
2025.12.17Opinion -
中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”
2025.12.10Opinion -
『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏
2025.11.28Opinion