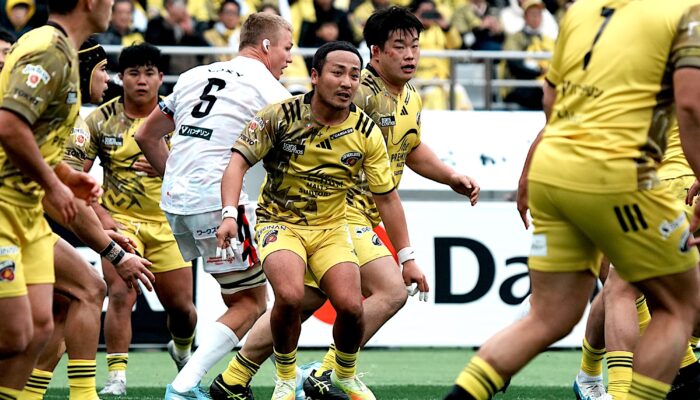育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」
サッカーの育成年代において、能力のある選手が上の年代へ飛び級するケースは、近年日本でも見られ始めている。飛び級した選手にとっては新たな成長の機会であり、誇らしくもあるだろう。一方で、飛び級が100パーセント成功への近道だと言い切ることもできない。世界的な“育成の雄”SCフライブルクで12年間育成アカデミーダイレクターを務めるアンドレアス・シュタイエルトは「それぞれの最適解を探すことが何より大切」だと話す。
(文・撮影=中野吉之伴)
子どもは成長したいと考え、大人は結果を出そうと焦る
「子どもたちはいつもすぐに成長したいと考えがちです。加えて周囲の大人が、すぐに結果を出そうと焦りがちです」
言葉の主はブンデスリーガ1部SCフライブルクで12年間育成アカデミーダイレクターを務めるアンドレアス・シュタイエルトだ。フライブルクはドイツ国内外において選手育成で長年高い評価を得ているクラブで、子どもたち個々に合わせた成長へ導くことに定評がある。
冒頭のコメントは「育成期に上の学年へ『飛び級』させる必要性や効果について質問した際に、最初にシュタイエルトが口にしたものだ。子どもたちの成長スピードや成長曲線はそれぞれ違う。サッカーを始めた時期も、取り組んでいる頻度も違う。カレンダー上の同年代と比べてスキルやフィジカルレベルで生じる差が大きくなりすぎてしまうと、1つ、2つ学年が上のチームでプレーさせるケースも少なくないかもしれない。
例えば日本代表MF堂安律はガンバ大阪ジュニアユース、ユース時代に上のカテゴリーでプレーし、本人はそれが自分にとってはとてもよかったと話している。シュタイエルトも飛び級がもたらすメリットがあることを肯定的に捉えている。
「年上の選手と一緒にプレーをして、競い合うことで、身体的に劣っている部分がある自分をどうやって克服するかを考え、戦略を練ることも重要です。ただ、子ども自身の発展・成長のためには、同じ学年でプレーして、その中で責任を持って先頭に立つことで学ぶこともとても大きいと考えています」 サッカーはスキルやフィジカルだけで構成されるスポーツではない。ゲームインテリジェンスや戦術理解度、さらには自己分析能力、自己改善能力、身体的・精神的負荷耐性能力、セルフモチベート能力、コミュニケーション能力なども非常に重要な要素である。さらには自分の力を発揮するためにはチームへのアプローチの仕方、チームでの自分のプレーの出し方、チームでの味方の良さを引き出すやり方を身につけることもとても大切なのだ。
「ポルディはあまりにも早く成長してしまった。でも…」
かつて元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキをU-12、U-13時代に指導していたギド・ミュラーに話を伺ったとき、早すぎる飛び級の弊害について、こんな警鐘を鳴らしていたことがある。
「ポルディはあまりにも早く成長してしまった。わずか16歳でトップチームデビューをして、19歳でキャプテンを務め、ドイツ代表デビューを果たし、23歳で代表キャップが70近くもある。メディアに祭り上げられて、みんなが彼の一挙手一投足に注目するようになってしまった。でも彼が1シーズンコンスタントに活躍をしたことがない事実をみんな知らないといけない。16歳のころには16歳のときにやるべきことがあるんだ」
カテゴリーを駆け上がるのが早ければ早いほうがいいわけではない。成長スピードが早過ぎてしまうと、ブレーキをかけるのも難しくなってしまう。 13歳でドルトムントのU-17カテゴリーでプレーし、16歳でトップチームデビューを飾ったFWユスファ・ムココ。彼は幼い頃から神童と呼ばれ、17歳で2022年FIFAワールドカップカタール大会でメンバー入りを果たして、日本代表戦で試合にも出場。ドイツサッカー界に希望をもたらす存在として大きな期待を寄せられていた。だが最近では度重なる負傷の影響もあって伸び悩み、フランスリーグのニースへレンタル移籍したものの、プレー機会をつかむことができずに苦しんでいる。先日はドイツ代表どころか、U-21代表からも招集されなかった。
レロイ・サネの苦悩と飛躍
U-23の選手がトップチームに加入する際にぶつかる壁についてシュタイエルトはこう話す。
「例えばU-23の選手がプロチームでトレーニングするときに大切なのは、どれほどのインテンシティでプレーしなければならないかを知り、その負荷に慣れるための努力をすることです。U-23もプロチームもトレーニングの量や頻度はほぼ同じ。一方でその強度には大きな違いがあります。欧州トップレベルでプレーしている選手は優れたプレーヤーであると同時に、優れたアスリートでもあります。U-23の選手たちはこの壁を乗り越える必要があるんです」
これはどのカテゴリーへの飛び級によっても生じる壁だ。選手を上のカテゴリーでプレーさせることで、より高いインテンシティへ順応することが要求される。それが選手にとって適切な刺激になることもあれば、重いプレッシャーや身体的な負担になってしまうことがある。育成年代で大事なのはより早くカテゴリーを駆け上がることではなく、選手個々にあった取り組みで確かな成長へとつなげることだ。
ドイツ代表MFレロイ・サネはシャルケのU-16時代ほとんど試合に出られない時期があった。当時のサネはまだ小柄でフィジカルコンタクトやインテンシティにまだついていけないところがあった。選手にとって試合に出られないのは焦りや不安につながりがち。だがシャルケの育成アカデミーではそんなサネに対して、どのような取り組みを今はすべきかを明確に提示し、時間をかけてじっくりと自分と向き合うようにアドバイスをしたという。
とある日のテストマッチで後半から途中出場を果たしたサネは、大柄な相手チームに対してフィジカルで圧倒されることなく、持ち味のスピードや巧みなスキルでゴールチャンスを量産。時はきたと確信したコーチングチームは、この日を境にスタメンで起用するようになった。それから2年後、U-19ながらトップチームデビューを果たしたサネはUEFAチャンピオンズリーグの舞台でレアル・マドリード相手に鮮烈なゴールを決めるなどその才能を発揮。トッププレーヤーへの階段を上り始めることができた。
堂安律は成功例。そのうえでどんな環境が望ましいのか?
シュタイエルトは育成に秘密の方程式があるわけではないと強調する。
「どんなことでもそうですが、ある何かが決定的に悪いわけではなく、また他方の何かが完全に良いわけでもないんです。時には両方の良さを合わせたものも重要かもしれません。絵を描くスタイルはさまざまで、あるプレーヤーに対してはこのように、また一方で別のプレーヤーに対してはあんなふうにと選手に応じてアプローチを変えて、それぞれの最適解を探すことが何より大切です」
選手の性格や特徴だってみんな違う。前述した堂安の場合は、「監督たちは僕のパーソナリティーをよく知っていたと思います」と当時について述懐してくれたことがある。
「僕が『自分はこのチームで王様だ』って感じてしまったら、ハードに取り組まないだろうという危機感が監督たちにあったと思います。年上のチームに入れて、『この中では下の選手なんだから、もっとハードにやらないといけない』という気持ちにさせてくれた。年上の先輩たちが僕よりも優れたプレーをしているのを目の当たりにしているから、そのおかげで僕は自分を見つめる時間がたくさんあった」
彼の持つ生粋の負けん気の強さや反骨精神はそうした環境がうまくプラスに働いた。そうした成功例だってもちろんある。でもシュタイエルトの言うとおり、そればかりがうまくいく方法だと思わないほうがいいのだろう。論理的なコミュニケーションや自主性をもった取り組み、状況に合わせた戦術判断などが日本の育成において課題なのだとしたら、それらと向き合えるにはどんな環境が望ましいのかを、選手個々のパーソナリティーの観点から現場で考えていかなければならない。
【連載前編】「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果
【連載中編】専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ
<了>
ユルゲン・クロップが警鐘鳴らす「育成環境の変化」。今の時代の子供達に足りない“理想のサッカー環境”とは
「育成で稼ぎたいのか?」ビッグクラブが陥る子供を潰す悪因 育成の最先端フライブルクに学ぶ“成長の哲学”
躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景
なぜサッカーの育成年代には“消えゆく神童”が多いのか――。橋本英郎が語る「努力し続ける才能」を引き出す方法
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持
2026.02.13Career -
WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏
2026.02.13Business -
新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」
2026.02.12Business -
「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断
2026.02.12Career -
女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割
2026.02.10Career -
なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性
2026.02.10Business -
技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方
2026.02.09Training -
ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ
2026.02.09Career -
「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟
2026.02.06Opinion -
中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代
2026.02.06Career -
守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏
2026.02.06Career -
広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係
2026.02.06Business
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方
2026.02.09Training -
スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体
2026.01.05Training -
「木の影から見守る」距離感がちょうどいい。名良橋晃と澤村公康が語る、親のスタンスと“我慢の指導法”
2025.12.24Training -
「伸びる選手」と「伸び悩む選手」の違いとは? 名良橋晃×澤村公康、専門家が語る『代表まで行く選手』の共通点
2025.12.24Training -
サッカー選手が19〜21歳で身につけるべき能力とは? “人材の宝庫”英国で活躍する日本人アナリストの考察
2025.12.10Training -
なぜプレミアリーグは優秀な若手選手が育つ? エバートン分析官が語る、個別育成プラン「IDP」の本質
2025.12.10Training -
107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学
2025.11.17Training -
「やりたいサッカー」だけでは勝てない。ペップ、ビエルサ、コルベラン…欧州4カ国で学んだ白石尚久の指導哲学
2025.10.17Training -
何事も「やらせすぎ」は才能を潰す。ドイツ地域クラブが実践する“子供が主役”のサッカー育成
2025.10.16Training -
“伝える”から“引き出す”へ。女子バスケ界の牽引者・宮澤夕貴が実践する「コーチング型リーダーシップ」
2025.09.05Training -
若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり
2025.08.22Training -
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training