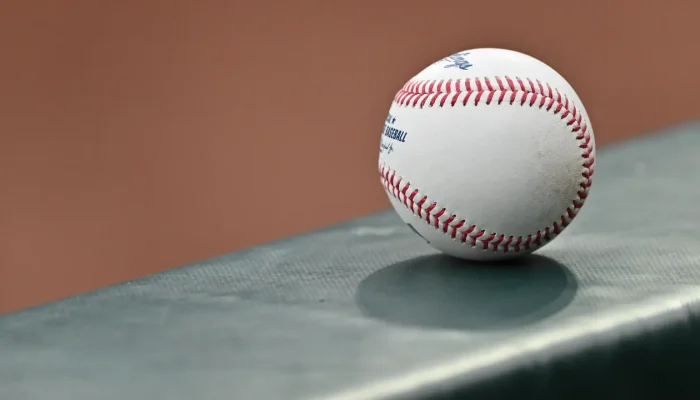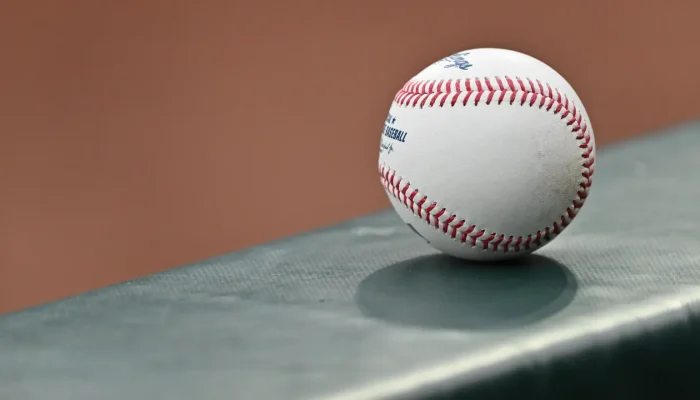空手界に横行する“理不尽”な判定に、月井隼南の魂の叫び。「判定に文句を言うな!」は正当な批判か?
現在フィリピン代表の空手家として活動する月井隼南。2021年の世界大会・KARATE1プレミアリーグでは金メダルを獲得した実力者だ。今年2月に行われたプレミアリーグで不可解なジャッジで敗れたことを受け、SNS上でその思いを率直にぶつけ、多くの議論を生んだ。「決まった判定に文句を言うな!」と批判を受けることを覚悟のうえで、なぜ彼女は声を上げたのか? 決して一時の怒りから生まれたものではない。これまで何度も理不尽なジャッジを受けてきた月井が心の底から発する、空手界の子どもたちの未来のためのメッセージだった。
(文・トップ写真=布施鋼治、本文写真提供=月井隼南)
弱小国フィリピン代表という環境的な要因
判定が覆らないことなんてよくわかっている。「私を優勝させてくれ」と声高に主張しているわけでもない。それでも、子どもたちの未来のために動かずにはいられない。
2022年2月、アラブ首長国連邦(UAE)で行われたKARATE1プレミアリーグ。フィリピン代表として組手の女子50kg級に出場した月井隼南はベネズエラの選手との3位決定戦で不可解なジャッジに遭遇した。
試合残り24秒、月井の右の突きによって対戦相手は明らかに効かされ、スリップダウンを喫している。対照的にベネズエラの選手の攻撃は月井の急所をしっかりと捉えていない。百歩譲っても、かすっている程度だ。しかし主審はベネズエラの選手の攻撃を有効と見なし、月井は想定外の敗北を喫した。
「そもそも伝統派なら直接打撃は反則なのでは?」という突っ込みがありそうだが、審判によっては加減された打撃ならばとってもらえる。さらに月井の立場は空手界では弱小国であるフィリピン代表という環境的な要因も大きく左右していた。
月井は「スキンタッチ(皮膚に当たるかどうかという絶妙な距離で当てること)だとポイントをとってもらえないことが多い」と吐露する。「だからKOやダウンにならない程度にしっかり当てるようにしています」。
かつて日本代表として活躍した月井が母の祖国であるフィリピン代表としてコートに上がるようになったのは2017年。その後世界ランキング100位以内に入って世界規模の大会に出られるようになったのは2019年になってからのことだ。なかなか勝ち上がることができない大会もあったので、月井は審判の傾向に注視するようになった。
「この審判はちゃんと見てくれるからスキンタッチでいいだろう」
「この審判はスキンタッチだととってくれないから、もう少し当てよう」
確実に勝つためのステップ・その1。いまでも微調整はずっと続けている。空手の世界では国によって扱いが変わるということが以前から指摘されている。フィリピンは戦前からプロボクシングが盛んなお国柄。あのマニー・パッキャオを輩出したことでも有名だが、空手の歴史は浅い。
「誰かにとってはたった一試合。でも選手にとっては…」
今回の一件について、月井は魂の叫びをSNSに上げた。
「誰かにとってはたった一試合。誰かにとってはたった一本の旗。誰かにとってはたった一つの技。でも選手にとっては身体も心も時間も、全てをそこに費やした大事な一つなんです。政治とかお金とかそんなの興味ないよこっちは。“強い人間が勝つ”それの何がいけないの?」
月井の訴えは胸にズシリと突き刺さった。それはそうだろう。筆者が知る限り、月井が長いキャリアの中で理不尽なジャッジを受けたのは一回や二回ではないのだから。
例えば、昨年6月に行われた東京五輪最終予選2回戦(オリンピックの階級では最軽量級となった-55kg級に出場)。試合はブルガリアの選手がリードしていたが、残り3秒というところで月井は左中段蹴りを決めた。映像で見る限り、明らかに入っているように見える。その刹那、彼女も決まったとアピールしたが、とってもらえなかった。
昨年10月にロシアで行われたプレミアリーグ2回戦でハンガリーの選手と当たったときも理不尽なジャッジに遭遇している。試合中、対戦相手は月井の頭を押さえつけてきた。明らかな反則だったが、主審は月井の失格負けを宣告した。試合後、大会の役員は来場していた月井の父・新さんの元を訪れ、「あれは審判のミスだ」と非を認めた。
月井は怒りのやり場を失った。「ミスを認めたからといって、何もなっていない。その審判が次に使われないということもなければ、ペナルティーを科せられるわけでもない」。

人数からすれば、十分とも思える審判の陣容だが…
空手の審判は1人の主審と4人の副審というのが基本。さらに審判のミスがないかどうかチェックする監査がいる。いわゆる柔道のジュリー(陪審)と同じ役割を果たす。簡単に説明すると、試合中に審判がミスを犯していないかどうかを確認する審判だ。さらにビデオレビューのジャッジが2人。人数からすれば、十分とも思える陣容である。
勝負は2人以上の副審が旗を上げたらOK。無理やり上げる必要はないが、その一方で同調というルールもある。自分の角度から見えなくても、他の審判の意見に同調してもいいというルールだ。
現役選手の中にはこの同調ルールに異論を唱える者が多いと聞く。仮に一人の副審から見えなかったとしても、同調すれば同じ一票になる。そうされることで、それまでの努力が水の泡となっては元も子もない。
では、そういうときに監査はどのような働きをするのか。残念ながらポイントについて物言いをする権限はない。試合時間が正確に遂行されているかどうか、あるいはペナルティーが宣告通りに与えられているかどうかをチェックするのが主な仕事であるからだ。
しかも、大きな大会になれば、4コートから8コートで試合が同時に行われる。決勝など1コートに神経を集中できる環境だと事情は違ってくるが、少人数で『どこで何が起こっているのか?』を逐一チェックするのは困難だ。
ビデオチェックもやり方を問題視する向きもある。会場に設置された巨大モニターに予選で審議が入った試合映像が映し出されることはほとんどない。映るとしても決勝など最後のほうの試合のみ。最後まで映し出されないこともある。試合映像はビデオチェックの審判が座る机に置かれたパソコンに映し出されるだけだというのだ。
しかもビデオは2方向からだけというケースも多いので、全方向からチェックできるわけではない。映像はコート全体で、そのときの技のアップが映し出されるわけではない。これでは、いくらビデオで確認しているとはいえ、フォローしているとはいえないのではないか。
誤審とともに歩んできたスポーツ界。空手も今こそ!
「だったら選手が団結して訴えれば?」という意見が出てくるかもしれないが、現実にはそれとは正反対のムーブメントもある。
月井が冒頭に記したベネズエラとの一戦の疑問をSNSにアップするとコメント欄には共感だけではなく、「一回くらい審判の犠牲になったくらいで文句を言うな」という反論も寄せられたというのだ。
もともとベネズエラは「形」の強豪国ながら、「組手」部門でのメダル獲得は久しぶりのことだった。帰国すれば、大きなニュースとして取り上げられるだろう。そうなれば、プロセスよりメダルをとったという事実だけが空手界ではクローズアップされる。勝てば官軍というわけだ。月井はそう理解した。そして、そういった意識が払拭(ふっしょく)されない限り、前には進めないとも思った。
誤解を恐れずにいえば、スポーツは誤審とともに歩んできた。
空手と同じ日本発祥の格闘技である柔道では、2000年のシドニー五輪100kg超級決勝で実現した篠原信一vsダビド・ドゥイエにおける誤審事件があまりにも有名だ。フランスのドゥイエの内股に対して篠原は内股すかしで切り返した。しかしながら、副審の一人は篠原の一本と判定したが、主審ともう一人の副審はドゥイエの有効と判断したため、このフランス人選手が金メダルを獲得したのだ。
この事件以降、国際柔道連盟ではその場での判定が困難なケースを想定してビデオ判定を導入し、判定を一層明確化するようになった。現在のジュリー制度のきっかけをつくったともいわれている。
判定は人が判断するものだから、時には過ちは避けられない。問題は、その過ちをどう正していくか。そこの部分を生かさないと、競技としての未来はない。
空手は東京五輪で初めて念願のオリンピック競技となったが、2024年のパリ五輪では除外されてしまった。オリンピック競技としての復帰のめどはまだ立っていない。柔道のように判定を明確化しようと動き出すのであれば、まさにいまこそ絶好のタイミングではないのか。
<了>
「根性って何だろう?」空手家・月井隼南が後悔する、ケガにつながる行き過ぎた根性論とは
「優先すべきは幸せ。根性の先に幸せは?」空手家・月井隼南が問う“根性で乗り切れ!”の是非
空手の未来に必要なのは「完全な数値化」?「イチローの理論」? 再び五輪種目指し求められる変革とは
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
ベテランの進化論。Bリーグ・川崎ブレイブサンダースを牽引する篠山竜青が、37歳でプレースタイルを変えた理由
2026.03.06Career -
欧米ビッグクラブ組が牽引する、なでしこジャパン。アジアカップで問われる優勝への三つの条件
2026.03.04Opinion -
なぜ張本美和・早田ひなペアは噛み合ったのか? 化学反応起こした「今の2人だけが出せる答え」
2026.03.02Opinion -
日本人のフィジカルは本当に弱いのか? 異端のトレーナー・西本が語る世界との違いと“勝機”
2026.03.02Training -
風間八宏のひざを支え、サンフレッチェを変えたトレーナーとの出会い「身体のことは西本さんに聞けばいい」
2026.03.02Career -
野球界の腰を支える革新的技術がサッカーの常識を変える。インナー型サポーターで「適度な圧迫」の新発想
2026.03.02Technology -
なぜ老舗マスクメーカーはMLB選手に愛される“ベルト”を生み出せた? 選手の声から生まれた新機軸ギアの物語
2026.03.02Business -
「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質
2026.03.02Opinion -
クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地
2026.02.27Career -
“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」
2026.02.26Education -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
欧米ビッグクラブ組が牽引する、なでしこジャパン。アジアカップで問われる優勝への三つの条件
2026.03.04Opinion -
なぜ張本美和・早田ひなペアは噛み合ったのか? 化学反応起こした「今の2人だけが出せる答え」
2026.03.02Opinion -
「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質
2026.03.02Opinion -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟
2026.02.06Opinion -
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion