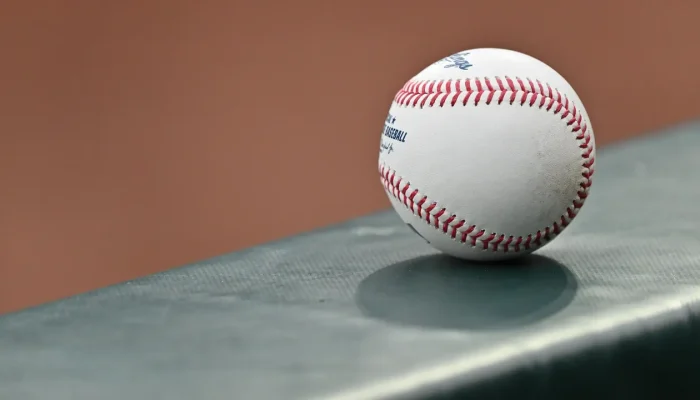デ・ゼルビが起こした革新と新規軸。ペップが「唯一のもの」と絶賛し、三笘薫を飛躍させた新時代のサッカースタイルを紐解く
2020年代のサッカーは、「デ・ゼルビ時代のブライトン」の以前と以後で区別されるようになるかもしれない。それほど2022-23シーズンにイタリア人指揮官ロベルト・デ・ゼルビが体現したスタイルはサッカー界に大きな影響をもたらした。今夏ドイツで行われた国際コーチ会議において、「ロベルト・デ・ゼルビがブライトンにもたらしたものとは?」とのテーマで分析された見解をもとに、デ・ゼルビサッカーを紐解く。
(文=中野吉之伴、写真=ロイター/アフロ)
ペップも「イノベーションを起こした」と絶賛するデ・ゼルビの存在
「サッカー界で彼こそが世界最高の監督だ」と多くの識者や同業者や選手が口をそろえる存在がマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラなら、そのペップが「そのサッカースタイルは唯一のもの。サッカー界に大きな影響をもたらし、イノベーションを起こした」と絶賛していたのが、元ブライトン監督のロベルト・デ・ゼルビ(現マルセイユ)だ。
2017-18シーズンからプレミアリーグに所属するブライトンに2022年9月に就任すると、2022-23シーズンに6位という大躍進に導いた。その薫陶を受けた日本代表FW三笘薫はプレミアリーグでも称賛を集める選手へと成長。アーセナル監督ミケル・アルテタも「まるで別のイメージでサッカーを見ている監督だ」とデ・ゼルビの手腕に驚きを隠さない。
今夏ヴュルツブルクで開催されたドイツサッカー連盟(DFB)とドイツプロコーチ連盟(BDFL)共催の国際コーチ会議で、DFB指導者育成インストラクターのマヌエル・シュリッツは「ロベルト・デ・ゼルビがブライトンにもたらしたものとは? サッカー界に継続的な効果をもたらすトリガーとなりえるのか?」というテーマでそのサッカーの分析を行っていた。
サッカーの試合を優位に進めるためには、どこでどのように相手に対して優位性を作れるのかがポイントになる。これまでは特に3つの優位性が挙げられていた。
1.質的優位性=選手個々のクオリティで違いを生み出す
2.数的優位性=特定のエリアで数的優位の状況を作る
3.位置的優位性=ゲームに好影響をもたらせる位置を取る
「いつ、どこで、誰が、どのようにこれらの優位性を生かしてプレーをするのかが、試合を左右する大事な要素として考えられてきましたし、これらの優位性は今後も大切なものとなるでしょう。でも試合の流れを変える優位性とはこの3つだけでしょうか? 今回4つ目として動的優位性を上げたいと思います」(シュリッツ)
なぜブライトンのGKは足裏でボールを止めるのか?
動的優位性とはなんだろう?
サッカーの試合では重要な局面で相手よりも動きのダイナミックさで上回ったほうが優位な状況を作れる。足を止めた状況やターンをして動き直してからダッシュを開始するよりも、助走をとったうえですでに勢いに乗った状態でボールを追ったほうが優位に立つことができる。シュリッツの説明が続く。
「サッカーの試合では相手よりもこの動的優位性で上回るために、いつ、どこで、どのようにギアをアップさせるのか。あるいはいつ、どこで、どのように相手のギアをダウン、あるいはストップさせてしまうのかが重要なファクターになります。この部分を意図的にどこまでチームとして共有できるかで、チームとしての成熟度には大きな差が出るといえます」
一例としてシュリッツはブライトンのビルドアップのシーンを動画で紹介し始めた。GKがボールを持つとペナルティエリアすぐ外までボールを運び、そこで足裏でボールを止めて様子をうかがっている。両隣りではセンターバックが同じように足を止めてスタンバイ。シュリッツがこのシーンを次のように強調していた。
「足裏でボールを止めるのはデメリットがあるとされています。動き直してパスに移るのに少しテンポが遅れるからです。優れた守備能力を持った選手はその隙を逃さずにボールを奪いに距離を一気に詰めてこようとします。デ・ゼルビはそこを逆に狙っているわけです。相手に食いつかせるのが狙いといえます」
最終ラインで奪われてしまっては元も子もないので、相手との距離感には細心の注意が払われている。相手FWが動き出した瞬間を逃さずにパスを受ける準備ができている味方へボールを渡して、相手のプレスをかいくぐるというやり方だ。かいくぐった後の一手も丁寧に準備がされている。
「この時、デ・ゼルビサッカーで大事なのは相手がプレスをかけてきているサイドへパスを逃がすという点です。相手チームは片方のサイドへのパスを出させないようなコース取りでボール保持者にプレッシャーをかけて、自分たちがボールを奪いやすい場所へ誘い込もうとします。でも逆にいうと、そこへは相手守備は配備されていないことを意味します。相手がボールを持つGKへのプレスへと動き出した瞬間、同サイドのセンターバックやボランチがパスをもらえる位置へすっとポジショニングを取り、そこからドリブルやパスですぐにボールを縦方向へ運んでしまうのです」(シュリッツ)
ダブルボランチがそろって近い距離にポジショニングを取り…
相手が誘い込みたいサイドの逆をとり、相手が力を注ごうとするベクトルの矢印を折る。一度ボールを止めるということは相手の動きも止めることになる。動的優位性がない状態を一度自分たちで作り出す。ブライトンの選手は0から一気に100へとギアを上げることが習慣づいており、相手が動き出してからギアを上げようとするより圧倒的に素早く次のプレーへと移行していく。だからわかっていてもなかなか止められないし、一気に自分たちの動的優位性を高めることができるというわけだ。
ギアを上げたらそれを高いスピードでキープするために、非常に精度の高いワンタッチパススキルが選手には求められる。相手が体勢を整え直す前に、一気にゴールまで強襲するのが一番効果的だからだ。
また三笘のようなドリブラーをサイドに配置する以上、彼らがその能力を最大限生かせる状況を作り出せたほうがいい。オフェンシブな選手が自分から仕掛けやすい状況とはどんなものだろう? 相手に密接マークを受けているよりも、ある程度スペースがある状況でボールをもらえたほうが仕掛けやすい。ではどうすればオフェンシブな選手がよりスペースがあって、ボールをもらえる状況を作れるのだろう? シュリッツはこのように分析する。
「ブライトンではダブルボランチが守備ラインに近いところで距離を短く保ちながらポジショニングを取ることが特徴的ですね。センターバックがボールを持った時には同サイドのボランチは離れてスペースを作り、逆サイドのボランチやインサイドハーフがボールをもらうために下りてくるというのが基本的なチーム戦術です。
デ・ゼルビサッカーではあえてダブルボランチがそろって近い距離にポジショニングを取ります。そうすることで相手守備を引き出し、オフェンスの選手が使えるスペースを広げるのが狙いなんです。ダブルボランチは相手のちょっとした動きに気を配りながら、少しの動き直しとコース取りでパス交換ができる状況を作り出し、そこから素早く前線の選手に正確で鋭いパスを展開します」
マルセイユでどのようなデ・ゼルビ・サッカーが見られるのか?
ポゼッションをしながらボールを展開するときに多くの指導者は「フリーの選手を探せ」というふうに選手にアプローチする。そして「シンプルにフリーの選手を生かして展開すれば、相手守備にズレが出てくる」と続ける。間違った話ではない。ただ、この「フリー」という概念は、どういう状況にいる選手を指すのかが、チーム内で共有できていないと思うような展開力にはつながらない。シュリッツは続ける。
「フリーというのはその選手の周りに相手がいない状況ということだけではなく、オープンな立ち位置をとれているかどうか、すなわち体をゴールへ向けた状況かどうか、そしてパスを通せる位置にいるかどうかが重要になります。フリーで、オープンな立ち位置で、パスを通せる選手を探しながら、ボールを回し、その選手がスムーズに推進力を入れられるように、意識的に前の足へとパスをつけることが徹底されていました。そうやって攻撃のスイッチを入れるのがデ・ゼルビ時代のブライトンは本当にうまかったですね」
そしてボールを奪われたら競り合いで圧倒的な積極性を見せながら即時奪回していく。三笘がブライトンで重要な役割を担っているのは、こうしたデ・ゼルビサッカーへの相性のよさと順応性の高さがあったからだろう。0から100へと一気にトップギアを入れることができるし、プレスバックでしっかりと自陣まで何度も戻ることができる。スペースへと飛び出すセンスに優れており、相手を引き連れて走ることで味方にビッグチャンスを提供することもできる。逆サイドで起点を作っているときにはタイミングよくゴール前へと侵入するので、決定機に絡む頻度もとても高い。
迎えた2023-24シーズンは相手チームからの研究も進み、出足を封じられたり、マンマーク気味のDFの裏をかいくぐられたりして順位も9位へと落とした。だがデ・ゼルビサッカーが脅威になったからこそ、そこから新たな対策が生まれたわけでもある。一つのトリガーとしてサッカー史に名を刻んだといっても過言ではないだろう。実際昨シーズン、ブンデスリーガで無敗優勝を果たしたシャビ・アロンソ監督率いるレバークーゼンは今回紹介したデ・ゼルビのブライトンのサッカーを参考にした仕掛けがいくつか見られた。
サッカーはこれからさらにどんなふうに進化していくのだろう。ブライトンの新監督には、プレミアリーグ史上最年少監督となった31歳のドイツ人指揮官、ファビアン・ヒュルツェラーが就任。そしてフランスに新天地を求めたデ・ゼルビはマルセイユでどのような取り組みを見せてくれるのだろう。興味は尽きない。
<了>
欧州サッカー「違いを生み出す選手」の定義とは? 最前線の分析に学ぶ“個の力”と、ボックス守備を破る選手の生み出し方
プレミアの“顔”三笘薫が背負う期待と懸念。日本代表で躍動も、ブライトンで見え始めた小さくない障壁
名門ビジャレアル、歴史の勉強から始まった「指導改革」。育成型クラブがぶち壊した“古くからの指導”
鎌田大地の新たな挑戦と現在地。日本代表で3ゴール関与も、クリスタル・パレスでは異質の存在「僕みたいな選手がいなかった」
「同じことを繰り返してる。堂安律とか田中碧とか」岡崎慎司が封印解いて語る“欧州で培った経験”の金言
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training -
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion -
日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」
2025.06.16Opinion -
野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」
2025.06.06Opinion -
冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは
2025.06.06Opinion -
なでしこジャパン2戦2敗の「前進」。南米王者との連敗で見えた“変革の現在地”
2025.06.05Opinion -
ラグビー・リーグワン2連覇はいかにして成し遂げられたのか? 東芝ブレイブルーパス東京、戴冠の裏にある成長の物語
2025.06.05Opinion -
SVリーグ初年度は成功だった? 「対戦数不均衡」などに疑問の声があがるも、満員の会場に感じる大きな変化
2025.06.02Opinion -
「打倒中国」が開花した世界卓球。なぜ戸上隼輔は世界戦で力を発揮できるようになったのか?
2025.06.02Opinion -
最強中国ペアから大金星! 混合ダブルスでメダル確定の吉村真晴・大藤沙月ペア。ベテランが示した卓球の魅力と奥深さ
2025.05.23Opinion