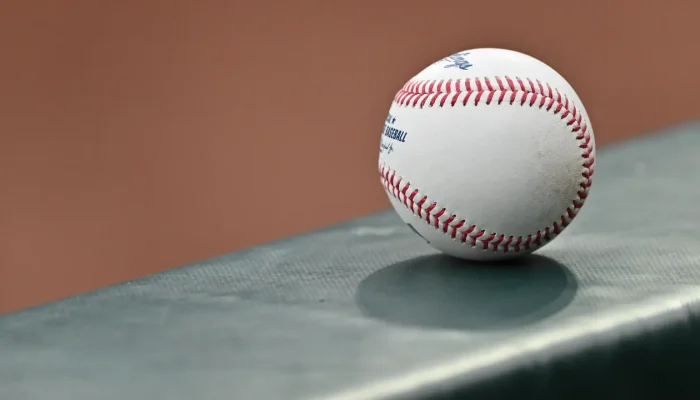ミシャ式、誕生秘話。「彼らが万全なら結果は違った」広島が誇る類い稀な“2人の存在”
森保一日本代表監督をはじめ、プロ・アマ問わず多くの指導者が多大な影響を受け続けている「ミシャ式」はいかにして生まれたのか? 2007年12月、「敗軍の将」としてサンフレッチェ広島のJ2降格を背負ったミハイロ・ペトロヴィッチ監督。迎えた2008シーズン、彼の革命が始まった。その後、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌でも多くのサッカーファンを魅了するペトロヴィッチ・サッカーの原点と、それを支えたクラブ・選手たちの物語。
(文=中野和也、写真=Getty Images)
【前編はこちら】ミシャ来日の知られざる情熱と決断 「オシムの腹心」はなぜ広島で“奇跡”を起こせたのか
「敗軍の将」ペトロヴィッチの進退
これがあの、ミハイロ・ペトロヴィッチなのか。
サンフレッチェ広島のJ2降格が決まった直後、記者会見に現れた「敗軍の将」は、信じられないほどに打ちひしがれていた。どんな大敗の後も堂々と記者と対峙し、「美しい死だった」と敗戦を振り返っていた男は、悄然と肩を落とし、記者の方向に向かって座ることすら、できなかった。
記者会見の冒頭、こういう言葉を彼は吐き出した。
「本当に申し訳ない。コメントするのは、正直難しい。32年のプロ生活の中で、もっとも大きな敗戦だった。広島はJ2に落ちるべきではなかった。サッカーとは、残酷なもの。サンフレッチェのファンタスティックなサポーターや選手、クラブに対して、申し訳ない。私は監督として、こうなった責任をとっていかないといけない。こういう結果にはなったが、私たちは素晴らしいチームだった」
それだけを言うのが、やっとだった。
質疑応答。
「ウェズレイを起用した理由は?」
「今日は、彼にとって広島での最後となる試合だった。素晴らしいゴールを決めてくれると期待して送り出した」
「森﨑和幸をボランチに起用したのは?」
「戸田和幸はコンディションが悪かった。カズ(森﨑和幸)を起用したのは、後ろから数的優位をつくるために、有効に働いてくれると思ったから」
ある記者がここでいら立ちを隠しきれずに質問した。
「進退については、どうお考えですか?」
ペトロヴィッチは「責任をとる」とは言ったが、「辞任する」とは一言も言っていない。その言葉がないと、記事の書きようがない。
意外とも言える発言が出てきたのは、その直後だ。
「私は監督として、ここ広島で素晴らしい時間が過ごせた。進退については、クラブから発表があるだろうし、私からは差し控えたい」
記者会見室はざわついた。ペトロヴィッチは、監督を続けるのか、それともやめるのか。
時間を空けずに、久保允誉社長(当時)が会見室に入室してきた。
「もう一度、フロントも含めた組織を立て直し、来季は全勝するつもりでチームをつくり、J1に戻ってきたいと思います」
息をつかせず、クラブのトップははっきりと告げた。
「私は……、私はみなさんからどう思われようが、ミシャと一緒にやっていきます」
久保社長は決然と決定事項を告げて、会見室を後にした。
情報を知ったサポーターは騒然となった。
「降格監督の続投は、許さない」
叫びはスタンドを覆った。
「お前がJ2に落としたんだ」
スタンドに居残ったサポーターが、社長に罵声を飛ばした。
当然、メディアもこの決断を猛烈に批判した。しかし、何をどういわれても、久保社長とクラブは、ペトロヴィッチとともにJ1復帰を目指す決定を覆しはしなかった。
広島の降格を告げるホイッスル
時間を降格決定の瞬間へと巻き戻す。
2007年12月8日、広島ビッグアーチ(現・エディオンスタジアム広島)。16時キックオフの決戦は、0-0のままで最終盤を迎えた時は照明に灯が入っていた。J1・J2入れ替え戦の初戦で1-2と敗れた広島ではあるが、アウェイゴールを奪ったことで、1-0の勝利をつかめば残留を勝ち取れた。しかし、なかなかゴールが奪えない。柏木陽介や佐藤寿人のシュートがバーに阻まれ、李漢宰や槙野智章が決定的なチャンスを迎えるも、ゴールできない。
アディショナルタイムに入り、広島は京都サンガF.C.陣内でFKを得た。キッカーは森﨑浩司。絶対的なキッカー。放り込んだ。跳ね返される。駒野友一が拾い、正確なパスでイリアン・ストヤノフへ。クロス。
一瞬、京都の守備がボールウオッチャーとなった。槙野が狙う。
オーバーヘッド。右ポストだ。でも、その近くに寿人がいた。
あーっ。
ため息。いつもならストライカーのところに転がってくるはずのボールは、ポストに当たった後、妙な回転がかかった。そのまま、ゴールラインを割る。
そこから間もなく、広島の降格を告げるホイッスルが鳴った。スタジアムは静まり返る。誰もが、現実を受け止められない。選手たちの多くは、身動きすらできなかった。北京五輪アジア最終予選最終節、日本を五輪に導く活躍を見せながら足を骨折し、入れ替え戦に出られなかった青山敏弘は号泣していた。
ペトロヴィッチは、ドレッシングルームに戻った。
このクラブを去らねばならない。それが監督としての身の処し方だ。
決意を固めたその時、スーツ姿の人物が飛び込んできた。
久保社長である。
経営者は監督よりも先に、言葉を発した。
「あなたを信頼している。来年も一緒に、仕事をしてほしい。広島の監督を続けてほしい。今回は、私が悪かった。もっとコミュニケーションをとるべきだった」
ペトロヴィッチは、その言葉が信じがたかった。
選手・監督として長くサッカー界で仕事をしてきたが、こんなことは、ありえない。
生涯最大の敗戦。生涯最悪の屈辱。
その最中にクラブの経営者からかけられた「信じている」という言葉は、辞任を決意していた男を翻意させるに十分だった。
「これほどの信頼に対し、他にどういう選択肢があるというのか。私は、この広島で仕事がしたい」
男は、泣いた。言葉が詰まった。「Yes」さえ、出てこない。
彼はただただ、久保社長の手を握った。それで、すべてが通じ合った。
ドレッシングルームには、落胆した選手たちが戻ってきた。久保社長は彼らに向かって、語りかけた。
「私とミシャを信じて、ついてきてくれないか」
この時、本当の意味でのペトロヴィッチの時代が始まったといっていい。
ずっと後になって、改めてこの日のことを聞いたことがある。その時もまた、熱情家すぎるセルビアの名将は瞳を潤ませたように、映った。
「あの年は私一人で指揮をとり、そして降格した。責任をとってやめる。それがノーマルだし、実際にそう考えていた。だからあの時は、ドレッシングルームで選手たちを待ち、別れの言葉を告げようとしていたんだ。その時、久保社長が来て、仕事を続けてほしいって言ってくれた。その時以来、私にとってのサンフレッチェ広島は特別なクラブになった」
周囲の信頼を得て、手にした「ミシャ式」の手応え
それにしてもどうして、久保社長はペトロヴィッチ続投を決めたのか。当時、決断した人は、その理由をこう説明してくれた。
「もちろん、監督や選手にも反省を促したい。でも(降格の)最大の責任は私にあるし、フロントにある。だから私は、代表権のない会長に退く決意もしました。その上で今回は、すべての選手に残留してほしいと思ったんです。もしペトロヴィッチ監督を交代させたとしたら、多くの選手は広島を出ていく。それは理屈ではなく、直感で感じました。選手たちは彼に対して、監督としてだけでなく父親に対するような想い、信頼を寄せていましたから」
実際、降格直後に森﨑和は「監督だけに責任を負わせるようであれば、僕も(移籍を)考えないといけない」と語っている。社長の心配には、リアリティがあった。
「もちろん、それだけが理由ではありません。彼の眼力と指導力を評価していたからこそ、私は(続投の)決断を下した。サッカーに対する信念、選手への愛情、失敗を人のせいにしない人間性。ペトロヴィッチ監督がそういう人だったからこそ、だったのです」
12月13日、筆者は降格後初めて、続投が決まった指揮官を取材した。彼はいつもどおり、胸襟を開いて言葉を吐き出してくれた。
「私自身、何人かの選手を信じすぎ、固執しすぎてしまったのかもしれない。その選手たちのクオリティを信じていましたが、それが逆の方向にいってしまった。若い選手たちも成長していたわけだから、彼らを思い切って使ってもよかった。もちろん、若い選手の起用は難しい。プレッシャーの強い中で使って、彼らの可能性をつぶすこともある。それでも、私の起用法を変えていれば……。そんな悔いはありますね」
敗因をすべて、自分に向けていた。
「責任のとり方はいろいろある。もしかしたら、私にとってはやめたほうが楽だったかもしれない」
それは間違いないだろう。事実、スタジアムではペトロヴィッチに対してコールや拍手はほとんど起きなくなった。その現実は、広島がJ1に復帰しても続いた。
「でも、私はこのクラブに残り、チャレンジすることで責任を果たしたい。サポーターの怒りは理解しているし、スポンサーも失望させてしまった。しかし、このクラブの資産である若くて才能に満ちた選手たちを育て、J1に復帰したい。そのために、私は頑張るしかないんです」
1年でJ1に復帰する。そのためには、戦力を整えないといけない。1年でのJ1復帰の条件は、戦力の充実という現実しかない。
ペトロヴィッチは選手たちと個別に面談し、チームに残留するように口説いた。それはレギュラーも、ベンチに座っている選手も関係ない。全員が必要だと彼は思っていた。それは、クラブも同様。J2に落ちたからといって、簡単に選手を放出する考えはなかった。移籍金満額のオファー以外は、交渉の余地はない、と。
契約満了が決まり、天皇杯を前にチームを去ったウェズレイを除いて、ペトロヴィッチは全員とじっくり話をした。
この年、ほとんど起用されなかった髙萩洋次郎は、指揮官に対して「チャンスをもらえなかったことが残念」と告げた。それに対してペトロヴィッチは「降格を回避するために経験のある選手を使わざるを得なかった」と言った。移籍も視野に入れていた髙萩は監督のまっすぐさを信頼し、広島に残る決断をしている。
李漢宰に対しては「今年は試合に出るメンバーを固定してしまった。自分も学ばないといけない。来季は右サイドでやってほしい。ただ、駒野がチームに残れば、君は2番手になる」。チャンスを与えられなかったことで指揮官へのモヤモヤを抱えていた李は、監督の正直さに心を打たれ、広島に残りたいとフロントに告げた。そしてこの2人は2008シーズン、主力としてチームをけん引することになる。
ペトロヴィッチの面談は、ほとんどの選手たちにポジティブな印象を残した。移籍したのは、日本代表の主力に近い存在である駒野と、若くて才能のあるDF吉弘充志、そしてFW田村祐基とGK河野直人。駒野以外の3人は出場機会を求めてのものであり、致し方ない。一方でFW久保竜彦の復帰にサポーターは興奮し、DF森脇良太とGK佐藤昭大も期限付き移籍先の愛媛から帰ってきた。ペトロヴィッチが「広島のダイヤモンド」と称した柏木陽介も「エンジン」と称賛した青山敏弘も、残留した。寿人をはじめ、森﨑兄弟(和幸と浩司)も、槙野も服部公太も、イリアン・ストヤノフも下田崇も。2008年に表現した広島の衝撃的なサッカー、その主役たちがしっかりとそろった。そして彼らとともに、ペトロヴィッチはいわゆる「ミシャ式」の手応えをつかみとる。
真骨頂である「疑似カウンター」の不発
物事が成就する前には必ず布石があり、基礎が打たれる。突然、何事かが芽生えるわけではない。その前に土壌を耕し、タネをまき、肥料も水もいる。
広島の場合はトレーニングだ。もともとテクニックタイプのタレントが多かったが、ペトロヴィッチは徹底して彼らの技術を鍛えるメニューを課した。ほぼすべてのトレーニングでボールを扱い、ボール回しのトレーニングに時間をかけた。ボールホルダーに対してたやすく圧力をかけられる状況をつくり、その中でも常に3つの選択肢を持てるように意識づけした。その結果として、GKからボールをつなぐスタイルを磨き上げることに成功した。
ただ、この技術やスタイルを勝利という歓喜につなげるための戦術的なベースが、なかなかできない。2008年当初もそうだった。
開幕から勝利を重ね、首位を走ってはいたが、警戒されてブロックをつくられると思うように打開できなくなった。第4節・水戸ホーリーホック戦、2人の退場者を出して大苦戦に陥り、森脇の終了間際の同点ゴールでかろうじて引き分け。次のFC岐阜戦でも、相手に主導権を渡してしまう厳しさの中で勝点1。第8節には、FWジョジマールがリベロのストヤノフを徹底マークするというヴァンフォーレ甲府の奇策に屈し、初黒星を喫した。続く第9節の対ロアッソ熊本戦も大苦戦。ポストに当たった熊本の2本のシュートが入っていたら、広島は連敗した可能性もあった。
個人能力がJ2では上位にあったからこそ、広島は開幕から首位にいられた。しかし、そんな状況は長く続かない。2003年、初のJ2で開幕から11戦負けなし・10連勝という快進撃を見せながら、夏場に失速した苦い経験がある。ペトロヴィッチは早急に、チーム戦術の機能性を高めないといけない。
第9節・熊本戦、「こんなサッカーではいずれ勝てなくなる」と森﨑和がミックスゾーンで言い放ったとおりの内容だったことは、指揮官に変化を決断させるに十分だった。中2日、時間はない。戦術的な擦り合わせもできない。しかし、彼の頭の中にはもう腹案ができていた。2トップから1トップへの変更。オーストリア第2の都市・グラーツの地で紙ナプキンの上で織田秀和強化部長(当時)に示したフォーメーションである。
2007年も何度か、この形は試されていた。しかし、それはウェズレイ不在の時に限られ、彼が出場停止やケガから戻ってくれば元の2トップに戻っていた。ウェズレイと寿人、2人の強烈なストライカーの両立を考えたからだ。しかしシーズン当初は爆発していた2人のコンビは、研究されるにつれてうまくはまらなくなった。
ペトロヴィッチの真骨頂である「疑似カウンター」、自陣でボールをキープして相手を引き込み、裏のスペースを空ける形がもっと機能するようになっていれば、2トップでもうまくいったのかもしれない。しかし、疑似カウンターを現実化するには、まだまだチームとしても個人としても、熟成が足りなかった。それに、2トップがはまった時の破壊力を、広島は2006年に経験しすぎた。J2降格の危機になればなるほど、その破壊力に頼ろうとしたのも無理はない。
ウェズレイが去った後も、指揮官は2トップを継続した。平繁龍一という若者の才能に期待をかけた。しかし、平繁のプレーは決して悪くはなかったが、チームとしてうまくいかない。「2トップだと、どうしても自分たちでスペースを消し合ってしまう。特にJ2ではその傾向が強い」と分析していた。
ケガから戻ってきた森﨑和幸という“才能”
「1トップ2シャドーをやるしかない」
ペトロヴィッチは、そう決めた。寿人を頂点にして、その後ろに髙萩と森﨑浩を据える。2人とも決定的なパスを出せる上に、裏に飛び出してゴールを陥れることもできる。
このシステムでの決定的なアイデアは、172cmと高さのない寿人を1トップに据えることだ。
当時の常識では、1トップには高さがあり、屈強な身体を持っているポストプレーヤーが最適と言われていた。2007年に初めて1トップをやった時、寿人は「世界でもっとも小柄な1トップですよね」と苦笑いした。
しかし、ペトロヴィッチの発想は違っていた。
「後ろからボールを動かしてコンビネーションを使って相手を引き出し、その上でスペースをつくる。そのわれわれの戦術における1トップに必要なのは、瞬間のスピードで相手の裏をとる能力だ。ヒサ(佐藤寿人)はプルアウェイ(一度引いて相手の視野から逃げてボールを呼び込むスキル)が得意だし、求める能力をもっている。彼が適任なんだよ」
ただ、監督の意図するシステムを機能させるには、ボランチに戦術的な意図を理解し、実行に移せる人材が必要だった。その役割を開幕当初は森﨑浩に担わせていたが、彼の本質はアタッカー。ゴール前でこそ力を発揮できるタイプだ。だが、やはり攻撃的な青山とのダブルボランチになると、本質的なチームプレーヤーである森﨑浩は若い青山をサポートする側に回り、個人の力を発揮しにくくなる。ボランチには、違うタイプの人材が必要だった。
ペトロヴィッチ・サッカーの神髄はパスだ。ほとんどのパスは足元でつながれ、ボールホルダーに対して最低3方向のパスコースを準備するために、選手たちは動く。アメリカンフットボールのクオーターバックが一気のロングパスでタッチダウンを狙うようなプレーは、ストヤノフと青山が狙っていたが、それは例外的。あくまで短いボールを中心にボール支配率を高めたいのが、指揮官の思惑だ。
ただ、そのパスも「つなぐだけ」では意味がない。何気ないパスをあえて出して「まき餌」に使ったり、あえて浮き球を使って相手のプレッシャーを無力化したり、無駄に見えるパス交換をやりながら呼吸を整える時間をつくったりしつつ、駆け引きの中から得点につながるプレーを演出する。本当の「無駄なパス」と「無駄に見えて意味のあるパス」は違う。その違いを出せるのは、本物の才能の持ち主だけだ。
ペトロヴィッチが戦術的変更を行う時間がまったくない中でもフォーメーションを変えることができたのは、1つにはチームのベースが整っていたこと。そしてもう1つは、森﨑和という才能がケガから戻ってきたこと。そこに尽きる。
森﨑和は、前述した特殊能力を持つ本物のMFである。ただ、広島のサッカーをずっと見ている人ですら、彼の才能に気づくのには時間がかかるものだ。寿人や李忠成をはじめ、多くの選手たちが口をそろえるのは「一緒にプレーしないと、本当のすごさはわからない」。だから彼は、Jリーグアウォーズでの表彰なども新人王と功労選手賞以外は、無縁だ。
ここは彼のタレントを語るのがテーマではない。ただ、ペトロヴィッチはこんな言葉を口にしている。
「戦術眼、予測、技術。あらゆるものが素晴らしいカズは、まさに『ドクトル・カズ』だ。彼は私の考えるサッカーを表現する指針になれる。素晴らしい人間性と頭脳を持っているカズの意見を参考にして、私はチームをつくっていった」
「ミシャ式」の肝である「可変システム」のスタート
2008年、第9節の熊本戦で股関節のケガから復帰した森﨑和は、チームだけでなく自身のパフォーマンスに対しても満足していなかった。続く第10節・徳島ヴォルティス戦の前日も控え組に回り、「自分の先発はないな」とも思っていた。
しかし試合当日の朝、ペトロヴィッチは彼をつかまえ「(先発で)いけるか」と問いただした。時間がない中で新フォーメーションを機能させるには、グラウンドで指揮官の意図を具体的に表現できる「ピッチ上の監督」を必要としたからだ。森﨑和の言葉であれば、寿人もストヤノフもうなずく。19歳の時、シドニー五輪代表候補だった藤本主税に「お前の言うことならみんな聞くんだから、もっと声を出せ」と言われたほど、こと戦術面に関する信頼は、群を抜いていた。
「いけます」
そして彼は、何かに突き動かされるように、行動した。いつもはやらない全選手への個別の声かけを実行に移し、「開始10分くらいは前からボールをとりにいこう」と指示した。
それは、ペトロヴィッチの指示ではなく、彼個人の判断だ。しかし監督のやりたいサッカーを実現するには、積極的な姿勢と自信を取り戻す必要があった。どちらも「ボールを握る」サッカーにおいては、不可欠なメンタル要素。主体的な意志を自分たちのものにしない限り、「ボールを動かしながら、相手を動かす」というペトロヴィッチ・サッカーは実現できない。だからこそ、森﨑和は「前から行こう」と言った。そしてその姿勢が、開始14分間で3得点、4-1の大勝という圧巻の結果となって、表現されたのだ。青山から寿人へのホットラインが本物になったという副産物も添えて。
森﨑和の才能は第13節・アビスパ福岡戦でも発揮された。この試合、福岡のリトバルスキー監督(当時)は、広島の起点となっていたリベロのストヤノフにFW黒部光昭をマンマークにつけた。それこそ、どんな時でも側から離れない徹底ぶり。
「カズ、ちょっと下がってサポートしてくれないか」
なかば助けを請う感じで、リベロはボランチに声をかけた。森﨑和が最終ラインに入ってみるとボールによく触れるし、スペースもある。やりやすい。でも、もっとやりやすくしたい。
「マキ、リョウタ、ちょっと開いてくれ」
ストッパーの槙野・森脇に森﨑和が声をかける。すると彼らは一気にタッチライン際まで広がり、攻撃的サイドバックのように前へと仕掛けた。その勢いに圧されるかのように、両ウイングバックはFWの位置まで上がった。フォーメーションを表現するならば4-1-5、いや2-3-5といっていい。
ストヤノフにしてみれば、緊急処置の依頼だったはずである。しかし森﨑和は「この形はいける」と現場で判断し、そのまま攻撃の時に最終ラインに下がるポジションどりを続けた。
これが「ミシャ式」の肝である「可変システム」のスタートである。
5トップで勝ち取ったシーズン「100ポイント」
このアイデアは、攻撃時に人数をかけやすくなり、カウンターへの対処もうまくいくという利点を生んだ。
当時、槙野はこんなこと語っている。
「ボールを失っても、カズさんとアオちゃん(青山敏弘)で守れる力がある。だから(ストッパーの)僕はボールを失っても次の攻撃のことを考えて、ポジションをとれるんです」
森﨑和が最終ラインに吸収されることで、青山も中盤でバランスを見る。なので、両サイドが攻撃に張り出したとしても、最も危険な中央には3枚が残ってリスクを見ているわけだ。その安心感があるから、5トップもストッパーも思い切って攻撃を仕掛けることができる。
この動きはまさに「システム」であり、多くの監督にとっての専権事項。選手の口出しを許さない指導者も少なくない。しかし、ペトロヴィッチという指揮官は、選手たちのアイデアを積極的に採用する。森﨑和の発想を指揮官は受け入れ、チームとして徹底した。その結果、広島の力は飛躍的な向上を果たす。データを見てみよう。
「可変システム」誕生前の11試合で、平均得点2、平均失点0.82平均勝点2.09。それなりに素晴らしい数字ではあるが、2位の湘南が平均得点1.82、3位の仙台が平均失点0.73と、数字そのもので圧倒しているわけではなく、勝点も湘南とは2ポイント差、仙台とは4ポイント差にすぎなかった。ところが可変システム採用後の31試合では 平均得点2.48、平均失点0.83、平均勝点2.48。特に第3クールの攻撃力はすさまじく、平均得点が3.14。第31節、甲府に0-2で敗れて以降の13試合で11勝2分。第32節の対福岡戦から第35節山形戦までの4試合で19得点2失点という数字を叩き出している。
J2が42試合制の時に広島が勝ち取ったこのシーズンの「100ポイント」を凌駕したのは、2014年の湘南(101ポイント)のみ。しかしその湘南も得点は86点にとどまり、広島の99得点には及ばない。2013年のガンバ大阪が99得点と並んだが、勝点は87ポイント。この年の広島がいかに強かったか、そして破壊力があったか。数字を見るだけでもわかる。
J1復帰以降の広島は、4位・7位・7位と悪くはないが優勝争いに絡むことができなかった。それは2009年オフに柏木、2010年オフには槙野やストヤノフと主力が移籍してしまったことも大きい。しかし、最大の要因は森﨑兄弟がいずれも病に倒れ、青山も負傷のために継続して試合に出られなかったことである。
このシステムは選手に技術・戦術能力の高さ、複雑な動きをコーディネーションできる頭脳を求めた。森﨑和は戦術をピッチ上で表現し、90分の中で微調整しながら試合という物語をつくる、まさにドクトル(博士)。森﨑浩は「3人目の動き」の達人であり、足元でつないだパスを神出鬼没の動きで裏をとったり、あるいは足元にボールを持って決定的な場面を演出、そして自分でゴールを決める。広島のMF史上、最も得点力のあるこの選手の重要性も、際立っている。ショートパスだけでなくロングボールで一気に局面を変えてチームのスパイスとなれる青山の存在は説明不要だろう。そして、そのつないだボールをゴールという果実につなげる寿人の特異な能力も、示しておく必要がある。もし、森﨑兄弟と青山がずっと試合に出られる状態であれば、広島の戦績はもちろん、彼の得点数もまた増幅していたはずだ。
「もしカズと浩司が万全であれば、特に2009年と2010年は違った結果になっただろう。でも、それが監督としての自分の宿命だったんだね」
2019年、ペトロヴィッチが森﨑和の引退に対し、寂しそうにつぶやいた言葉である。
日本代表監督・森保一の礎
「ミシャ式」誕生を側で見ていた男の一人に、2007年のシーズン途中から2009年までペトロヴィッチの下で指導者として働いていた森保一(現・日本代表監督)がいる。主たる仕事は若手の育成であったが、他にも分析を担当したり、仕事は多岐にわたった。その1年半、ペトロヴィッチの下で働いた日々は、彼にとって大きな財産になったという。
「ただボールをキープしろと言うだけでなく、そのために何をするべきか、どうやって相手を崩すか、そのアイデアを豊富に持って選手に伝えることができる。その能力は(これまで接してきた監督の中で)ミシャさんが一番だったと思います」
2012年、ペトロヴィッチの後を引き継いで広島の監督に就任した時の、森保の言葉である。
「多くの監督は、攻撃も守備もまず、相手のいない状況でやらせてコンビネーションや形を叩き込む。でもミシャさんは常に相手ありきで練習を進める。相手がこうきたら、こう逆をとれ、みたいな。そういう練習を実行するのは本当に難しい。また、ミシャさんは本当に選手をよく見ている。事前にメニューを組んでいても、選手の状態を見て急きょ変えることもしばしばでした。メニューそのものを変えたり、ルールを変更したり。そういうことを含めて、たくさんの引き出しを持つミシャさんのまねは難しい。だけど、ミシャさんに追いつきたいという気持ちは、ありましたね」
実際、監督就任のオファーを受けた時、「偉大なミシャさんの後を、俺でいいんだろうか」というプレッシャーはあったという。それでも「やりたい」という挑戦者としての気持ちが湧き上がり、現役時代から愛着のある広島の監督に就任したいと心に決めた。決定後、ペトロヴィッチに挨拶して激励を受けたことも、彼らしい。
「偉大なるミシャ」の後の広島を受け継いだ森保一は、子細にチームの戦力と状況を分析した結果、「変革」ではなく「継続」を選択し、その上で守備を調整して闘いに挑んだ。かつてストヤノフがにらみを利かしたリベロに、アルビレックス新潟時代からその能力を認めていた千葉和彦を抜てき。森﨑浩の病からの復帰を待ちつつ、シャドーにストライカータイプの石原直樹を起用した。ボランチには森﨑和と青山を固定。特に森﨑和に対しては「現場監督」と呼び、練習が終わるとチームの状況について長い時間をかけて言葉をかわすほど、絶対的な信頼を与えた。
2008年以来のフル稼働となる森﨑和と青山のダブルボランチが稼働したことで攻守に抜群の安定感を得た。それがチャンスの数の増大につながり、寿人の得点は前年の11得点から22得点に倍増。オーバートレーニング症候群から復活した森﨑浩も途中出場3得点を含む7得点(チーム2位)を記録して復活。ペトロヴィッチが手塩をかけたチームは、森保一という若き指揮官の冷静と情熱を得て、大輪の花を咲かせた。
森保監督時代の広島の栄光は、ペトロヴィッチという名指導者が選手たちとともにつくり上げたものが、ベースとなっている。城福浩監督が「広島の伝統」と表現する技術の高さと戦術能力は、一朝一夕に生まれたものではない。
2009年のJ1復帰以降、広島はリーグ優勝3回、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)出場権獲得5回、JリーグYBCルヴァンカップ決勝進出2回、ゼロックススーパーカップ優勝3回(2008年のJ2時代を含めると4回)、クラブワールドカップ3位入賞1回。常に降格の危機と背中合わせだったチームは、2017年を除いて常に10位以内をキープしている。決して潤沢な予算ではないにもかかわらず、だ。広島という土壌を耕した人はペトロヴィッチであり、彼への感謝は常に心の中にある。
まぎれもなくペトロヴィッチは“天才”である
2012年、浦和レッズの監督に就任したペトロヴィッチは、その前年に残留争いを演じたチームを立て直して3位を確保、5年振りのACL出場権獲得を成し遂げた。その後は常に優勝争いの主役となり、2015年はファーストステージ優勝。2016年には自身初、クラブとしては13年ぶりとなるルヴァンカップ制覇。チャンピオンシップでアウェイゴールの差で鹿島アントラーズに敗れたとはいえ、セカンドステージ優勝・年間勝点1位を獲得したことも忘れてはならない。
2018年からは北海道コンサドーレ札幌の監督に就任。前年の総得点39だったチームを一気に48点まで引き上げ、順位も史上最高位の4位にまで引き上げた。昨年は10位に終わったが、総得点は54点。札幌史上初となる3年連続J1残留を成し遂げるとともに、2部制になった1999年以降で初めて、J1で平均得点1.5の壁を破った。ルヴァンカップではクラブ史上初の決勝進出を果たした。
そういう数字的なことだけでなく、プロ・アマ問わず多くの指導者が彼の哲学に共鳴し、影響を受け続けていることも、確かである。「攻撃に人数をかける」「パスを連続的につないでコンビネーションで相手を崩す」「GKを含めたビルドアップ」などは、今や普通に行われていることだ。
彼を日本に招請した織田元広島社長は「ミシャは天才」と常々、口にしていた。スポーツやエンターテインメントの世界では「天才」という言葉がインフレーションを起こしていると常々感じているが、新しいやり方を切り開き、特異から通常に変える力を持っているということでいえば、まぎれもなくペトロヴィッチは天才である。その天才が構築したいと考えていた世界を、森﨑和というマエストロが具体的な調理を施すことによって「ミシャ式」は生まれた。その天才は、かつてこんな言葉を口にしていたことをご紹介して、締めくくりとしたい。
「いい時は、誰だって称賛してくれる。でも、降格のような最悪の事態に陥った時でも、結果ではなく仕事の内容を認めてくれる人は、そうはいない。成功した時には友人が増えるけれど、うまくいかなかった時には離れていくもの。そういう時にこそ、本当に大切な人が誰なのか、わかるんだ。人生とは、うまくいかない時から始まっていくものなんだよ」
<了>
【前編はこちら】ミシャ来日の知られざる情熱と決断 「オシムの腹心」はなぜ広島で“奇跡”を起こせたのか
浦和が示す、変革の覚悟。なぜ“ほぼ同じ陣容”で「ミシャの呪縛」から抜け出せたのか?
久保竜彦の“破天荒さと凄み”を生かせなかった日本の現実 戦友たちの証言で振り返る
この記事をシェア
KEYWORD
#COLUMNRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地
2026.02.27Career -
“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」
2026.02.26Education -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」
2026.02.20Career -
「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念
2026.02.20Career -
ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断
2026.02.20Career -
名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持
2026.02.13Career -
WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏
2026.02.13Business -
新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」
2026.02.12Business -
「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断
2026.02.12Career -
女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割
2026.02.10Career
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地
2026.02.27Career -
フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」
2026.02.20Career -
「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念
2026.02.20Career -
ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断
2026.02.20Career -
名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持
2026.02.13Career -
「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断
2026.02.12Career -
女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割
2026.02.10Career -
ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ
2026.02.09Career -
中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代
2026.02.06Career -
守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏
2026.02.06Career -
モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯
2026.01.30Career -
ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件
2026.01.23Career