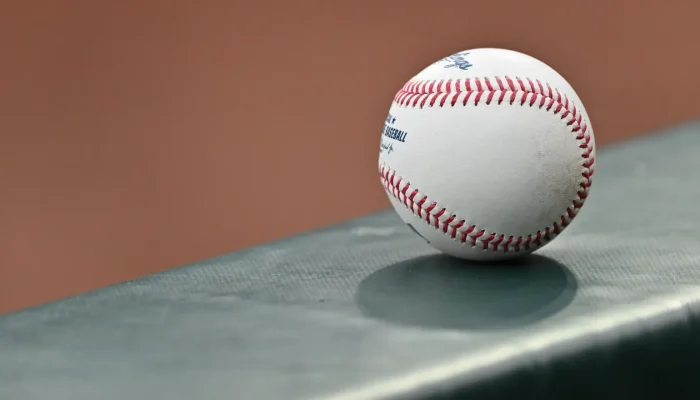インターハイ中止で問い直す「文武両道」 女子強豪校が取り組む「時間の有効活用」
全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会(インターハイ)の中止が決定し、高校女子サッカー部にとっては、冬に行われる全日本高等学校女子サッカー選手権大会(選手権)と並ぶ、高校生年代最高峰の舞台を一つ失うこととなった。各地の女子サッカー部はこの中止をどのように受け止め、現在をどのように過ごしているのか? 昨年のインターハイを制した東京・十文字高校の武岡イネス恵美子総監督と、京都随一の強豪・京都精華学園高校の越智健一郎監督の話に共通していたのは、オンラインを活用した指導の実践と、「学生としての本分」を重視した「文武両道」の精神だった。
(文=松原渓)
インターハイ中止がもたらすものは試練か、あるいは……
世界からサッカーの大会やイベントが失われてから、2カ月が経とうとしている。
入場する選手たちの精悍(せいかん)な表情、スタンドにはためく色とりどりの旗。ひんやりとしたスタンドの椅子の感触。見事な連係から生まれるスーパーゴール、熱狂に包まれるスタジアム。そんな記憶の風景を辿るたびに、スポーツをしたり、観戦したり、語り合える日常がいかに幸せなものだったかを思う。
世界を恐怖に陥れた新型コロナウイルス感染症は、社会のカタチを数カ月で変化させた。
国境を越えた移動や県境間の移動が制限され、SNSでは「ステイホーム」が合言葉になった。現在、世の中のコミュニケーションはWeb会議ツールやテレビ電話が主体となり、仕事はリモートワークが推奨されている。
サッカー界では各国のリーグや国際大会が相次いで中止になり、Jリーグもなでしこリーグも開幕時期の見直しを重ねている。スポーツは不要不急のものといわれてしまえばそれまでだが、日々、そうした目標に向かってトレーニングを積み重ねてきたアスリートたちの苦悩や切なさは想像するにあまりある。
4月26日に、全国高等学校体育連盟(高体連)は、8月に予定されていた全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会(インターハイ)の中止を決定した。中止は、1963年の第1回以来史上初めてのことだ。選手たちの悔しさはいかばかりだろうか。
インターハイ覇者・十文字高校、2連覇への思い
高校の女子サッカー部にとって高校日本一を決める同大会は、冬に行われる全日本高等学校女子サッカー選手権大会(選手権)と並ぶ、高校生年代最高峰の舞台だ。未来のスターを発掘しようと、なでしこリーグや女子サッカーの強豪大学の関係者も注目する。スポーツ推薦入学を目指している選手にとっては、アピールの場にもなる。
昨年のインターハイで初優勝した十文字高校は、今夏の大会に並々ならぬ意欲を燃やしていた高校の一つだ。丁寧なビルドアップや迫力のあるサイドアタックを武器とし、インターハイの前哨戦といわれる東京都高校女子サッカー新人戦大会では2連覇を達成した。
「去年の大会で初優勝して、今年はメンバー的にもさらにいいチームになると期待していた年代なんです。技術がある選手も多く、新人戦の段階ではボールを丁寧につなぐことを意識したチーム作りをしていました。今回のインターハイは選手たちも意識していたと思いますし、私もすごく期待していました。大会がなくなったことで非常にガッカリしています」
そう話すのは、同校に着任して20年目を迎え、現在は総監督として女子サッカー部を主に事務面でサポートする武岡イネス恵美子先生。1990年代に日興證券ドリームレディースで活躍し、女子日本代表の経歴も持つ。2016年度の選手権初優勝は顧問として見届けた。
十文字高校は、激戦区でもある関東圏で屈指の強豪校として名を馳せてきた。
その背景には、十文字中学・高校、十文字学園女子大学、社会人チームのFC十文字VENTUS(なでしこリーグ2部所属)、そしてジュニアユース(U-15)と幅広いカテゴリーを運営する「十文字フットボールクラブ」の存在があり、長いスパンで選手を育成できる。また、全天候型の人工芝グラウンドなど、環境面でも恵まれている。女子サッカー部は今年、新たに岸本昌蔵新監督を迎え、部員数は86名まで増えた。
受け継がれる「文武両道」の精神
通常、平日は朝7時過ぎから8時まで豊島区のグラウンドで朝練を行い、放課後は約1時間半~2時間の強度の高いトレーニングをこなしてきた。だが、全国の休校措置が発表された3月から練習は中止している。
そこで、トレーニング不足を補うために活用しているのが、Web会議ツールとして使われるようになった「Zoom」だ。
「1週間前(4月下旬)に、トレーナーさんを中心に、全員でZoomを使ったトレーニングを始めました。週3回、オンラインでできるトレーニングをして、それ以外の日は岸本監督とトレーナーがテーマを決めて『5km走』などのメニューを選手に伝えて、ケガ人には別メニューも考えています。選手たちは基本的に冬の選手権まで活動するので、現段階では目標を選手権に向けて切り替えています。それまで目標とする大会はないのですが、『今、できることをやろう』と。Zoomを通じて岸本監督が考えるサッカー観を選手たちと共有しながら、個別面談の回数を増やして、一人ひとりの声を聞けるようにしています」
監督が選手個々と向き合う時間が増えたことは、副産物ともいえる。それは今後、ピッチ上でも必ず生きてくるだろう。
十文字高校は女子サッカー部以外にも全国レベルの部活をいくつか持ち、同時に進学校としても知られている。「文武両道」は、女子サッカー部創設者であり、チームの礎を築いた石山隆之監督時代から受け継がれてきた精神だ。
武岡先生はこう語る。
「今年も、3年生の中心選手には学力面でも高い生徒が多いので、サッカーをできないのだったらしっかり勉強をやろう、と力を入れていますね。やはり、学生のベースは学業です。現役引退後にサッカー界で活躍している元選手もいますけれど、セカンドキャリアがおぼつかない間は、サッカーだけではなく勉強もしっかりしてほしい、と私からもよく話しています」
女子代表を経て引退後にセカンドキャリアとして教師への道をひらき、数多くの生徒たちの進路と向き合ってきた武岡先生の口調からは、サッカーができないこの時間を無駄に浪費することなく、将来への糧にしてほしいという願いが感じられた。
「離れていても一体感を大切に」京都精華のSNS活用法
一方、京都府随一の女子サッカー強豪校である京都精華学園高校の越智健一郎監督は、インターハイの中止をかなり前から予測していた。選手たちも早い段階でそのことを伝えられていたため、受けるショックも緩和されたようだ。
同校にはインターハイで引退を考えていた3年生もいる。そのために、最後に全員でできる試合や、宿泊を伴ったイベントも計画しているという。
同校の女子サッカー部はテクニックを重視したスタイルで知られているが、練習にダンスを取り入れたり、リフティングから試合で使えるスキルを学ぶなど、創造性豊かなトレーニングに定評がある。この時期、どのような方法を取り入れているのか聞いてみると、興味深い答えが返ってきた。
「毎日2回、朝の7時半と昼の13時半にLINEのビデオグループ通話をしています。強制ではないので、部員45人中30人前後ぐらいが参加する感じですね。狙いとしては、朝早く起きるという習慣を崩さず、生活習慣を整えることです。学校がないとつい夜更かしをしてしまうと思うので、朝7時半に起きて決まったストレッチを全員でしています。僕は遅れてきた子をいじったり(笑)、『今日は何するの? 俺は歩きに行くよ』と声をかけたり。そういう雑談も含めたコミュニケーションの場にもしています。午後は、ダンスを使ったトレーニングをみんなで3曲分やるんです。僕はそこには参加していません。選手たちだけのほうが会話が弾んだり、思ったことを言い合える時間だと思いますから」
これを毎日欠かさず行っているというから驚く。「僕らはコミュニケーションがすべてのチームだと思っていますから」と越智監督は力強く言い切る。監督が大枠となる習慣を作った上で、選手たちの自主性に任せる。画面上でもお互いに顔を見て励まし合ったり、監督やチームメートに「見られている」という意識が、継続するモチベーションにもなるのだろう。
越智監督は、オンラインで他校の監督たちと近況報告や情報交換もしているという。大会ではライバルだが、ピッチを離れればともに高校女子サッカー界を盛り上げる指導者仲間。このような厳しい状況下、オンラインでいつでもつながれるのは心強い。
「オール4とれなかったらアホちゃうか〜?」
一方、インターハイの中止が、大学のスポーツ推薦入学に影響することを嘆く風潮に対しては、思うところがあるという。
「サッカーの全国大会で結果を出せば、学業の成績はそこまで考慮せずに選手を取ってくれる強豪大学もあります。それで、引退(して勉強に専念)する選手がいる時期に、3年生の主力選手があまり勉強をしない、ということがあります。僕は両立が当たり前だと思っていますし、選手に対してはいつも冗談半分で『成績表がオール4とれなかったらアホちゃうか〜?』といういじり方をしているので、みんなも頑張ってくれています。主力選手には本当にオール4以上という子が多いですね。インターハイが中止になったことで、勉強も大事なんだよ、という当たり前のことをみんなが再認識できたらいいですね」
スポーツ推薦で大学に入った後に、学業面で周囲についていけずに苦労するケースは往々にしてある。「大学は学問を追求するところであり、スポーツで入って、スポーツだけするところではない」という越智監督の問題提起は、選手だけに投げかけられているものではないだろう。
代表で活躍する選手の中には、「首席で卒業した」とか「成績優秀だった」という選手もいる。そういう選手に共通しているのは、「努力する才能」の他に、「時間の使い方に長けている」ことかもしれない。越智監督は言う。
「時間の使い方がうまい子は、勉強もサッカーもうまく切り替えてできます。だから、今、彼女たちに特に求めているのは、時間の使い方を考えること。『最低3時間は勉強をやろうね』と励まし合ったりもしています。勉強以外にも、読書や料理、ジョギングやウォーキングなど、みんな楽しそうにいろんなことに取り組んでいるみたいです」
人生に彩りをもたらしてくれるスポーツを楽しむ日常が戻ってくる日のために、今をどう過ごすか。自宅で過ごす時間の使い方、そのアイデアと実行力がカギになりそうだ。
<了>
圧倒的なハッピーオーラ!京都精華「チャラい」監督、女子部員との卓越したコミュ力とは
[高校サッカー選手権 勝利数ランキング 都道府県対抗]昨年王者・青森山田の青森は2位。1位は??
岩渕真奈の好調は「腸腰筋」にあり。身体の専門家が施したトレーニング法とは?
この記事をシェア
KEYWORD
#COLUMNRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion -
世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地
2025.07.01Opinion -
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地
2025.06.28Career -
“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線
2025.06.27Business -
「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案
2025.06.25Business -
プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
2025.06.20Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」
2025.07.01Education -
スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験
2025.06.19Education -
なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意
2025.06.17Education -
部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方
2025.03.21Education -
高卒後2年でマンチェスター・シティへ。逆境は常に「今」。藤野あおばを支える思考力と言葉の力
2024.12.27Education -
女子サッカー育成年代の“基準”上げた20歳・藤野あおばの原点。心・技・体育んだ家族のサポート
2024.12.27Education -
「誰もが被害者にも加害者にもなる」ビジャレアル・佐伯夕利子氏に聞く、ハラスメント予防策
2024.12.20Education -
ハラスメントはなぜ起きる? 欧州で「罰ゲーム」はNG? 日本のスポーツ界が抱えるリスク要因とは
2024.12.19Education -
スポーツ界のハラスメント根絶へ! 各界の頭脳がアドバイザーに集結し、「検定」実施の真意とは
2024.12.18Education -
10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢
2024.08.19Education -
レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道
2024.08.06Education -
須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶
2024.08.06Education