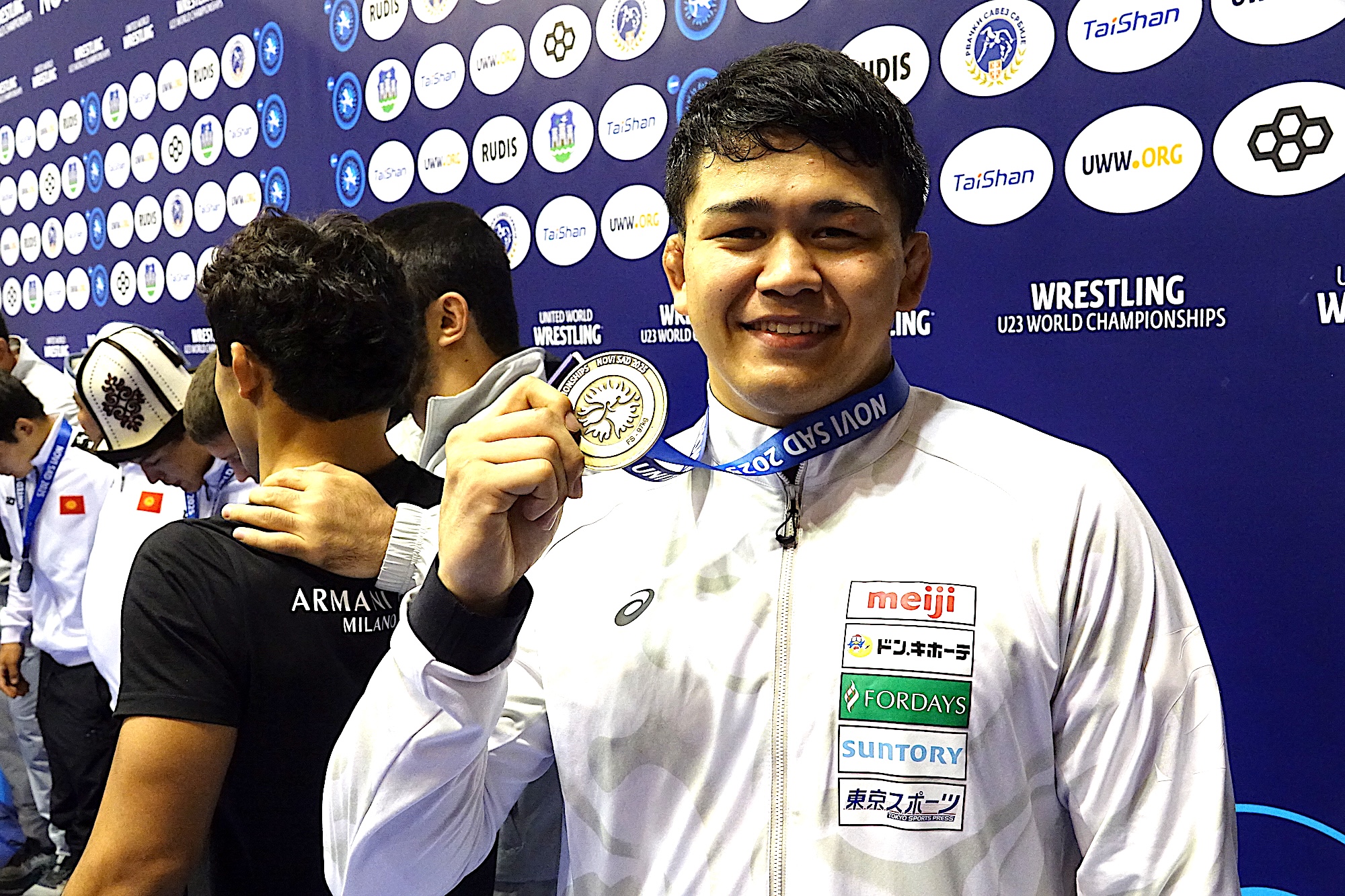リーグワン王者・BL東京に根付く、タレントを発掘し強化するサイクル。リーグ全勝・埼玉の人を育てる風土と仕組み
2023-24シーズンのジャパンラグビー・リーグワンが幕を閉じた。5月26日に国立競技場でおこなわれたプレーオフトーナメント決勝戦は、東芝ブレイブルーパス東京が埼玉パナソニックワイルドナイツに競り勝ち見事王者に輝いた。リーチ マイケルが主将を務めるブレイブルーパスと、現役ラストマッチとなった堀江翔太が牽引するワイルドナイツ。決勝戦に相応しい白熱した試合を見せてくれたこの2チームの強さの源を探っていくと、「タレントの発掘と育成に長けている」という共通項にたどり着く。
(文=向風見也、写真=森田直樹/アフロスポーツ)
ワイルドナイツの人を育てる風土と仕組み
2024年5月26日。東京の国立競技場へ5万人超のファンを集めたのは、ジャパンラグビー・リーグワンの決勝だ。
一昨季まで国内2連覇の埼玉パナソニックワイルドナイツがレギュラーシーズン全勝で乗り込んだのに対し、東芝ブレイブルーパス東京が24―20のスコアで返り討ち。旧トップリーグ時代以来14季ぶりの優勝を決めた。
ブレイブルーパスの猛者が接点に絡めば、ワイルドナイツの黒子がそれを懸命に引きはがした。転ばせた。ワイルドナイツが一枚岩の防御ラインを敷けば、ブレイブルーパスがアイデアと勇気の合わせ技で壁をこじ開けた。
かようなバトルの背景には、人を育てる風土と仕組みがあった。
まずワイルドナイツは、既定の枠をはみ出た個を一枚岩の組織に溶け合わせるのが得意だ。
日本代表としてワールドカップに4度出場して今季限りで引退の堀江翔太は、もともと帝京大学卒業後にニュージーランドへ挑んだ開拓者。最前列のフッカーでありながら優れた技巧、戦術眼を評され早々とワイルドナイツの主力となり、加入3季目の2010年度、旧トップリーグで初めてシーズンMVPとなった。
2013年に再び海外クラブへ渡って課題だったスクラムやラインアウトの課題を修正し、ワイルドナイツに帰れば自分たちに合う防御システムの編成に携わった。
2015年に出会った佐藤義人トレーナーとの肉体改造の効能を、後輩に伝え広めもした。高卒で入団の福井翔大、日本代表の正司令塔となる松田力也はその門下生だ。
プロになれなかった才能を日本に迎え入れ、引き上げ、個別に強化
堀江が前身の三洋電機時代から根付くカルチャーに育まれ、カルチャーを育む側に回るなか、クラブは未来の一流を海の向こうからも探すようになる。
今度の決勝でも先発したベン・ガンター、ジャック・コーネルセン、ディラン・ライリーのオーストラリア出身トリオは、いずれも当初は練習生だった。
「その時代のオーストラリアでは好選手が多かったものの、スーパーラグビー(国際リーグ)に挑めるのは毎年一定数だけ」とは、あるクラブ首脳。プロになりたくてもなれなかった才能を日本に迎え入れ、引き上げ、個別に強化した。
計画を主導したのはロビー・ディーンズ ヘッドコーチ、さらには3人と同郷の吉浦ケインS&Cコーチである。
当初タックルが不得手だったコーネルセンには、サイズアップを命じて堅陣を支える名黒子に昇華。パワフルなガンターには、栄養摂取に気を付けさせて機動力アップを求め、リーグ屈指のボールハンターに育てた。
大きくて速いのが魅力のライリーは、試合終盤までトップスピードを出すことを主眼に置いて鍛えた。堀江、稲垣啓太ら日本代表勢の揃う戦力とかみ合った末、リーグワンの初代トライ王となった。
ライリーは感謝する。
「ワイルドナイツには若手、国際経験の豊富な選手が、日本人と外国人の両方がいるといういい文化がある。チーム内でグループを作り、ベテランのアドバイスを若手が生かしています」
新人にはチームスタイルの「研修」を座学で実施
国内の新人へも、ワイルドナイツはチームスタイルの「研修」を施す。
この取り組みを始めたのは2019年頃からで、その年に着任した金澤篤、ホラニ龍コリニアシ両アシスタントコーチが攻防のシステムを座学で伝えた。
従前の「見て学べ」からの脱却。2020年度(2021年)のトップリーグ最終年度では竹山晃暉が、昨季のリーグワンでは長田智希が新人賞に輝いた。長田は述べる。
「最初は(チームに)慣れるのに必死でしたが、その取り組みがあったことで早く慣れることができた部分はあったかもしれないです」
ブレイブルーパスに根付く、タレントを見つけ、強くするサイクル
タレントを見つけ、強くするサイクルは、ブレイブルーパスにもある。
親会社の経営不振が大きく報じられたことで、新人獲得が困難になったのは2016年度以降。クラブも低迷期に突入する。
しかし、2017年に現役を退き採用担当となった望月雄太(現広報)は諦めなかった。
「上位チームのやるようなリクルートではなく、多くのチームを回り、もう一度、原点に立ち返って足で稼ごうと。多くのチームを回り、多くの人としゃべり、いろんなところに情報を取りに行きました。あとは、『東芝が必ず復活するのでぜひ……』という(大学関係者への)ロビー活動のようなことも、1年目は徹底的にやりました」
求める人物像は、選手同士の距離感が近いチームカラーに合い、かつ「タフ」な戦士。所属する組織のことが好きで、厳しい鍛錬に耐えうる資質があれば、その人は自然と伸びるという算段だ。望月の現役時代、スキルの高さで有望視された若手が短期間いただけで移籍してしまうことがあり、その経験も反映させる。
リクルート対象の大学生を年季の入ったクラブハウスや寮へ招き、「このへん、汚いけどごめんね」。謝りながらも、「その選手は、そういうのが大丈夫だと思って呼んでいる」。マッチングの肝は人間観察にある。
今回のプレーオフで活躍したフランカーの佐々木剛は、学生時代にブレイブルーパスの練習に混ざった時の印象が忘れられない。2011年度入部の森太志の名を挙げて言う。
「(当時のトップリーグでの)成績はよくはなかったのですが、皆が自分のチームへ自信を持っていた。練習を終えて皆で昼飯を食べていたら、太志さんは『もう、決まりでしょ? いいチームだから』って」
「東芝は家族感が強い。初めて練習を見に行った時…」
ブレイブルーパスにとって、佐々木の入った2020年度はターニングポイントとなった。
佐々木は大東文化大学の主将で、それぞれ京都産業大学、筑波大学、東海大学で主将だった伊藤鐘平、杉山優平、眞野泰地といった幹部候補生、早稲田大学きっての核弾頭である桑山淳生が加わった。
クラブが分社化した翌2021年度には、2020年度に大学日本一となる天理大学の小鍛治悠太と松永拓朗、明治大学の副将だった森勇登、帝京大学のニコラス・マクカランも門を叩いてきた。
この選手たちのうち、準決勝の直前に故障した伊藤以外はすべて決勝のメンバー入り。決勝トライまでのラストフェーズでは、森、松永、2018年度からの在籍で日本代表のジョネ・ナイカブラとつなぎ、最後は森がフィニッシュした。
さらに2022年度に仲間入りの木村星南、原田衛は、レギュラーシーズンのベストフィフティーンとなった。望月の集めた戦力が、最適化されていたのが伝わる。
そのバックグラウンドには、首脳陣の再編があった。創部史上初の外国人ヘッドコーチとしてトッド・ブラックアダーが招かれたのは2019年。現体制は段階的に招く専門コーチの指導、何より指揮官自身の積極的な若手起用、雰囲気作りで原石を磨いた。
流経大柏高校から大学を経ずに2021年にブレイブルーパスと契約した現日本代表のワーナー・ディアンズは、こう証言する。
「東芝は、僕が入る前から家族感が強い。初めて練習を見に行った時のチームミーティングはすごく印象に残っている。コーチに選手がいろんなことを言っていたのですが、厳しくはなく、楽な雰囲気。選手同士でもいろいろと話し合っている。ミーティングの前は音楽を流し、ダンスが好きな人は前に出てきて躍ってもいます」
優勝したブレイブルーパスでは、今季から花園近鉄ライナーズ前ヘッドコーチの水間良武が入閣していた。控え選手の育成が主業務の一つで、来季以降の戦力維持にも期待がかかる。主将のリーチ マイケルは補足する。
「いまの若手は試合に出たい、日本代表やインターナショナルレベルでプレーしたいという欲が強い。5年前の若手と比べても、練習量が多い。向上心を感じます」
かたやワイルドナイツでは、スパイクを脱ぐ堀江がピッチの上で「もう一回、チームを作り直さなあかんな」とポツリ。その言葉を耳にした坂手淳史主将は「そうですね」と頷いたという。心で捲土重来を誓う。
<了>
ラグビー姫野和樹が味わう苦境「各々違う方向へ努力してもチームは機能しない」。リーグワン4強の共通点とは?
「エディーさんも変わっている部分はあると思いたい」堀江翔太とリーチ マイケルが語る、新生ラグビー日本代表に抱く期待
9年ぶりエディー・ジョーンズ体制のラグビー日本代表。「若い選手達を発掘しないといけない」現状と未来図
大学生は下位チームを選ぶべき? ラグビー・リーグワン「アーリーエントリー」導入2年目の現実
ラグビー日本代表“控え組”の本音。「柱メンバー」の献身は矜持の発露…「選手層が課題」との総括に何を思う
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性
2026.01.09Career -
名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実
2026.01.09Career -
「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年
2026.01.09Career -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み
2026.01.07Education -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体
2026.01.05Training -
あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由
2025.12.26Career -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性
2026.01.09Career -
名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実
2026.01.09Career -
「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年
2026.01.09Career -
あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由
2025.12.26Career -
雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」
2025.12.25Career -
なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”
2025.12.24Career -
次世代ストライカーの最前線へ。松窪真心がNWSLで磨いた決定力と原点からの成長曲線
2025.12.23Career -
「まるで千手観音」レスリング97kg級で世界と渡り合う吉田アラシ、日本最重量級がロス五輪を制する可能性
2025.12.19Career -
NWSL最年少ハットトリックの裏側で芽生えた責任感。松窪真心が語る「勝たせる存在」への変化
2025.12.19Career -
「準備やプレーを背中で見せられる」結果に左右されず、チームを牽引するSR渋谷・田中大貴の矜持
2025.12.19Career -
「日本の重量級は世界で勝てない」レスリング界の常識を壊す男、吉田アラシ。21歳の逸材の現在地
2025.12.17Career