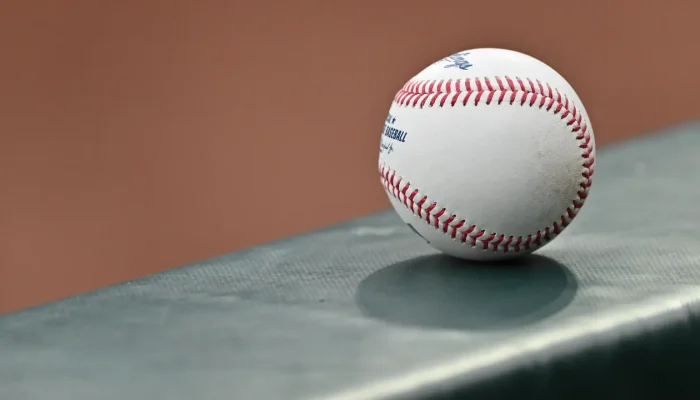なぜバドミントン日本代表は強くなったのか? 成果上げた朴柱奉ヘッドコーチの20年と新時代
バドミントン日本代表の朴柱奉(パク・ジュボン)ヘッドコーチが、2024年12月末に任期を終える。2004年の就任から約20年間、日本をバドミントンの強豪国へと押し上げた功績は計り知れない。現役時代、ダブルスの名選手として名を馳せ、母国である韓国、イングランド、マレーシアで指導者としての実績を積んだ朴ヘッドコーチに率いられたバドミントン日本代表はなぜ強くなったのか? 日本バドミントン界を変えた20年を振り返る。
(文=大塚一樹、写真=新華社/アフロ)
胸に刻まれた2006年5月3日の敗北
東京2020オリンピック以前に話を聞くことが多かったので、もしかしたら更新されているかもしれない。しかし、バドミントン日本代表の朴柱奉ヘッドコーチが「日本に来て一番悔しかった試合」として、昨日のことのように悔しさをにじませて語るのは決まって、2006年に日本で行われたトマス杯&ユーバー杯だった。
2006年、4月28日から5月7日まで日本の大型連休、ゴールデンウィークに合わせて行われた男女団体世界最強決定戦は、2004年に日本代表に就任した朴にとって、最初のマイルストーンでもあった。
男女とも仙台で行われた予選リーグを勝ち抜き、東京体育館に移動してのトーナメント初戦となる準々決勝、男子はインドネシアに、女子はオランダに敗れることになる。
「満員ですよ。東京体育館がバドミントンで満員というのは、日本ではそれまでになかったと聞きました。その満員のお客さんの期待に応えられなかった」
朴は、試合内容以前に日本選手のメンタリティーに一番のショックを受けたという。
「技術は当時から悪くなかったんです。特に女子はもっと上に行ける、行かなきゃいけないチームでした」
成長著しい小椋久美子/潮田玲子の“オグシオ”ペアを擁し、決勝進出を「最低限の目標」にしていた女子チームの敗戦は、選手たちにとっても誤算だった。しかし、「こんなはずじゃない」と憤りさえ感じていたのは、むしろ世界を知るコーチたちの方だった。
韓国代表としてバルセロナ五輪で男子ダブルスで金、アトランタではミックスダブルスで銀メダルを獲得している朴と、中国代表としてトマス杯優勝経験のある中島慶(中国名:丁其慶)女子ダブルスコーチには、地元の満員の声援を力にするどころか、そのプレッシャーに浮き足立ち、本来の実力を発揮できない選手たちのメンタリティーが理解できなかった。
「丁さん(中島コーチ)は、東京体育館のトイレから1時間出てこなかった。私もホテルに帰った後、食事もしないで寝ました。あれは日本に来てから一番ショックだったし、悔しい試合でした」 根本的なことを変えないとうまくいかない。変えられればうまくいく。ある意味では、課題が明らかになり、何をすべきかが明確になった。本格的な改革が始まったのはトマス杯&ユーバー杯の敗戦年の負け方、選手のメンタリティを目の当たりにしたことだったと朴はことあるごとに話していた。
朴柱奉の就任と改革の始まり
2004年8月に行われたアテネ五輪のバドミントン日本代表は、男女を通じてわずか1勝に終わった。
長い低迷から脱するために世界的指導者に教えを請うしかない。白羽の矢が立てられたのは、現役時代に男子ダブルス、混合ダブルスで一時代を築いた“ダブルスの神”であり、母国・韓国のほか、イングランド、マレーシアでも指導経験があり、イングランド、韓国ではナショナルチームの改革に成功したと評判の朴柱奉だった。
2004年11月に日本バドミントン協会と契約した朴は、日本特有の問題にすぐに気が付いたという。
当時の日本バドミントン界は、多くのアマチュアスポーツがそうであるように実業団主導型。企業がチームを持ち、選手は社員として業務に携わるのが通常。練習は企業保有の体育館で、日本代表は「呼ばれた時に行って帰ってくる場所」に過ぎなかった。
国際大会の3、4日前に集合して軽い調整を行い、その足で飛行機に乗り大会をこなす。
1992年にバドミントンがオリンピックの正式競技に採用されてからは、メダルへの注目度から日本代表としてプレーする意義は高まってきていたが、主体はあくまでも実業団チームにあった。
「日本はとにかく実業団中心。選手もコーチも実業団から派遣されているような状態で、スケジュールも国内の大会が優先されて組まれていました」
強化の時間もなかったが、日本代表が一堂に会して練習する場所の確保にも苦労した。当時の日本代表の練習会場は、公共、大学の体育館を借りるのが一般的だった。当然各体育館には優先すべき競技、チームがあるわけで、物理的にも十分な練習時間を確保するのは難しかった。 これらの諸問題については、ある意味で“外圧”である朴の「なぜ?」が効いた。遅々として進まない部分はあったが、自身も所属会社から派遣されている身である日本人コーチにはない「日本代表ファースト」を押し通す突進力が徐々に伝わった。実際にかなり早い段階で男女シングルス、男女ダブルスのコーチングスタッフ完全専任化が実現し、バドミントン日本代表が“実体化”していった。
どの国にも事情はある
強化のために正論を説いた朴だったが、日本の現状、実態を無視して強引に代表ファーストを推し進めたわけではなかった。実業団側に物を申す立場ではあったが、選手が日常的にフィーをもらっているのは会社であり、企業の支えなしに日本のバドミントンは発展していかないことは理解していた。
現役時代、“ダブルスの神様”と呼ばれていた朴は、ダブルスは選手の組み合わせにこそ妙があると思っていた。しかし、所属チームが異なるペアの組み合わせはタブーだった。
「それは諦めたよ」
変な習慣だとは思っていたようだが、ダブルスのペアの連動やプレーの呼吸は長い時間を掛けて熟成させていていくものだ。「ペアで1チーム」である以上、日本代表ペアが実業団チームでもそのまま同じチームで戦えた方がいい。実業団対抗の側面がある国内大会で所属企業が異なるペアが出場することはない以上、そこは諦めるしかなかった。
専用練習場NTCの誕生と強化合宿
朴を招聘した協会にも長期的な展望があった。
「なぜバドミントン日本代表は世界と戦えるようになったのか?」という問いの大きな理由の一つが、2008年1月から供用を開始したナショナルトレーニングセンター(NTC)の存在が挙げられる。
NTCに新設されたバドミントン専用体育館は、公式コートが10面取れる広さ。シャトルが識別しやすいように黒く塗られた天井など、完全バドミントン仕様の専用コートだが、施設の機能よりもうれしかったのが、日本代表のための常設の練習環境ができたことだった。
「これで6時半からでも練習ができる」
朴は日本代表の強化には、日本のトップレベルの選手が日本代表の一員である自覚とプライドを持ってプレーすることが不可欠だと考えていた。
文字通り日本を代表する選手が「日本代表」という一つのチームとして切磋琢磨することが、2006年のトマス杯、ユーバー杯で明らかになった期待を力に変えるメンタリティーの欠如、技術を勝利に結びつける戦い方を学ぶ近道だと考えた。 NTCという“日本代表を象徴する場”ができたことで、若手選手や全国の中高生をピックアップする合宿も定期的に行われるようになった。選手を探し、育て、日本代表の選手としてさらに磨き上げる。その活躍が競技人口の増加、さらなる有望選手の登場につながる好循環のループが始まっていた。
見えない壁を越えた北京、ロンドン、リオの成果
朴の指導の下、最初に結果を出したのは、2006年のアジア大会で銅メダル、2007年の世界選手権でも銅メダルを獲得した女子ダブルスのオグシオペアだった。期待と注目が集まった北京五輪では、小椋のケガなどもあり準々決勝敗退に終わったが、末綱聡子/前田美順の“スエマエ”ペアがベスト4進出を果たす。
「自分たちでもメダルに手が届くかも」
NTCのネットを挟んで共に練習する選手やペアが結果を出したことで、それまで日本の選手のストッパーになっていた心理的障壁、世界との見えない壁が壊れた。
2012年ロンドン五輪では藤井瑞希/垣岩令佳の“フジガキ”ペアが銀メダル、2016年リオデジャネイロ五輪では高橋礼華/松友美佐紀の“タカマツ”ペアがついに金メダルを獲得する。
女子ダブルスだけでなく、男子シングルスで後に世界ランキング1位に輝く桃田賢斗、女子シングルスの奥原希望、山口茜ら、代表ファースト定着後に見出され合宿で鍛えられた選手たちが世界トップクラスの成果を挙げた。 2014年には男子の国別対抗戦、各種競技のワールドカップに当たるトマス杯で初優勝を遂げる。女子のユーバー杯でも準優勝と、2006年の同大会から変化と進化を続けた日本代表は、バドミントン強国の仲間入りを果たすことになった。
コロナ禍で奪われた“最大の武器”
長期にわたって結果を残し、継続していた朴体制だったが、集大成となるはずだった東京五輪ではエース桃田が2回戦敗退、奥原、山口もベスト8、男女ダブルスに出場した4組もすべてベスト8で敗退。混合ダブルスの渡辺勇大/東野有紗“ワタガシ”ペアが唯一のメダルとなる銅メダルを獲得するに留まった。
桃田の複雑なキャリアについてはここでは言及しないが、東京での不振はコロナ禍によって代表合宿が大幅に制限されたことと無関係ではない。当時はNTCの利用にもさまざまな制約があり、思うような練習ができないどころか、日本代表選手が集まることさえままならない状態があった。
加えて、国際大会のカレンダーが大幅に狂う中、日本代表はオリンピック直前に行われた伝統の全英オープンで、奥原が金、男子ダブルスでは遠藤大由/渡辺勇大ペアが金、園田啓悟/嘉村健士ペアが銀、女子ダブルスでは永原和可那/松本麻佑の“ナガマツ”ペアが金、福島由紀/廣田彩花の“フクヒロ”ペアが銀、志田千陽/松山奈未の“シダマツ”ペアが銅メダル、さらに混合ダブルスでも“ワタガシ”ペアが金、金子祐樹/松友美佐紀ペアが銀と、圧倒的な強さを見せた。
この結果で地元開催のオリンピックへの期待はさらに高まることになったが、実は東京五輪前の国際大会には、“打倒日本”を掲げた中国、韓国勢が不在だった。エントリーを控え、国内で長期合宿を張り、オリンピックにピークを合わせる戦略を取った両国に、日本は期せずして分析用データを提供していたとも言える。 コロナ禍で世界ランキングが停止していたことも、日本選手の「見せかけのランキング」を押し上げ、世界との実力差を正確に測れないまま本番となったことも「まさか」の惨敗に反映された。
パリでも別の理由で再びの合宿不足
2024年パリ五輪でも、似たような問題が起きていた。コロナ禍はすっかり明けていたが、今度は2022年に起きたバドミントン協会職員による横領と隠蔽に端を発する強化費削減が大きく響いた。
パリに向けての日本代表合宿が「予算不足」により立て続けに中止になる異例の事態。
2大会続けて、日本の強みだった合宿による集中強化、代表内の競争による心身の調整が行えない状態に陥った。 結局、“シダマツ”、“ワタガシ”が銅メダルを獲得したものの東京のリベンジと意気込んで挑んだ日本代表としては悔しさが残る結果に終わった。
つなぐものと変えるもの 新時代に向かって
2024年、朴は20年続けた日本代表のヘッドコーチの職を辞すことを決めた。
朴が築いた「代表合宿を軸とした一体感」のモデルは大きな成果を挙げた。しかし、さまざまな不運はあったとはいえ、選手個々が世界ランキングの上位に名を連ね、国際大会で優勝を狙えるような強豪に成長した現在、すべてを日本代表、NTCのコートに集約するのは難しくなっていた。
実際に日本代表の合宿が長期にわたることに「もう少し環境の変化があってもいい」と語る選手もいた。選手が主体性を持って自分のチームを持ち、世界と戦う展開も今後あるかもしれない。
2025年からは、富岡高校で桃田や渡辺、東野を育てた大堀均がヘッドコーチに就任する。日本代表に大きな変化をもたらした朴は、引き続きアドバイザーとして日本代表をサポートするのは心強いが、日本のバドミントン界が次のステップに進むためには、20年の試行錯誤と改革を礎にそこで得た教訓を生かして、次の改革を始める必要がある。
予算繰りに今後も苦労しそうな点は懸念材料だが、協会の体制にも改革が進み、“見る競技”としてのバドミントンの価値を高める動きも活発化していくはずだ。
女子ダブルスコーチにロンドン五輪で銀メダルを獲得した“フジガキ”ペアの藤井瑞希が就任するなど、プレイヤーとして世界を知る世代が指導に当たることへの期待は大きい。
<了>
卓球が「年齢問わず活躍できるスポーツ」である理由。皇帝ティモ・ボル引退に思う、特殊な競技の持つ価値
非エリート街道から世界トップ100へ。18年のプロテニス選手生活に終止符、伊藤竜馬が刻んだ開拓者魂
「逃げるわけにはいかない」。桃田賢斗が“勝てない”苦悩の日々も、決して変わらぬ真摯な信念
「ダブルスは絶対できない」奥原希望が“勝てない”シングルスに拘り続けた理由とは
世界1位のスゴさが伝わらない…潮田玲子・池田信太郎が語る、日本バドミントン界の憂鬱
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
欧米ビッグクラブ組が牽引する、なでしこジャパン。アジアカップで問われる優勝への三つの条件
2026.03.04Opinion -
なぜ張本美和・早田ひなペアは噛み合ったのか? 化学反応起こした「今の2人だけが出せる答え」
2026.03.02Opinion -
日本人のフィジカルは本当に弱いのか? 異端のトレーナー・西本が語る世界との違いと“勝機”
2026.03.02Training -
風間八宏のひざを支え、サンフレッチェを変えたトレーナーとの出会い「身体のことは西本さんに聞けばいい」
2026.03.02Career -
野球界の腰を支える革新的技術がサッカーの常識を変える。インナー型サポーターで「適度な圧迫」の新発想
2026.03.02Technology -
なぜ老舗マスクメーカーはMLB選手に愛される“ベルト”を生み出せた? 選手の声から生まれた新機軸ギアの物語
2026.03.02Business -
「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質
2026.03.02Opinion -
クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地
2026.02.27Career -
“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」
2026.02.26Education -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」
2026.02.20Career
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
欧米ビッグクラブ組が牽引する、なでしこジャパン。アジアカップで問われる優勝への三つの条件
2026.03.04Opinion -
なぜ張本美和・早田ひなペアは噛み合ったのか? 化学反応起こした「今の2人だけが出せる答え」
2026.03.02Opinion -
「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質
2026.03.02Opinion -
三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化
2026.02.25Opinion -
日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成
2026.02.20Opinion -
「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟
2026.02.06Opinion -
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion