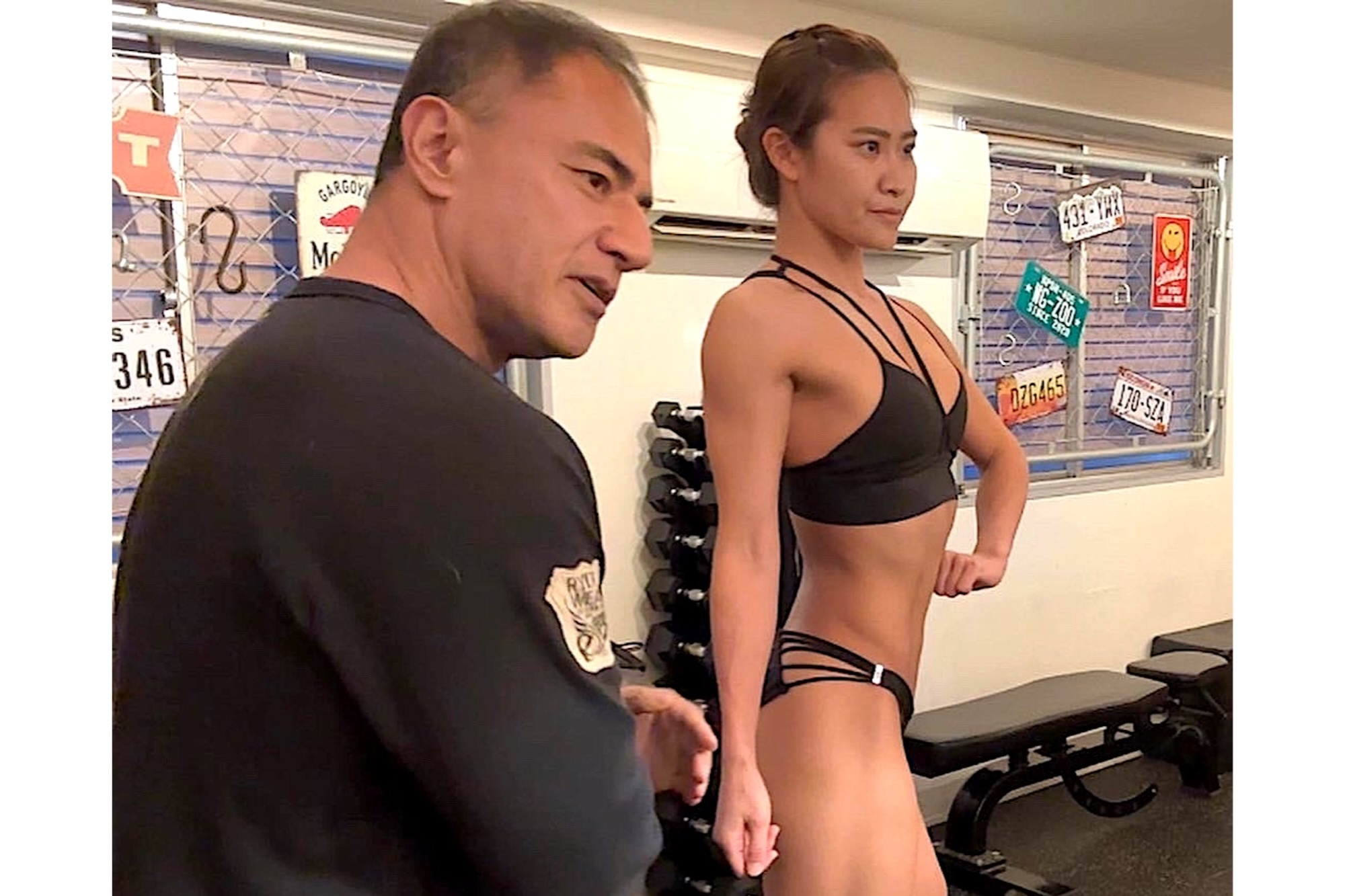騙されると決して勝てない「サーブの奥深さ」とは? 今さら聞けない卓球観戦の醍醐味
2月1日に行われた卓球の2020 ITTFワールドツアー・ドイツオープン準々決勝。世界ランク1位の樊振東を破ったドミトリ・オフチャロフの多彩なサーブを駆使した戦い方は「サーブ1球の威力」を強く感じさせるものだった。卓球のサーブにおける「下回転」と「横回転」の違いとは何か。そしてドイツの英雄、ティモ・ボル選手がその使い手として有名な「YGサーブ」とはどんなサーブを指すのか。そんな“サーブ”に関する基本を見ていこう。
(文=本島修司、写真=Getty Images)
サーブはその1球で勝負を決める「1球目攻撃」
卓球の試合を見るうえで、まず、最初に目に飛び込んでくるもの。それは、サーブだ。
テレビ中継の解説者も「ここで、このサーブを使えるかですね」という言い方をしたり、「このサーブをうまくレシーブすることができるかがポイントですね」という説明をする。そこでは、「下回転サーブ」「横回転サーブ」「YGサーブ」など、さまざまな言葉が飛び交う。卓球経験者でもない限り、試合中に少し説明されたくらいではちょっとわかりにくいものがある。
卓球は、サーブを出して“試合が始まる”。選手によってはサーブのことを、こんな言葉で表現する選手もいる。
「1球目攻撃」
サーブが得意な選手ほど、この言葉をよく使っている。そう、卓球におけるサーブとは、その1球で勝負を決めてしまえるほど「威力」があるボールなのだ。
例えばバドミントンの場合、「サーブ一発で終わる」というシーンを頻繁には見かけないと思う。一方、テニスではパワーのある豪速球でサーブから打ち抜くシーンがけっこうある。バドミントンのサーブは下から出し、テニスのサーブは上から大きく振りかぶって出すため、テニスはいきなり相手のコートにスマッシュのような速度で“打ち込む”ことができるからだ。
しかし、卓球の場合、テニスともバドミントンとも様相が異なる。卓球のサーブは少し別モノなのだ。それは、まず「自分の手前の台でワンバウンドさせなければいけない」というルールがあること。そして、他競技に比べてより「強烈な回転で勝負する」という一面があること。
この2つの要素が混ざり合い、1球目から豪速球を相手に叩き込むことはできないが、回転量と「切り方を変える」変化で多彩な攻撃を仕掛けることができるという特徴がある。つまり、サーブのことを「1球目攻撃」を呼ぶような選手の多くは、「ものすごい回転をかけることができる」か、もしくは「別な回転をかけたように見せかけるサーブの切り方」ができるということになる。
「レシーブが一番苦手」という選手が山ほどいる理由
卓球において「あなたの一番の課題は何ですか?」と聞かれ、「レシーブ」と答える選手は多い。
レシーブとは、サーブを取ること。プレー開始から「2球目」を指す。レシーブが苦手ということは、単純に「回転が強いサーブを取れない」とか、「相手のサーブの切り方のフォームにだまされやすい」ということになる。
日本卓球界の伝説的存在である荻村伊智朗は、「卓球はチェスをしながら100m走をしているようなものだ」という名言を生み出している。プレーが始まる一瞬の静寂からの、「サーブの切り方と回転で相手をだます」⇔「レシーバーはだまされないぞと身構える」という攻防は、心理戦の要素もあり、まさに頭と体を両方使っている瞬間だ。
「試合の中で、相手が取れないサーブを1つ持っていたら、勝ち」
こんなことを言う指導者もいる。
これがそれほど大げさな言い回しではなく、卓球では「あのサーブ1本が取れないせいで勝てなかった」と試合後に口にするシーンが多い。相手が取れないサーブが1本あるということは、すべてそのサーブを中心に組み立てていけばよく、かなり有利に試合を運ぶことができる。
では、卓球のサーブの回転にはどんな種類があるのだろうか。
「下回転サーブ」と「横回転サーブ」の違い
サーブに、意図的に強く回転をかけることを、「サーブを切る」と言う。逆に、意図的に切らない、ほぼ無回転のサーブのことを「ナックル」と言う。
では「切った」回転にはどんな種類があるか。これは、大きく分けると2種類ある。1つ目は「下回転」。2つ目は「横回転」だ。その中間として「斜め下回転」、横回転をさらに縦に切ったものとして「上横回転」などもあるが、大まかに言うと「切ったサーブ」とは「下回転系」と「横回転系」。この2つに分かれる。
下回転サーブは、ボールの真下を鋭くこすって回転をかける。例えば、この「切れた下回転サーブ」を、もし普段卓球をまったくやらない人が触れるとどうなるかというと、ボールは下に落ちる。ネットミスになる。
それに対し、横回転サーブは、ボールの横側をこする。切れた横回転サーブに普通にラケットを当ててしまうと、真横に大きく跳ね上がってしまい、台に入れることはできない。こちらはオーバーミスになる。
「斜め下回転サーブ」は、感覚的には下回転サーブに近く、基本的には下に落ちる。やや斜め下に落ちるという感じになる。「縦横回転サーブ」は、真横ではなく上に飛ぶが、触った瞬間に跳ね上がるような感覚もあり、横回転に近いものがある。
つまり、回転の強いサーブとは、真下や斜め下に落ちる「下系」か、横や上に飛ぶ「横系」の2つに分かれていて、サーバーとレシーバーが、この2種類をベースに“化かし合い”をしている、という視点で試合を見てほしい。
印象的だったのは、2015年のITTFワールドツアー・ジャパンオープン、男子シングス決勝。世界ナンバーワンとも言われるサーブの名手である、日本の吉村真春選手は、中国の世界ランキング2位(当時)、許昕選手相手に横回転系と下回転型のサーブの使い分けを展開。1セット目から許選手のレシーブをかき乱している。斜め下回転は下へ、縦横回転系は上へ飛ぶシーンが多い。
「どうしても相手のサーブが取れていない」という試合が展開されている時は、サーバー側がサーブを出す時に「完璧なマジシャン」と化しているということだ。レシーバーは、一度ハマってしまった手品があれば、タネと仕掛けを見破れなければ、その試合に勝つことはできない。
2020 ITTFワールドツアー・ドイツオープン。ドイツの名手、ドミトリ・オフチャロフ選手が、世界ランク1位(当時)の中国の樊振東選手に勝った試合などは、「サーブ1球の威力」を感じる試合だ。オフチャロフ選手は、しゃがみ込みサーブや、代名詞となっている静かな構えから強烈に切るバックサーブを組み合わせながら、横回転を中心に、スピードの強弱もつけている。世界トップクラスの回転量のサーブを有効に使い切ったオフチャロフ選手は、最後まで有利に試合を進めて、勝利を手にした。
ドイツの英雄ボルが操るYGサーブとは何か
手品のように出すため、回転を見破られないように出すために、実際に選手たちはどのような“仕掛け”を施しているのか。回転を見破られないために、選手たちが具体的にやっていることには、次のようなものがある。
・切る瞬間まで、ラケットの角度を違う方向に向けている
・切った後に、フォロースルーを変える
・同じ回転のサーブを、あえてまったく違う体の動きをつけて出す
・同じ回転で「スピード」を変える
・同じ回転で「長さ」を変える
そして近年、「ヤングジェネレーションサーブ」というものが登場した。通称「YGサーブ」。これは、「逆の方向から切るサーブ」だ。普通サーブというのは、体の外側から内側へ切り込むようにして、回転をかける。しかし、逆側から、つまり体側から外側に向かって切るのがYGサーブとなる。
ドイツの英雄、ティモ・ボル選手は、YGサーブの使い手として有名だ。横回転系が強く、サーブ一発で決まるシーン、相手がレシーブを浮かしてしまうシーンなどを見ると、圧倒的な回転量と、回転を見抜かれないフォームのすごさが、見ているこちら側にもヒシヒシと伝わってくる。
2019世界卓球選手権大会・男子シングル3回戦。ボル選手と日本の森薗政崇選手が対戦した試合も、YGサーブが何度も使われていた。この試合での、ボル選手のコンパクトなフォームで切るYGサーブは、見ていてため息が出てしまうほどの強烈な回転量を感じさせる。ダブルスの世界的な名手である森薗選手のレシ-ブをもってしても、あまりの切れ味の鋭さに、真上にオーバーミスになってしまうシーンがあるほど。まさに、世界最高峰の切れ味のサーブだ。
また、この試合で興味深いのは、森薗選手がサーブに入る前の動作で「サーブの素振り」をしているのだが、その素振りが「YGサーブの素振り」という点。実際に出すか出さないかは別としても、まるで「サーブからこの切り方で仕掛けていくぞ」という雰囲気で、強敵のボル選手に挑んでいる。
この「逆に切るパターン」であるYGサーブが定着してから、卓球におけるサーブで相手を惑わす戦術の幅は格段に広がった。フォアサーブ、バックサーブ、しゃがみ込みサーブ。これだけでも多彩な切り方があるうえに、逆から切るパターンも想定しなくてはいけなくなった。
いずれにしても、観戦する側も、実際に受けるレシーバーも、着目しなければいけないのはサーブを出す選手の“切る瞬間”だ。サーブを切る瞬間、どの角度でラケットに当たっているか。
「横系なのか? 下系なのか?」
それさえわかれば、この試合では下回転系をベースに組み立てていく選手なんだなと見たり、横回転系一発で常にサービスエースを狙っているんだなと見たり、卓球の見方が、より一層深く面白いものになっていくはずだ。
<了>
なぜ平野美宇はジュニア出澤杏佳にあっさり敗れたのか? 異彩放つ「異質ラバー」の秘密
美誠&水谷ペアが圧倒的に強い理由 卓球、混合ダブルス独特の「速さ」と「早さ」
伊藤美誠の完封勝利が明らかにした「暗黙のルール」の終焉。発祥の地・中国世論を動かした識者の見解
この記事をシェア
KEYWORD
#COLUMNRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」
2025.07.18Opinion -
なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある
2025.07.18Opinion -
ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地
2025.07.16Career -
ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し
2025.07.16Opinion -
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training -
福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性
2025.07.09Technology -
J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質
2025.07.04Opinion -
ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略
2025.07.04Business -
大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談
2025.07.03Business -
異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観
2025.07.02Business -
「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?
2025.07.02Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?
2025.07.14Training -
なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」
2025.07.14Training -
コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”
2025.05.23Training -
「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド
2025.04.21Training -
減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法
2025.04.18Training -
痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり
2025.04.16Training -
躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景
2025.04.04Training -
育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」
2025.04.04Training -
専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ
2025.04.02Training -
海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?
2025.03.31Training -
「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果
2025.03.28Training -
Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード
2025.03.03Training