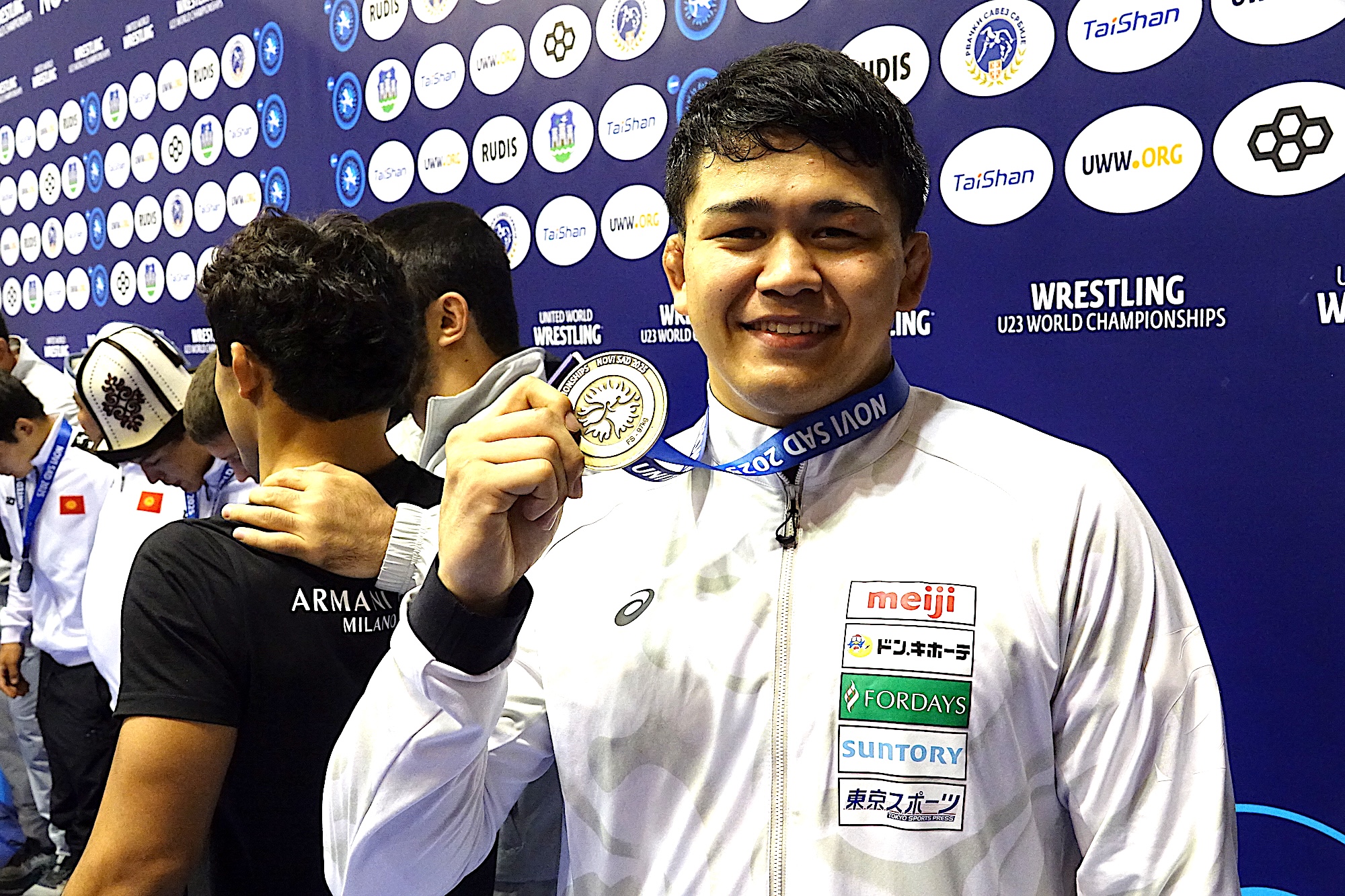「リーダー不在だった」との厳しい言葉も。廣瀬俊朗と宮本慎也が語るキャプテンの重圧と苦悩“自分色でいい”
プロ野球選手として長く活躍し、アテネ、北京の両オリンピックで野球日本代表のキャプテンを務めた宮本慎也。東芝ブレイブルーパスでキャプテンとして日本一を経験し、ラグビー日本代表でもキャプテンとしてチームをまとめた廣瀬俊朗。同じ大阪府吹田市出身で、ともに誰もが認めるチームリーダーという共通点を持つ2人。そこで今回は彼らの特別対談が収録された書籍『キャプテンの言葉』の抜粋を通して、チームスポーツにおけるリーダー論、両競技の課題と可能性についてひも解く。今回はアマチュアの学生とトップレベルの大人のまとめ方の違いについて。
(文=宮本慎也、廣瀬俊朗 写真=YUTAKA/アフロスポーツ)
「自分は自分」でいい。社会人時代の手痛い失敗
廣瀬:キャプテンという話で言えば、僕はむしろ大学時代よりも社会人のときに大きな失敗を経験しましたね。
東芝で入社4年目(2007年)にキャプテンになったのですが、前任のキャプテンの冨岡鉄平さんという方がいて、自分がキャプテンを引き継いだとき、この方の真似をしようとしたんです。冨岡さんは歳が僕の5つ上なんですが、すごく人望があって、何よりも発する言葉一つひとつに説得力がありました。僕もリスペクトしていたのですが、「こういうキャプテンをみんなが求めているんだ」という意識が僕の中で強くなりすぎてしまって、みんなの前でしゃべるときも、「こういうことを言ったら、みんなはどう考えるかな」とか、冨岡さんと同じことをやろうとしたんです。それで逆に信頼を失ってしまって。
冨岡さんがキャプテンをしてトップリーグを3連覇し、黄金時代を迎えつつあったチームを、僕がキャプテンになって4位に落としてしまったんです。チームメイトから、「リーダー不在だった」と厳しい言葉を投げかけられたこともありました。言葉としては同じことを言っているのに、冨岡さんはみんなを惹きつけられて、僕が言っても全然響かない。「何が違うんだろう?」と、いろいろと考えさせられました。
宮本:それはたぶん、無理して合わせていたからじゃないですかね。そうすることによって、自分がなくなるんだと思うんですよ。そういうのって見ている側には伝わるから、「あぁー、あの人の真似してるのか」とか、ちょっと冷めた感じで見られるようになってしまう。同じやり方だったとしても、周りからの見え方が違うんです。
廣瀬:まさにそうだったと思います。富岡さんからキャプテンを引き継いだとき、「お前が日本一のキャプテンにならないと、チームは日本一になれない」と言われたんです。でも自分の中に「日本一のキャプテン」のなり方や具体的なイメージがないから、それを無意識に富岡さんと重ねてしまって、追いかけていたんでしょうね。
「自分は自分」でいいんですよね。前任者を過剰に意識しすぎてはいけないし、かといって否定する必要もない。それを痛感しました。
学生と社会人の違い。幅広い層の大人をまとめる難しさ
宮本:基本的には、たとえば東芝だったら東芝、慶應大だったら慶應大、僕で言えば同志社大、プリンスホテルと、それぞれにみんなチームが時間をかけてつくってきた伝統があるので、そこさえ守っていたら、あとはもう自分の色でいいと思うんですよ。いろんなタイプのキャプテンがいていいし、そこで自分が無理をしていると、絶対相手に伝わりますから。
でもそのとき、やってるときって、なかなか自分ではわからないんですよ。だから、そうやって真似してしまうことがある。たぶん廣瀬さんも、そんな感じだったんじゃないですかね。やっぱり無理なくできるのが一番いいんだと思います。見ているほうも、自然に見えるでしょうから。そしたら見え方も全然変わってくるはずなんです。
廣瀬:確かにあのときの僕は、無意識のうちにそうやって無理をしていましたね。
学生と社会人の違いとして、まず社会人というのは、チームに幅広いいろんな年代の選手がいるということがあります。当時の東芝にも、高校を卒業したばかりの選手から30代の選手まで、単純に10歳以上の開きがあったし、その中には前のキャプテンもいる。ここの特徴、難しさというのをすごく感じました。
それに加えて、社会人というレベルの中で、ラグビーがうまい人もいるし、経験が豊富な人もいる。その中で自分がキャプテンとしてどうチームをまとめていくかということで、「これはプレー以外のところでもいろいろ頑張らなあかんな」というのは、やっぱり社会人になってから、より考えるようになったことでした。そこで「なんのために勝つのか」とか、チームにおける「大義」に意識が向くようになって、そういった話をみんなの前でもしていましたね。
そもそも大学のときには、ラグビーの技術の部分では、チームの中である程度プレーで引っ張れたんですよ。まずはそこでチームメイトのリスペクトが得られていることで、何か言葉を発しても浸透しやすい。それが社会人になったら、僕なんかはもうそのアドバンテージみたいなものはなくなりましたから。そういうところでも、結構違っていたような気がします。
レギュラーじゃない選手がキャプテンをやるケース
宮本:おっしゃってること、わかりますよ。これは僕も同じなのですが、人よりもプレーで優れているから、普通にやっていればある程度信頼が得られるということ。これが高校とか大学、いわゆるアマチュアの段階ではできるんです。
でも、プロ野球とか、ラグビーでも社会人のトップリーグのレベルまで来たら、ホンモノが生き残ってくる世界ですからね。もう「プレーで圧倒的に」というのは難しくなるんです。そうなったときに、やっぱり難しさは当然出てきますよ。「お前、うまくもないのに黙っとれ」と言われたら、普通は何も返せなくなっちゃうし、そう言われないかって自分でも考えますから。それでも「おい、お前ら」って言えるヤツは、なかなかいないでしょう。
廣瀬:そうなんですよ。これはどんなスポーツも共通でしょうね。
宮本:だから、たまに高校とか大学で、レギュラーじゃない子がキャプテンをやるというケースがあるじゃないですか。僕、あれはすごいなぁと思うんです。いや、かなり大変なはずですよ。
廣瀬:野球はレギュラーじゃない選手がキャプテンをやるケースって、結構多いんですか?
宮本:どうなんですかね? 数に関してはわかりませんが、精神的にしっかりしていて、チームに良い影響を与えられるような人物であれば、補欠であってもキャプテンを任されるような選手は結構いると思います。僕の息子がお世話になっていた東海大菅生高校でも、レギュラーではない子がキャプテンをやって、その子がすごくいい子で、チームがよくまとまっていたという学年がありましたから。
廣瀬:強豪校でもそういう感じなんですか。まあどんな立場でやっても、キャプテンはいろんなプレッシャーがあって大変ですもんね。それならレギュラーとか控えに関係なく、向いている人間を探したほうがいいもんなぁ。自分からやりたいと言う人がどれだけいるんですかね。
今はベンチ入りのメンバーも投票で決める?
宮本:だから最近は投票で決めるチームが増えているじゃないですか。それで昔とは傾向が変わってきているのかもしれないです。監督の主観ではなく、みんなが見て、「やっぱりコイツがやらないと」みたいな子。
今はもうベンチ入りのメンバーでも投票しているチームがありますから。エースとか4番打者とか、レギュラーの軸のところに関しては、選手たちもみんな勝ちたいんだから、その子のことが好きだろうと嫌いだろうと誰が見ても実力のある子に投票しますよね。でも背番号15番以降とかになってくると、誰が入ってもそんなに差はないでしょう。そしたら3年生でメンバー入りの線上にいる子なんかは、一生懸命やっているのを同級生も見ているから、「この子を入れてあげたい」って投票して、その子が入ることで、下級生の本当なら入れそうな実力の子が外れることになったりとか。
廣瀬:へぇー、そういう文化があるんですね。微妙ではあるけど、選手が自分たちで決めていることですもんね。そこには責任も伴うから、いい加減なことはできないわけで。
宮本:そうです。でも、見方によっては、緩くなっていますよ。それも時代で、仕方がないんでしょうけど。昔だったら監督が全部決めて、背番号1番から20番まで発表して、選手はあれこれ文句があっても、そこで割り切ってやっていたわけじゃないですか。今どきは、選手だけじゃなくて保護者たちもあれこれ言ってきたりしますから。監督の責任回避と言ったら言い過ぎだけど、「お前らで決めたんだろ」みたいな。
そのあたり、ラグビーではどんな感じなんですか? 野球とはまた違うハードさというか、体をぶつけあうスポーツなので、ある程度のレベルになったら、キャプテンも絶対的な統率力みたいなものがなかったらチームが動きませんよね。
廣瀬:あんまりヘタなことはできないというのはあると思います。ただラグビーも、ちょっとポテンシャル的には劣っていても、常に一生懸命やるとか、チームのためにめっちゃ頑張るとかっていう選手は、チームメイトにリスペクトされるんですよね。そういった意味では、試合に出られない人でもキャプテンになりうるのかなと思います。
本当に面倒くさい。「なんでそいつを慕う?」なベテラン
宮本:高校野球だと、野球の技量はそんなに高くないんだけど、チーム内でやけに人望がある、人気があるヤツっているんです。影響力があるから監督もとりあえずメンバーに入れたりするんだけど、でも実際、そういう子って、たとえメンバーには入れなかったからといって、ソッポを向くようなことは基本的にないんですよ。周りから好かれるということは、自分の境遇が悪い中でも、ちゃんとやっているからじゃないですか。だからそういう人間性の子は、ベンチに入れなくてスタンドにいても、応援とか、一生懸命やってくれますけどね。
廣瀬:ラグビーにもいますよ、そういう子。なかなか結果が出なくて、自分でも選手として「ちょっと厳しいかな」というのはわかっていると思うんです。それでもやっぱりみんなが見ているんで、心がチームから離れていたら、だんだん信頼をなくしていくものなんですよね。そこでそんな立場になっても頑張ってくれる。
ただ、これが社会人くらいになるとちょっと複雑なところがあって、これまでずっとレギュラーで試合に出ていたベテラン選手とかが、意外と影響力あるんですよ。こういう人がメンバーを外れたときに、ソッポ向かれると……。
宮本:厄介ですよね。口ばっかりで。
廣瀬:そうそう。本当にそう(笑)。
宮本:「何やってんだよ!」みたいなヤツ、プロ野球界にも結構いますよ。口だけ達者で、「ああやって、こうやったほうが」とか言うんですよ。こっちは「じゃ、お前がやれよ」と思いますけどね。いますよね。一番面倒くさいわ、それ。
やっぱり楽なほうに行くヤツはいるんです。「なんでそいつを慕う?」みたいなヤツは、やっぱ出てきますよ。これが本当に面倒くさい。
廣瀬:おそらくどこのチームにもありますよね。そういう選手をどう扱うのか、という問題が。
宮本:だから、ここにAとBという選手がいて、「(起用するのは)どっちだ?」というときに、正当な競争をさせられる監督が、僕はすごいと思うんですよ。これが自分の好みに走っちゃったりすると、選ばれなかったほうが絶対にクサるんで。でもそれはそれで、監督のやろうとしている戦い方に合っているからこちらを選ぶわけなんで、それも「好み」ということになるのかもしれませんけど、こればかりは仕方がないですよ。
そこを曖昧にしたら、別の選手がソッポ向く可能性だってあるから、ここの扱いを監督とかはすごく気にしなきゃいけないんです。下のほうの選手だったら、「俺は関係ないから」とか違う方向を向いていたって、コイツがすごい影響あるかって言ったら、まったくないですからね。何も気にする必要はない。
廣瀬:そこはキャプテンというよりも、やっぱり監督の判断になってきますね。まあ微妙なところです。キャプテンとしては外された選手のサポートが大事になってくる。
(本記事は東洋館出版社刊の書籍『キャプテンの言葉』から一部転載)
【第1回連載】当時のPL学園野球部はケンカの強いヤツがキャプテン!? 宮本慎也、廣瀬俊朗が語るチームリーダー論
【第3回連載】野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」
【第4回連載】ラグビーにおけるキャプテンの重要な役割。廣瀬俊朗が語る日本代表回顧、2人の名主将が振り返る苦悩と後悔
【第5回連載】プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?
<了>
「敗者から勝者に言えることは何もない」ラグビー稲垣啓太が“何もなかった”10日間経て挑んだ頂点を懸けた戦い
「キサンッ、何しようとや、そん髪!」「これを食え」山中亮平が受けた衝撃。早稲田大学ラグビー部4年生の薫陶
ダルビッシュ有が明かす教育論「息子がメジャーリーガーになるための教育をしている」
大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?
[PROFILE]
宮本慎也(みやもと・しんや)
1970年生まれ、大阪府出身。PL学園高校、同志社大学を経て、社会人野球のプリンスホテルに入社。1995年ドラフト2位でヤクルトスワローズに入団。1997年からレギュラーに定着し、1997年、2001年の日本一に貢献。アテネオリンピック野球日本代表(2004年)、北京オリンピック野球日本代表(2008年)ではキャプテンを務めた。2006年WBCではチームのまとめ役として優勝に貢献。2012年に2000本安打と400犠打を達成。ゴールデングラブ賞10回、オールスター出場8度。2013年に43歳で引退。現役引退後は野球解説者として活動。2018年シーズンからは東京ヤクルトスワローズの1軍ヘッドコーチに就任。2019年辞任。その後、NHK解説者、日刊スポーツ評論家の傍ら、学生野球資格を回復し、学生への指導や臨時コーチなどを務める。「解体慎書【宮本慎也公式YouTubeチャンネル】」も随時更新中。著書に『歩 -私の生き方・考え方-』(小学館)、『洞察力――弱者が強者に勝つ70の極意』(ダイヤモンド社)、『意識力』(PHP研究所)などがある。
[PROFILE]
廣瀬俊朗(ひろせ・としあき)
1981年生まれ、大阪府吹田市出身。5歳からラグビーを始め、大阪府立北野高校、慶應義塾大学、東芝ブレイブルーパスでプレー。東芝ではキャプテンとして日本一を達成した。2007年には日本代表選手に選出され、2012年から2年間はキャプテンを務めた。現役引退後、MBAを取得。ラグビーW杯2019では国歌・アンセムを歌い各国の選手とファンをおもてなしする「Scrum Unison」や、TVドラマへの出演など、幅広い活動で大会を盛り上げた。同2019年、株式会社HiRAKU設立。現在は、スポーツの普及だけでなく、教育・食・健康に関する活動や、国内外の地域との共創に重点をおいたプロジェクトにも取り組み、全ての人にひらけた学びや挑戦を支援する場づくりを目指している。2023年2月、神奈川県鎌倉市に発酵食品を取り入れたカフェ『CAFE STAND BLOSSOM~KAMAKURA~』をオープン。著書に『ラグビー知的観戦のすすめ』(KADOKAWA)、『相談される力 誰もに居場所をつくる55の考え』(光文社)、『なんのために勝つのか。ラグビー日本代表を結束させたリーダーシップ論』(小社)などがある。
この記事をシェア
RANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性
2026.01.09Career -
名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実
2026.01.09Career -
「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年
2026.01.09Career -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み
2026.01.07Education -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体
2026.01.05Training -
あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由
2025.12.26Career -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性
2026.01.09Career -
名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実
2026.01.09Career -
「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年
2026.01.09Career -
あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由
2025.12.26Career -
雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」
2025.12.25Career -
なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”
2025.12.24Career -
次世代ストライカーの最前線へ。松窪真心がNWSLで磨いた決定力と原点からの成長曲線
2025.12.23Career -
「まるで千手観音」レスリング97kg級で世界と渡り合う吉田アラシ、日本最重量級がロス五輪を制する可能性
2025.12.19Career -
NWSL最年少ハットトリックの裏側で芽生えた責任感。松窪真心が語る「勝たせる存在」への変化
2025.12.19Career -
「準備やプレーを背中で見せられる」結果に左右されず、チームを牽引するSR渋谷・田中大貴の矜持
2025.12.19Career -
「日本の重量級は世界で勝てない」レスリング界の常識を壊す男、吉田アラシ。21歳の逸材の現在地
2025.12.17Career