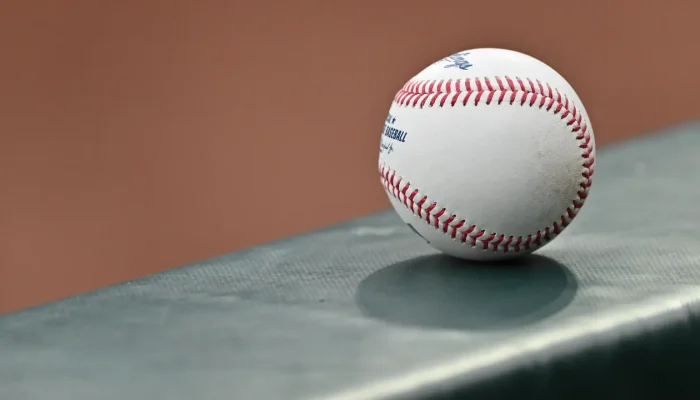「根性って何だろう?」空手家・月井隼南が後悔する、ケガにつながる行き過ぎた根性論とは
日本で数々の空手の大会で優勝を果たし、現在はフィリピン代表として東京五輪出場を目指す異色の空手家・月井隼南。SNSでの彼女の「つべこべ言わずに余計なこと考えずに、とにかくたくさん練習しろ!っていう根性論が当たり前の世界で、その通りにやって両膝の手術10回することになった私からすると、根性はいろんなことを考えた先にあるものであって、初めからそれで解決しようとするのは危なすぎます」との投稿が多くの反響を呼んでいる。行き過ぎた「根性論」はいまでも頻繁にニュースになり、議論を起こしている。月井自身が経験した出来事を振り返り、ケガの放置にもつながる根性論が抱えるリスクを考える。
(インタビュー・構成=布施鋼治、撮影=九島亮)
幼少期から最も身近なフレーズだった「根性」
「根性って、いったい何だろう?」
月井隼南が初めて根性という言葉に疑問を抱いたのは、高校1年生の終わりに左膝の靱帯を損傷したことがきっかけだった。
月井は現在フィリピンのナショナルチームに所属し、東京五輪出場を目指す異色の空手家である。最初の指導者は海外4カ国で指導歴のある父・月井新だった。新から直接「根性を出せ」といった類の言葉をかけられた記憶はないが、別の道場との合同練習を行う時には、他の指導者から似たような言葉を聞いた記憶がある。
ただ、名指しで言われた記憶はほとんどない。その理由について月井は「私は生まれつき気が強かったので、どちらかといえば、周囲から『根性がある』と言われていたからかもしれない」と分析する。
「自分でも我慢強いほうだと思っていました」
我慢強い性格が、のちの自分を苦しめることになるとは知る由もない。合同練習中、「根性を出せ」というセリフが響きわたることは月井にとって日常の風景だった。
「誰もがそれを疑わない環境にいたと思います。子どもの頃は、とくに違和感を感じることもなかったですね」
合同練習の際、1000本突きという稽古の時には、やっていくうちにみな徐々に集中力が失せていく。そうすると、陣頭指揮をとる指導者は決まって『根性を出せ』とゲキを飛ばした。月井にとって根性は最も身近なフレーズだった。
「疲れてきたけど、自分を奮い立たせる意味で、まだまだここからみたいな時に使う言葉でした。自分が健康でいる時には、とくに何も感じなかったですね」
チームから外されてしまうのではないか
靱帯を損傷するまで、月井の空手人生は希望と栄光に包まれていた。『全日本少年少女空手道選手権大会』6年女子個人組手や『全国中学生空手道選手権大会』女子個人組手で優勝している。しかし、冒頭で記した左膝靱帯のケガは月井を天国から地獄へと突き落とした。
悲しいかな膝に違和感を覚えても、すぐ病院に行くようなことはできなかった。それが縦社会の流儀であり、その不文律のマナーには従わなければいけないと信じていた。まずは先輩に病院に行きたいことを遠回しに伝えた。
「私も若くて純粋だったので、行きたいというか、行ったほうがいいのかどうかもわからなかった」
高校からは親元を離れ、大阪の強豪校での寮生活。周囲には、自分から安易に病院に行くとは言えない空気が漂っていた。寮で相談する人もいなかった。
「2人の同期は心配してくれたけど、先輩の言うことには従わないといけない。たぶん同期の中では私が一番気が強かったので、同期はもっと言えなかったと思う」
結局、月井はストレートに病院に行きたいとは言えなかった
チームから外されてしまうのではないか。すごく責められるのではないか。
病院に行きたいという気持ちより、危機感の優先順位のほうが上にあった。月井は「同じような雰囲気は強豪校だったら、どこにでもあった」と思い返す。
恐怖を覚え、身を萎縮させた言葉「いちいち痛がるな」
「ケガをしたり、熱が出たら、すぐ病院ではなく、まずは様子見なんですよ」
様子を見て快方に向かうケガもあれば、根本的な治療をしなければ悪くなるケガもある。月井は後者だったが、月井のケガの具合をわかってくれる者は皆無だった。
「様子見でも、あまりにもひどい状態だったら練習はできない。でも練習することが普通の世界なので、『練習していない=頑張っていない』ということになってしまう」
月井の左膝は腫れだし、まっすぐに歩くことすらままならなかった。左足を引きずるように歩いていると、先輩から信じられないような一言を投げかけられた。
「いちいち痛がるな」
月井は恐怖を覚え、身を萎縮させた。
「先輩にそう言われると、その上の先生にはもっと言い辛くなる。『先生に言ったら怒られてしまうのか』と思ったら本当に言えなかった。道場の片隅で膝に負担がかからないように筋トレをしながら、できる練習だけ中に入ってやるしかなかったですね」
周囲の冷やかな視線。だましだまし練習する日々
練習を休むことはなかったが、さすがに自分でもまずいと思い、高校の近くにある小さな病院に自ら足を運んだ。
「でも、CTスキャンもなく、レントゲンを撮ってもらうだけでは『骨に異常はない』と診断されるだけでした」
接骨院に行くと、「腱か靱帯を痛めているかもしれない」と言われた。2週間ほど様子を見ながら練習をすると、靱帯の腫れは引いてきた。そうなると、歩く分には問題はない。月井は通常の練習に戻ったが、以前とは明らかに違っていた。
「踏ん張りが利かないので、わけのわからないところでカクッと倒れてしまう」
月井本人にケガに対する知識がなかったことも、膝の具合をより悪化させる要因となった。靱帯は一度伸びると機能しないということを知ったのは、ずっとあとになってからのことだった。
「腫れが引いたのは靱帯の炎症が収まっただけで、靱帯の神経自体は壊れていたわけですからね」
周囲に靱帯を損傷した選手がいなかったこともマイナスに働いた。月井が突拍子もないタイミングで転倒を繰り返すと、「休みたいからわざと倒れている」と陰口をたたかれるようになった。周囲の冷やかな視線を浴びながら、月井はだましだまし練習をするしかなかった。
根性がなければスポーツをやってはいけない?
地力もあったし、それまでの貯金がモノをいったのだろう。大会に出ると勝ち上がるにつれ、患部は腫れ上がったが、それでも勝つことはできた。ポイントを先取したら逃げ切る。月井は自然と体をかばいながら闘う術を覚えていた。
「個人戦でも団体戦でも、ずっと全国制覇をしていました。でも、そうなると、『どこかケガをしていることは当たり前』という雰囲気になる」
同期、あるいは先輩の中には半月版を損傷している者もいたが、ケアの仕方は決まっていた。「ちょっと腫れてきたら水を抜きに行き、3日後には練習に戻る。そういうルーティーンが普通でしたね」。
月井の場合、靱帯という目に見えない場所だったことも響いた。
「そもそも格闘技は歯が折れても普通にそのまま平気で練習を続けるような世界じゃないですか。何かしら痛いとか腫れているというのは通常なんですよね。逆にいえば、昔はもっとヤバかったのかもしれない」
月井の一言に50代半ばの筆者は、昭和の格闘技の稽古を思い返した。
「根性だよ、根性!」
取材先でいったい何度耳にしたことだろうか。受け取り方によっては、根性がなければスポーツをやったらいけないのではないか。そんな錯覚すら覚えた。
スパルタ指導が注目を浴び、称賛された1964年東京五輪
そもそもスポーツと根性はセットとみなされてきた節がある。例えば、1964年の東京五輪。五輪種目として初めて開催された女子バレーでは大松博文監督のスパルタ指導が注目を浴び、称賛された。
コートの上で動けなくなっても、ボールをぶつけられ、立ち上がり回転レシーブの練習を再開する。たとえ暴力的な仕打ちを受けたとしても、歯を食いしばりながら、自己の限界を一歩超える。それが根性の定義であり、日本人特有の美徳だったのではないか。
日本女子バレーの流れは『巨人の星』や『アタックNo.1』といったスポーツ根性モノの劇画や漫画に踏襲され、スタンダードなものになっていく。とはいえ、前回の東京五輪から50年以上の歳月が流れている。日本スポーツに横たわる根性論にも如実に変化が現れた。例えば大相撲で過度なシゴキがあれば、刑事事件になる。スポーツ科学的には効果がないといわれるウサギ跳びを強制したり、練習中に水飲みを禁じる運動部もほとんどなくなった。
その一方で高校野球児はいまだ丸刈りが主流だし、大学スポーツではパワハラ騒動があとを立たない。結局、根っこの部分は変わっていないのだろうか。月井は言う。
「周りから根性論のコントロールがすごいので、途中からわけがわからなくなるんですよ。判断できなくなる。それが異常であることに誰も気づいていない」
ナショナルチーム入りも果たし、休むという選択肢はなかった
痛む左膝をかばったせいだろう。高校2年の半ば、月井は右膝も痛めていることに気づいた。インターハイで優勝したあと、東京の実家に帰省した月井は父とともに大病院に行き初めてMRIを撮りに行った。
しかし、撮る角度が悪かったのか、担当医は「靱帯は切れていない」という診断を下した。その時の診断書に「損傷」と書かれていなかったことを月井は鮮明に記憶している。「あれは本当にアンラッキーでした。損傷と診断されていれば、次の治療に踏み出すことができたのに」。
小学校の頃から月井の体のメンテナンスをしている五反田トレーニングセンターの永田一彦からは「ゆるいし、僕の感覚的にはもう完全に切れている」と言われた。しかしながら永田はフィジカルトレーナーという立場なので、診断書を書くことはできない。
永田は「もしやるなら」と前置きした上で、月井にこう告げた。「だましだましやるのも辛いと思うので、テーピングでガチガチに固めてやるしかない」
ケガをしているにもかかわらず、成績を残していた月井は高校3年の時には日本のナショナルチーム入りを果たす。月に1回は厳しい練習メニューが待ち構える強化合宿があった。休むという選択肢はなかった。
ある強化合宿の前、月井は大阪の大病院に行き、患部の水を抜いてもらおうと考えた。診断した医師は眉間に皺を寄せ、月井に告げた。「水ではなく、血がたまっています。99%、靱帯が損傷していると思う」。
左膝に痛みを感じてから、2年以上の歳月が流れ……
しかしながら腫れたままだとMRIでも写らないので、その時は予約だけを入れた。検査結果が出ているわけではないので、月井はそのまま強化合宿に参加した。その際、ある関係者には事前に「靱帯を損傷している可能性がある」と打ち明けた。
その人からは「だったら、できるところまでやったほうがいい」という答えが戻ってきた。実際合宿で動いてみると、よく転んだ。動く分にはまだ我慢できたが、練習後アドレナリンが切れたあたりに歩くと思い切り痛みを感じる。月井の異変を察した別の関係者から声をかけられた。
月井は正直に自分の思いを打ち明けた。その関係者も「たぶん切れているだろう」という見解だった。「でも、僕に止める権利はないので、痛み止めを飲んで頑張るしかない」。意見は十人十色。さらにまた別の関係者にケガについて告げると、一喝された。
「アホか。靱帯を損傷していたら歩くのも無理や。お前のは気持ちの問題や」
気持ちのせいと突き放してきた関係者は3~4人目だった。そういう時に限って「指導者の言うことは絶対」という刷り込みが頭をもたげてくる。それまでの痛みや疑問を忘れたかのように、高3だった月井は頷くしかなかった。
「あっ、やっぱり靱帯が切れていても問題はないんだ」
止めてくれる大人はゼロだった。月井も周囲も、靱帯損傷についてあまりにも無知だったといわざるをえない。高3の1月に出場した全国規模の大会では、月井の異変に誰もが気づき始めた。
「あの子、なぜあんなに何度も転んでいるの?」
試合中だけではなく、主審から辞めがかかった直後にも転ぶのだから無理もない。月井の心は揺れ動いた。「仕方ない」と思う一方で、「私は逃げに入っているのか」と自分を責めた。
そのあたりから彼女の評価は「センスはあるけど、根性がない」に変わっていく。
その直後、大阪でMRIを撮ると、靱帯が断裂していることが判明する。何を信じていいのか、わからなくなった。左膝に痛みを感じてから、すでに2年以上の歳月が流れていた。
<了>
「いつもやめたかったし、いつも逃げ出したかった」登坂絵莉、悩まされ続けた苦難を告白
「世界一美しい空手の形」宇佐美里香 万人を魅了する“究極の美”の原動力となった負けじ魂
「日本の柔道はボコボコ、フランスはユルユル」溝口紀子が語る、日仏の全く異なる育成環境
なぜ喜友名諒、清水希容は圧倒的に強いのか? 元世界女王に訊く、金メダルへの道筋と課題
[アスリート収入ランキング2019]トップは驚きの137億円! 日本人唯一のランクインは?
PROFILE
月井隼南(つきい・じゅんな)
1991年9月30日生まれ、フィリピン出身。空手家。空手師範の日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれ、3歳までフィリピンで育ち、その後日本へ。小学6年、中学、高校の全国大会、インターハイ、新潟国体でそれぞれ優勝。幼少期より数々の大会で活躍するも、学生時代はケガに悩まされる。ケガからの復帰後、2017年より単身フィリピンへ移住。来年に延期された東京五輪より正式種目になる空手で、フィリピン代表の一員として出場を目指している。
この記事をシェア
KEYWORD
#INTERVIEWRANKING
ランキング
LATEST
最新の記事
-
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯
2026.01.30Career -
ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件
2026.01.23Career -
ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地
2026.01.23Career -
世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断
2026.01.23Career -
女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道
2026.01.20Career -
丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化
2026.01.19Career -
伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”
2026.01.16Career -
史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北
2026.01.16Career -
狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生
2026.01.16Career -
代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地
2026.01.14Career -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion
RECOMMENDED
おすすめの記事
-
森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略
2026.02.02Opinion -
「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂
2026.01.13Opinion -
高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由
2026.01.09Opinion -
“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏
2026.01.09Opinion -
高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相
2026.01.07Opinion -
アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神
2025.12.26Opinion -
「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地
2025.12.23Opinion -
「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実
2025.12.23Opinion -
なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋
2025.12.17Opinion -
中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”
2025.12.10Opinion -
『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏
2025.11.28Opinion -
デュプランティス世界新の陰に「音」の仕掛け人? 東京2025世界陸上の成功を支えたDJ
2025.11.28Opinion